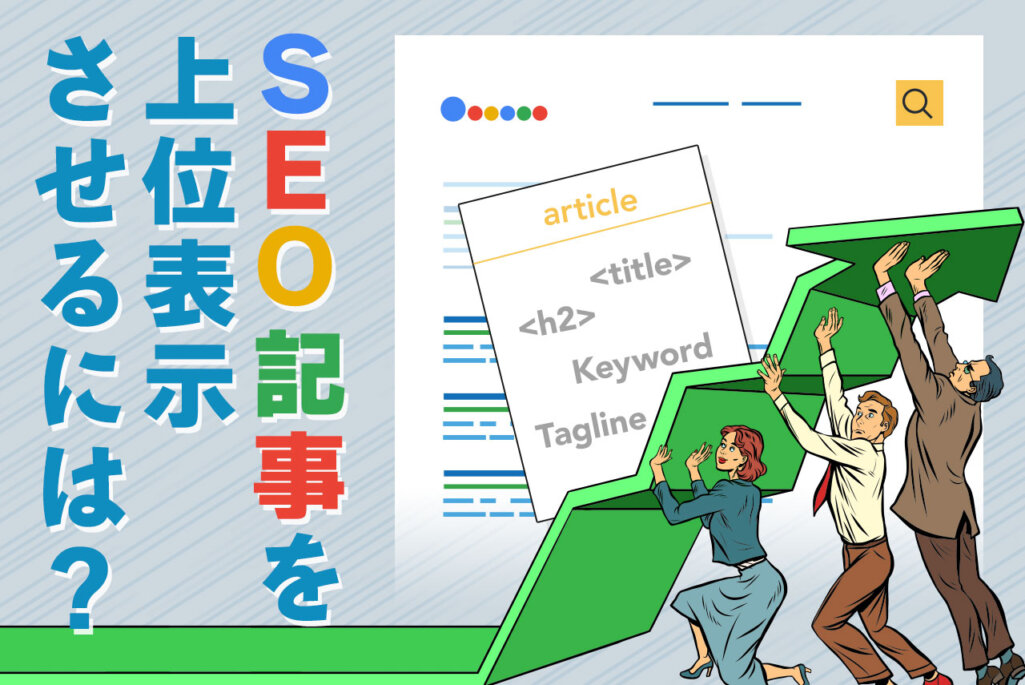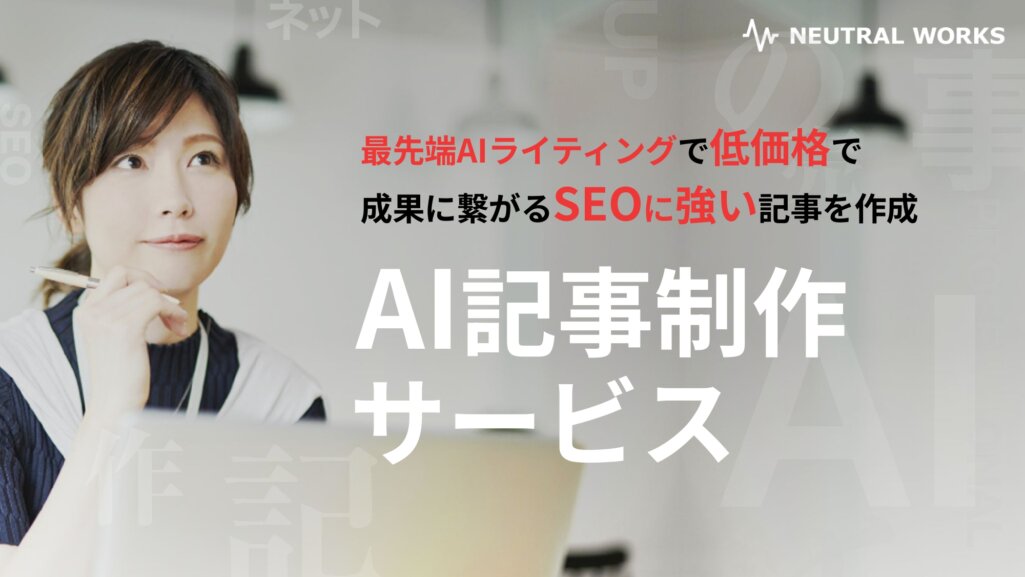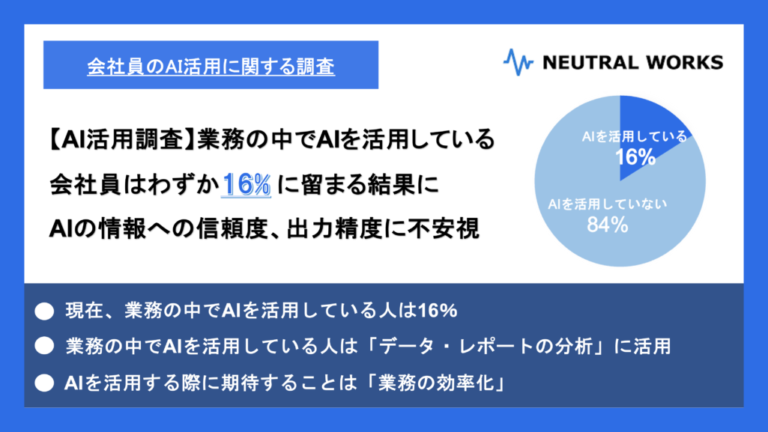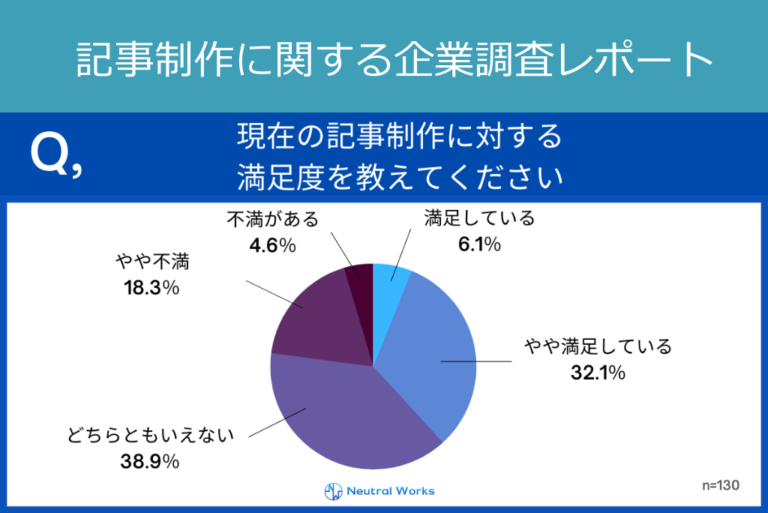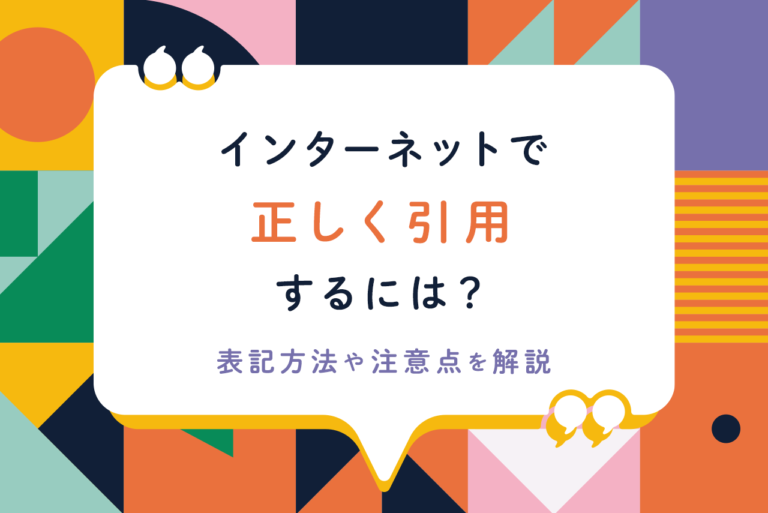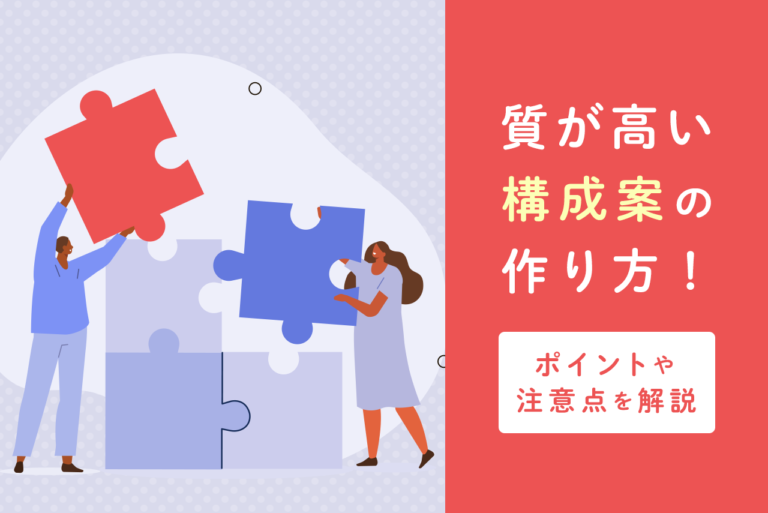この記事のポイント
この記事でおさえておきたいポイントは以下です。
-
SEO記事とは何か
-
SEO記事とは、ユーザーの検索意図に合致し、Googleが評価しやすい内容で構成された記事です。記事は、リード文や見出しなどの要素を効果的に使い、ユーザーにとって価値ある情報を提供することで、検索順位向上を目指します。
-
SEOで評価されにくいページとは
-
SEOで評価されにくいページは、「タイトルと内容が一致していない」「ユーザーの求める情報がない」「情報が古い」ページです。これらの要素は検索エンジンからの評価を低下させ、結果として検索順位が下がる可能性があります。
-
SEO記事を作る際の注意点
-
SEO記事作成の注意点は、独自性のあるコンテンツを心がけ、無理にキーワードを盛り込まないことが重要です。また、誰が読んでも分かりやすい内容を意識して、記事のテーマと内容が一貫するようにすることが求められます。
せっかく記事を書くなら、やはりSEOで上位表示させたいですよね。しかし、なかなか上位表示がされなかったり、アクセス数を集めることができなかったりと、苦労している方も多いのが現状でしょう。
「キーワードを織り交ぜるだけ」「伝えたいことを一方的に伝えるだけ」といった書き方では、なかなか評価されません。SEOで上位表示を狙う記事を書くためには、読み手であるユーザーを意識した記事構成にしていくことが重要です。
そこでこの記事では、記事の組み立て方を中心に、直近のSEOの評価傾向やSEO対策で重要な項目を解説します。
当メディア「QUERYY(クエリー)」を運営する株式会社ニュートラルワークスでは、無料のSEOセミナーを開催しております。
SEOのプロが、SEO対策の基礎/外部対策/内部対策/テクニカル/コンテンツなど、最新情報を分かりやすく解説しておりますので、ぜひご視聴ください。
<無料>資料ダウンロード
AI記事作成代行サービス
SEOのプロがAIを活用した記事を制作!(1万円/1記事)
SEOで順位が上がらない担当者様へ
実力のあるSEOコンサルタントが本物のSEO対策を実行します。
SEO会社に依頼しているが、一向に検索順位が上がらない・・・。
SEO対策をSEO会社に依頼していてこのようなお悩みはありませんか?SEO対策はSEOコンサルタントの力量によって効果が大きく変わるマーケティング手法です。弊社では価値の高いSEOコンサルティングをご提供するため、厳選した業界トップクラスの大手SEO会社出身で大規模サイト運用経験のあるトップコンサルタントが在籍しております。
目次
SEO記事とは

SEOとは、検索エンジンを利用したマーケティング手法のひとつです。Googleなどで検索した結果、自社のページが表示されることでユーザーに自社の商品やサービスを認知させることができます。
検索結果に上位表示されるほど効果が高く、ページの来訪者が多くなりやすいです。検索したユーザーにとって有益な情報を提供していると評価された記事ほど、上位表示されるという特徴があります。
SEO記事とは、ユーザーにとって有益となる記事を作成し、SEO評価が高く検索結果に上位表示されることを狙った記事を指します。多くのユーザーが検索エンジンを利用してリサーチを行うため、上位表示される評価が高い記事があれば、多くのユーザーを集めることが可能です。また、広告費をかけないためコストをかけずに集客することができます。
 魅力的な記事の書き方!記事を書くときのポイントとは?
魅力的な記事を書くために必要なポイントを解説しています。ターゲットの設定、記事構成の工夫、視覚的な工夫や読みやすさの向上など、読者を引き付けて行動を促すための具体的なテクニックを詳しく紹介します。
魅力的な記事の書き方!記事を書くときのポイントとは?
魅力的な記事を書くために必要なポイントを解説しています。ターゲットの設定、記事構成の工夫、視覚的な工夫や読みやすさの向上など、読者を引き付けて行動を促すための具体的なテクニックを詳しく紹介します。
SEOで評価されやすい記事
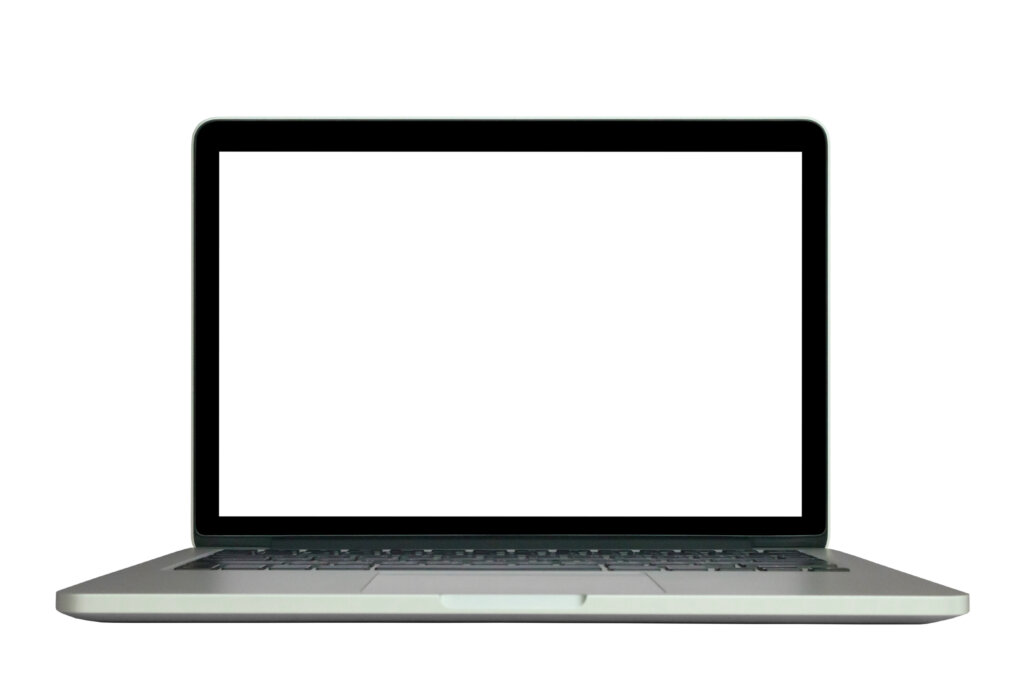
SEOで評価されやすい記事は、ユーザーのニーズに応えたページです。その理由は、Googleがユーザーのニーズを満たすことを何よりも優先しているからです。
Google検索エンジンは、ユーザーがなにかしらの悩みをもって検索したキーワードに対してベストアンサーを示すページを上位表示するようになっています。その証拠に、Googleは「10の事実」といった考えを設けており、ユーザーフレンドリーな検索エンジンであり続けることを努めています
また、ユーザーのニーズに応えるページを作成する上で、ニーズには2種類あることを理解しておきましょう。
1つ目は「顕在ニーズ」と呼ばれるもので、ユーザー自身が必要としているものを理解しているパターンです。この場合、ユーザーへのアプローチは比較的簡単です。
そして2つ目は「潜在ニーズ」と呼ばれるもので、ユーザー自身が必要としているものに気が付いていないパターンです。
この場合はユーザーへのアプローチが難しく、ユーザーが解決したいことの根底を探り、「本当に必要なのはこれではないか?」といった提示が必要となってきます。このように、ニーズには2種類あるので、どちらのニーズも満たしていくことがポイントとなります。
つまり、ユーザーにとってわかりやすく、見やすく、使いやすいページかどうかが評価の基準となっています。そのため、自分が伝えたい内容を優先するのではなく、ユーザーの悩みに応えることを優先したページ作りが、SEO対策の肝となることを覚えておきましょう。
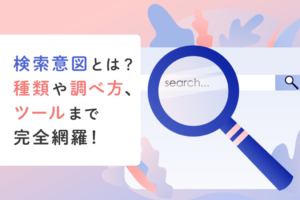 検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説
効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。
検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説
効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。
また、SEO記事で重要な要素を下記に纏めましたので、こちらもご参考ください。
| 大分類 | 中分類 | 評価指標 | 有効な対策 |
| コンテンツ | 質 | 検索ニーズ を満たす |
検索語句のニーズを満たすコンテンツ制作。検索者がページ遷移して、対象の検索目的を達成(解決)するコンテンツを作る。 |
| 体験に基づく 根拠ある内容 |
体験に基づく具体的な内容。独自性が高く閲覧者にとって有益な体験に基づくコンテンツを作る。 | ||
| 関連ページ 内部リンク |
該当コンテンツを補完する内部リンク。情報深掘りしたい時に、同一サイト内でニーズを満たせる内部リンク設置。(再検索させない) | ||
| 信頼性 | 事業領域 | コンテンツテーマは事業領域に親和性の高いものにする。 | |
| 専門家 | テーマの専門家による執筆/監修。専門性を伝えるためにオンライン上で対象人物の情報を発信。メディア出演や執筆など権威性や専門性が連想される情報をオンラインで発信。 | ||
| 関連被リンク | コンテンツに沿った関連性の高い被リンクを獲得。外部から多く引用されるコンテンツ(一次情報)は信頼性が高く評価される。 |
SEOで評価されにくいページ

一方、ユーザーにとって不便なページは評価が下がる傾向にあります。SEOで評価がされにくいページの特徴には、下記のような例があります。
- タイトルと記事の内容が一致していない
- ユーザーのほしい情報が掲載されていない
- 扱う情報が古い
- ページの読み込みに時間がかかる
- テキストのみのページ構成
例であげたものは、ユーザーにとって有益でなく、利用しにくい特徴の代表です。1つずつ理由をみていきましょう。
タイトルと記事の内容が一致していないページ
タイトルと記事の内容が一致していないページは、ユーザーにとって不便なページとなってしまいます。
何らかの悩みを持ったユーザーが関連するキーワードで検索し、タイトルを見て問題解決ができると期待してサイトへ流入します。しかしタイトルとコンテンツ内容が一致していないと、ユーザーが離れてしまうことは想像に難くないでしょう。
ユーザーのほしい情報が掲載されていないページ
同様に、ユーザーのほしい情報が掲載されていないページもユーザーには使いにくいです。タイトルのつけ方が正しくても、内容が薄ければユーザーの求める情報と異なるため、ニーズを満たしていないことになります。
情報が古いままのページ
また、コンテンツ情報が正しいとしても、ピックアップしている情報が古いままであるのはユーザーに不親切です。そのため信頼性が薄くなり、結果的にGoogleからの評価は下がってしまいます。
ユーザーに親切な記事を作成するには、こまめな情報の更新が大切となります。
ページの読み込みに時間がかかるページ
SEOでの評価項目は、コンテンツ内容だけではありません。ページの読み込みに時間がかかるサイトは、SEOで評価されにくいです。
やはりページが表示されるのを待つ時間が長いと使いにくいですし、ユーザーを待たせてしまい、結果離れてしまいます。
テキストのみのページ
そして、テキストのみとなっているページ構成も、評価が落ちる要因となります。テキストだけで画像やイラストがないと読みずらい、分かりにくいといった不満を持たせてしまいます。また、ユーザーにとって単調な印象になってしまいます。
SEOで評価されやすい記事を作るには

SEO記事とはユーザーのニーズに応えるページであることをご説明しました。ここからは、SEOで評価されやすい記事を作る方法について解説していきます。
上位表示させたいキーワード(SEO対策キーワード)を決める
上位表示を狙うためには、まずSEO流入を獲得するための対策キーワードを決めるところから始めましょう。対策キーワードはやみくもに決めてしまうと、思ったように集客ができないことがあります。また、集客できたとしても、ターゲットではないユーザーが集まってしまうことも。クオリティの低い集客だと、せっかくのSEO対策が無駄になる可能性があります。
そこで、以下では対策キーワード選びの3つのコツを紹介していきます。ひとつずつ解説しますので、コツを抑えてしっかりと対策キーワードを決めてからSEO記事作成に挑戦していきましょう。
対策キーワードを選ぶコツ1
対策キーワードを選ぶ1つ目のコツは、自社の商品やサービスを使っている顧客が検索しそうなキーワードを狙うことです。この方法では、対策キーワードを検索したユーザーの検索意図を想像して、自社のターゲットになりうるユーザーが検索しているキーワードかどうかを見極めることが重要となります。
例えばサイト制作会社のサイトを運営している場合、流入するであろうユーザーは「サイト制作」「LP制作 コツ」「ウェブマーケティング」などのキーワードを使用していることが考えられます。これらは対策キーワードとして設定することが可能です。
また、対策キーワードの幅を広げるなら、関連キーワード取得ツールを活用するのも良いです。関連キーワードとは、対策キーワードに対して関連しているキーワードを含めた複合語のことです。関連キーワードを調べることで、より詳しくユーザーが求めている情報を知ることができます。
例えば上記で想定した「ウェブマーケティング」に対して、「ウェブマーケティング 資格」「ウェブマーケティング 仕事内容」などのような関連キーワードがあります。前者と後者では、ユーザーが知りたい情報が異なっていることがわかります。
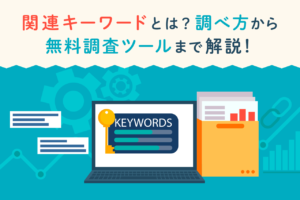 関連キーワードとは?サジェストとの違いや関連キーワードツールを紹介
関連キーワードは、SEO対策で重要な要素です。この記事では、関連キーワードの定義やサジェストとの違い、さらに関連キーワードツールの紹介を通じて、SEO効果を高める方法を詳しく解説しています。
関連キーワードとは?サジェストとの違いや関連キーワードツールを紹介
関連キーワードは、SEO対策で重要な要素です。この記事では、関連キーワードの定義やサジェストとの違い、さらに関連キーワードツールの紹介を通じて、SEO効果を高める方法を詳しく解説しています。
対策キーワードを選ぶコツ2
対策キーワードを選ぶ2つ目のコツは、対策キーワードにある程度の検索数があるかを確認することです。というのも、ターゲットになるユーザーの検索するキーワードであったとしても、ほとんど検索されていないニッチなキーワードだと、せっかくSEOで上位表示されても流入が見込めない可能性が高いです。
SEO記事を使って効果的に集客するためにも、検索数はチェックしておきましょう。目安としては、1位で表示された場合の平均クリック率は20%前後と推定されているため、そこから流入数を算出していくとよいでしょう。
例えば、「〇〇」という対策キーワードの月間検索数が1000だとすると、1位表示された場合の月間流入数は約200と推定することができます。この想定した数値が多いのか少ないのかを判断していきます。とはいえ、対策キーワードの検索数が多ければ多いほど良いというものでもありません。検索数が多くなるほど、同じキーワードを狙ってSEO対策している競合サイトが増えてきます。
するとSEOの難易度が高くなり、数多くいるライバルの中でより優れたコンテンツを生み出さなければなりません。ページが評価されるまでに時間がかかることも。
そこで、サイトを立ち上げてから手応えを感じるまでは、検索数が少ないキーワードから始めてみることがおすすめです。他のサイトが満たしていないようなニーズを狙ってキーワードを選定することによって、効率よく着実にアクセス数を集めることが見込めます。
 検索ボリュームの調べ方を解説!おすすめツールとキーワード選定の方法紹介
検索ボリュームは、特定のキーワードが検索エンジンでどれだけ検索されているかを示す指標です。この記事では、検索ボリュームの調べ方やおすすめのツール、効果的なキーワード選定の方法について解説しています。
検索ボリュームの調べ方を解説!おすすめツールとキーワード選定の方法紹介
検索ボリュームは、特定のキーワードが検索エンジンでどれだけ検索されているかを示す指標です。この記事では、検索ボリュームの調べ方やおすすめのツール、効果的なキーワード選定の方法について解説しています。
対策キーワードを選ぶコツ3
対策キーワードを選ぶ3つ目のコツは、対策キーワードに対してどのようなページが評価されやすいかを確認しておくことです。対策キーワードのチョイスができていたとしても、コンテンツ自体がユーザーのニーズを満たしていない、または検索エンジンからの評価を得ていないと、上位表示にはつながりません。
そのため、対策キーワードに対して、SEOで上がりやすいのはどのようなページなのかを事前に確認することが重要です。例えば、対策キーワードをもとに作成した記事ページが、現状上位表示されている記事と類似した内容であれば、問題ありません。
しかし、上位表示されているのが「商品一覧ページ」「ポータルサイトの検索結果ページ」といった商品ページが上がっている場合は、記事ページでの対策はかなり難しい可能性が高いので注意しましょう。
対策キーワードを実際に検索して、検索結果をみてみると、どのようなページがSEOで評価されやすいのかを把握することができます。対策キーワードを選定してコンテンツを作成する前に、確認しておくことをおすすめします。
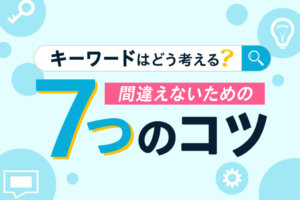 コンテンツマーケティングで成果を出すキーワード選定方法と7つのコツを総まとめ
この記事では、コンテンツマーケティングで成果を上げるためのキーワード選定方法と7つのコツを詳しく解説しています。効果的なキーワード選びの手順やポイントを学びたい方におすすめの内容です。
コンテンツマーケティングで成果を出すキーワード選定方法と7つのコツを総まとめ
この記事では、コンテンツマーケティングで成果を上げるためのキーワード選定方法と7つのコツを詳しく解説しています。効果的なキーワード選びの手順やポイントを学びたい方におすすめの内容です。
ターゲットとゴールの設定
記事構成を作る前に、ターゲットとゴールを設定することが重要です。ターゲットとは、対策キーワードで検索したユーザーのことを指しています。その際、そのターゲットがなぜこのキーワードを検索したのかを熟考することが大切です。ユーザー視点で熟考することによって、ユーザーが何に悩んでいるのかが見えてきます。
そして、どんな情報があれば解決するのかを考えましょう。そのページを読み終えた後に、ユーザーがどうなっているとユーザーの悩みを解決したといえるのかを考えることが、ゴールの設定となります。このように、記事構成の作成前にターゲットとゴールを設定しておくことで、ユーザーにとって読みやすい記事作成へと繋がります。
記事の構成を組み立てる
ターゲットとゴールが設定できたら、記事の構成を組み立てていきましょう。
構成要素の決定
ターゲットのゴールに向けて、どんな情報をどのような順番で示せば、よりわかりやすく伝わるかを構成していきます。例えばこの記事に関して、必要だと思われる要素を書き出すとします。
- SEO記事とは何か
- Googleのアルゴリズムにはアップデートがある
- SEOで評価されやすい記事の説明
- 記事の書き方の説明
- SEOにはNG行為がある
上記のように書き出してから、本当にこれらの要素が必要なのか、また他に必要な要素があるのかどうか考えていきます。上から二つ目の「Googleのアルゴリズムにはアップデートがある」という要素は、関連性があるものの、それほど強くはないため外します。
また、突然SEO記事の書き方を説明するだけでなく、SEO記事とは何かを説明する方がユーザーにとって親切だと考えました。すると、下記のように構成要素を整理することができます。
- SEO記事とは
- SEOで評価されやすい記事の説明
- 記事の書き方の説明
- SEOにはNG行為がある
このように、不要な要素は入れないこと、ターゲットの潜在的なニーズにも応えることが、構成要素を決定する上で理想となります。
大見出しの決定
構成要素が決定したら、大見出しを決定していきましょう。大見出しとは、記事を構成する最も大きな見出しのことです。そして見出しには2つの重要な役割があります。
- ユーザーにこの記事で何が書かれているのかしっかり認識してもらう役割
- Googleのクローラーに機械的にページ内容を認識させる役割
1つ目はユーザー視点での役割です。SEO対策でよく触れられることが多いですが、大見出しはユーザーがページを読むうえでもトピックを理解するのに大いに役立ちます。
どんなにコンテンツ内容が充実していても、全体の流れが把握できないと、読んでいるユーザーにはストレスがかかってしまいます。そのため、読みやすい構成にするためにも、大見出しをはじめとした見出しを使用することは大切です。
そして二つ目の役割は、Googleのクローラーに機械的にページ内容を認識させることです。」Googleのクローラーは人間がコンテンツを読む容量ではなく、ページに記載されているソースを読み込み、コンテンツ内容を把握します。
そこでGoogleのクローラーに認識してもらうために、コンテンツはHTMLタグを使用します。各見出しに対応しているHTMLタグは以下のようになっています。
- h1……記事のテーマ
- h2……大見出し
- h3……中見出し
- h4……小見出し
このように、h1〜h4を親子構造に設定することが、SEOのルールとなっています。先ほど設定した構成要素をHTMLタグに当てはめると、下記のようになります。
構成要素
- SEO記事とは
- SEO記事で評価されやすい記事
- SEO記事で評価されやすい記事を作るには
HTMLタグの設定
<H2> SEO記事とは<H2>
<H2> SEO記事で評価されやすい記事<H2>
<H2> SEO記事で評価されやすい記事を作るには<H2>
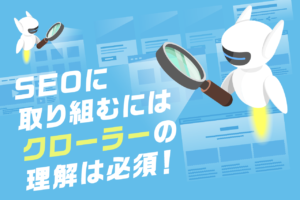 クローラーとは?検索エンジンにインデックスされる仕組みや巡回頻度を上げる方法解説
Webサイトを制作、公開しても検索結果に表示されないと検索エンジン経由の集客はできません。検索エンジンがWebサイトの情報を取得するために使用しているのがクローラーです。クローラーがサイトの情報をどのように取得しているのか、基本的なところから解説します。
クローラーとは?検索エンジンにインデックスされる仕組みや巡回頻度を上げる方法解説
Webサイトを制作、公開しても検索結果に表示されないと検索エンジン経由の集客はできません。検索エンジンがWebサイトの情報を取得するために使用しているのがクローラーです。クローラーがサイトの情報をどのように取得しているのか、基本的なところから解説します。
中見出し・小見出しの決定
大見出しが決まったら、その下の階層となる見出しを設定していきます。上部でも記載した通り、ユーザーおよびクローラが理解しやすい構成で設定することが、SEO記事を作成する上で大切になっていきます。例えば、大見出しにした「SEO記事で評価されやすい記事を作るには」について、いくつかの要素を解説するとします。すると、下記のような見出し構成になります。
- <H2> SEO記事で評価されやすい記事を作るには<H2>
- <H3> 上位表示させたいキーワード(SEO対策キーワード)を決める
- <H4>対策キーワードを選ぶコツ①<H4>
- <H4>対策キーワードを選ぶコツ②<H4>
- <H4>対策キーワードを選ぶコツ③<H4>
- <H3>ターゲットとゴールの設定<H3>
- <H3> 上位表示させたいキーワード(SEO対策キーワード)を決める
見出しを決定する際に注意することは、階層構造を崩さないことです。階層構造が崩れてしまうと、SEO評価もマイナスとなってしまいます。
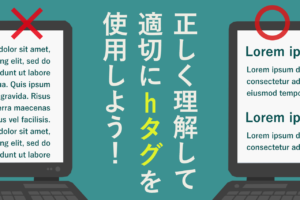 hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説
Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。
hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説
Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。
記事構成に迷ったら
構成要素を書き出したあと、どういった構成にすればいいかわからない、何を書けばいいのかわからないと迷うこともあるでしょう。記事の構成や内容に迷った時は、対策キーワードで検索してみるのがおすすめです。
検索結果を見てみることで、実際にどんな構成・内容のページがGoogleに評価されているのかを把握することができます。SEOで評価される記事を作成する上で、対策キーワードに対する検索結果をじっくり観察してみることも大事です。
タイトルと目次を設定する
大見出しと小見出しを作成したら、タイトルや目次を設定していきましょう。それぞれについて解説していきます。
記事タイトルの決定
記事構成が決定したら、記事タイトルを決めていきます。記事の上部に表示されるだけでなく、検索結果にも表示される要素です。そのため、記事タイトルはユーザーがそのコンテンツを読むかどうか始めに決定する要素となるので非常に重要です。
記事タイトルには、「<title>」タグを設定します。「<title>」タグを使用することで、Googleのクロームにタイトルであることを認知してもらえます。ただし、Googleが勝手に表示する場合もあるので、設定した文言が必ず表示されるわけではありません。
記事タイトルを決定する際のポイントは、ユーザーがクリックしたくなり、かつページ内容にそった文言にすることです。特に、対策キーワードを含めるとよりSEOで評価されやすくなる傾向にあります。検索結果でタイトルが全文表示された方が、内容が伝わりやすいです。そのため、タイトルの文字数は30文字前後が目安となります。
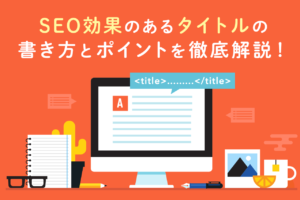 SEO効果のあるタイトルとは?具体例と書き方のポイントを解説
SEO効果の高いタイトルは、検索エンジンでの順位向上やクリック率の増加に直結します。この記事では、魅力的かつ効果的なタイトルを作成する方法や具体例、注意点について詳しく解説しています。
SEO効果のあるタイトルとは?具体例と書き方のポイントを解説
SEO効果の高いタイトルは、検索エンジンでの順位向上やクリック率の増加に直結します。この記事では、魅力的かつ効果的なタイトルを作成する方法や具体例、注意点について詳しく解説しています。
ディスクリプション(description)の設定
タイトルが決まったらディスクリプションを設定していきます。ディスクリプションとは、メタディスクリプション(meta description)とも呼ばれ、ページの説明や要約をした文章を指します。検索エンジンでタイトルの下部に表示されるので、ユーザーにどんな内容のページか伝えることが可能です。
ディスクリプションは、「<head>」タグで設定することができます。設定しなくても、検索エンジンが本文内から自動で抜粋し表示してくれますが、予期しない内容になってしまうことも。正しく記事の内容を提示するためにも設定しておくと良いでしょう。
 description(ディスクリプション)とは?書き方や確認方法を解説
メタディスクリプションは、検索結果に表示されるページの要約で、クリック率向上に寄与します。この記事では、メタディスクリプションの役割や最適な書き方、確認方法について詳しく解説しています。
description(ディスクリプション)とは?書き方や確認方法を解説
メタディスクリプションは、検索結果に表示されるページの要約で、クリック率向上に寄与します。この記事では、メタディスクリプションの役割や最適な書き方、確認方法について詳しく解説しています。
目次の作成
次に目次を設定していきます。記事内の目次には、2つのメリットがあります。
- コンテンツ全体を把握しやすくなる
- ページ内遷移ができる
1つ目のメリットは、コンテンツ全体を把握しやすくなることです。ページに来訪したユーザーはタイトルを読んで流入しています。そこで目次を提示することによって、本当に検索意図に沿ったコンテンツ内容であるかどうかを確認することができます。目次を読んで納得してもらうことによって、コンテンツへの信頼性が高まります。
そして2つ目のメリットが、ページ内遷移ができることです。目次に各見出しへのアンカーリンクを設置した場合に有効となります。目次にリンクを仕込むことにより、ユーザーが気になる部分にジャンプすることができます。ユーザーの知識量は人によって異なります。そのため、知っている内容を読み飛ばし、スムーズに問題解決することが可能となります。
本文の要素と役割を理解しておく
本文は各見出しの内容を説明する文章です。コンテンツの肝となる部分ですが、本文は以下の3つの要素から成り立っていることを知っておきましょう。
- トップコピー
- ボディーコピー
- ボトムコピー
それぞれについて解説していきます。
トップコピー
「トップコピー」とは、記事の冒頭部分に提示するテキストのことで、リード文と呼ばれることもあります。トップコピーの役割は、その記事に興味を持ってもらい、読者を惹きつけることです。トップコピーでワンクッション入れることで、その記事を読むための心構えができます。
そのため、トップコピーは魅力的な文章になるようにしましょう。特に、問題提起を行ったり、共感させるような内容にしているページが多い傾向にあります。
ボディーコピー
ボディーコピーは、導入後の目次から、まとめに入るまでの本文のことです。言い換えるなら、記事の肝となる部分にあたります。ボディーコピーを作成する際のポイントは、HTMLタグの階層構造を整理しながら、読みやすく伝わりやすい設計を意識することです。
読みやすい構成にすることは、ユーザーへの満足度を上げ、Googleのクローラーにも質の良いコンテンツとして認識してもらうことができます。ユーザーは分かりやすい文章構造を求めているので、周りくどい言い回しや冗長な文章を控え、結論ファーストの文章で仕上げることが大切です。
ボトムコピー
本文の最後には、ボトムコピーを置きます。ボトムコピーとは、記事のまとめ部分にあたります。ページ全体の内容が振り返れるようなまとめにすることで、長いコンテンツだった場合でも、ユーザーが何を読んだのか把握することができます。もしCTAボタンを設置したい場合は、ボトムコピーに設定するのを忘れないようにしましょう。
記事を執筆する
記事の構成について理解できましたら、実際に記事を書いてみましょう。記事の作成には大きく分けて以下のような2つの工程が発生します。
- ライティング
- 校正
ここからは各工程ごとに解説していきます。
ライティング
記事の大枠が決まってから最初に行うことはライティングです。ライティングでは以下3つのポイントを意識しましょう。
- 読みやすく柔らかい表現にする
- シンプルな文章を心掛ける
- 読み手にストレスのない文章を書く
1つ目のポイントは、読みやすく柔らかい表現にすることです。サイトのターゲット層にもよりますが、より多くの人に読んでもらうことを目的としたサイトであれば、難しい熟語や硬い表現を避けて、柔らかい表現を使用する方がユーザーにとって読みやすくなります。
2つ目のポイントは、シンプルな文章を心掛けることです。文章は無駄な部分をそぎ落とし、必要な部分を残した簡単な文章の方が、ユーザーにとって親切です。そしてシンプルな文章はユーザーに伝わりやすいというメリットがあります。
3つ目のポイントは、読み手にストレスのない文章を書くことです。ここでいうストレスとは、専門用語を解説しないでそのまま使用したり、難しい表現を使ったりすることを指します。どんなユーザーでも理解しやすい文章を目指すことで、ユーザーの離脱を防ぐことができます。
 Webライティングとは?書き方や副業の始め方、おすすめの本を解説
Webライティングは、ウェブ上で効果的に情報を伝えるための文章作成技術です。この記事では、Webライティングの基本的な書き方、副業としての始め方、おすすめの参考書籍について詳しく解説しています。
Webライティングとは?書き方や副業の始め方、おすすめの本を解説
Webライティングは、ウェブ上で効果的に情報を伝えるための文章作成技術です。この記事では、Webライティングの基本的な書き方、副業としての始め方、おすすめの参考書籍について詳しく解説しています。
校正
ライティングが完了したら、誤字や脱字が無いかを確認しましょう。誤字脱字が多い場合、ユーザーからの信頼を失うこともあるので、怠らないことが大切です。校正にはツールを使用することで、しっかりと文章の仕上がりを確認することができます。また、実際に読み直したり、黙読することで、より精度の高い校正が行えます。
SEO記事を作る際の注意点

ここからはSEO記事を作成する上での注意事項について説明していきます。無意識のうちにやっていたということにならないよう、気をつけましょう。
コピーコンテンツ
他のサイトの内容をそのままコピーしたようなコンテンツは評価されません。その理由は、同じ内容のページを検索結果にいくつも表示してもユーザーのためにならないからです。コピーコンテンツが多いと、ユーザーからもGoogleのクローラーからも信頼されません。
コピーコンテンツは避け、本当にユーザーにとって価値のあるコンテンツの提供を心掛けましょう。内容が似ていてもオリジナルの構成・文章でより分かりやすく説明していれば、コピーコンテンツにはなりません。作成したいページと似たものが既に他のサイトにあっても、オリジナルの構成・文章で作成すれば問題ないので、諦めずに手がけましょう。
 重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説
重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。
重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説
重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。
ドメイン内で全く同じTDHを設定している
また、ドメイン内で全く同じTDHを設定することも、NGとなります。TDHとは、title、description、h1のことを指しています。1つのドメイン内で同じTDHを使用するということは、全く同じコンテンツが2つあるというように認識されてしまいます。
常識的に考えれば、いずれもページの内容に沿って設定されていれば、同じになるはずはありません。クローラもユーザーも正しくページ内容を理解できるように、ドメイン内のTDHはそれぞれ異なった内容で設定しましょう。
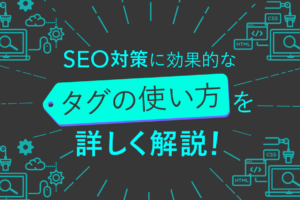 SEO対策に効果的なタグの使い方!title、description、hタグを解説
SEO対策におけるタグの適切な使用は、検索エンジンの評価やユーザーの利便性向上に直結します。titleタグ、descriptionタグ、hタグの役割や効果的な使い方について解説しています。
SEO対策に効果的なタグの使い方!title、description、hタグを解説
SEO対策におけるタグの適切な使用は、検索エンジンの評価やユーザーの利便性向上に直結します。titleタグ、descriptionタグ、hタグの役割や効果的な使い方について解説しています。
対策キーワードのつめこみ
対策キーワードをコンテンツ内に使用することはSEO評価につながりますが、詰め込めば詰め込むほどSEOで評価されやすいわけではありません。前述した通り、クローラーはユーザーにとって価値のあるページ内容が評価される仕組みとなっています。
かつてクローラが文章を理解できなかった時代は、キーワードが入っているほど評価される傾向にありました。しかし、クローラーのアップデートを重ねて、近年ではページの内容まで理解できるように進化しています。そのため、キーワードばかりで内容の薄いコンテンツは評価の対象にならないので注意が必要です。
無駄に長い文章構成
充実したコンテンツは高い評価につながりますが、文章が長ければ評価されるわけではないです。重要なのは、適切な文章量で必要な情報を提供できているかどうかです。
極端な例となりますが、たとえば「りんご 英語」というキーワードに対しては、「apple」という単語1つで、「りんごを英語で何と言うか」と言うユーザーの悩みは済むはずです。それなのに、すぐに答えを提示せず、周辺の話ばかり続けてしまったら、ユーザーはストレスを抱えて離脱してしまいます。
そのため、長い文章を書こうとするのではなく、ユーザーにとって読みやすい記事構成や文章になることを心がけることの方が重要です。
ユーザーに見せているものとクローラに見せているものが異なる
クローラーに対策キーワードを読み込んでもらうことは大切です。しかし、だからと言ってソースコード上に大量にキーワードを入れ込んだり、大量にリンクを設置するなどはSEO的にマイナス評価となります。ソースコード上ならユーザーには見えないですが、このような手法はコンテンツを評価する上でマイナスになるように設定されています。
また類似した手口となる、「隠しテキスト」もNGです。隠しテキストとはクローラ対策としてユーザーには見せないで、ページの背景色と同じ色の文字でテキストを書くと言う手法です。クローラーが認識した時点でマイナス評価となってしまいます。
このように、現在ではクローラをだますような行為はSEOではマイナス評価となってしまいます。近年のアップデートによって大きく下げられるので、やらないようにしましょう。
そのほかのSEO対策

基本的なSEO対策について解説していきました。ここからは、そのほかのSEO対策について解説していきます。最近のGoogleの評価指標はページ構成のほかに、UIUX観点で2つの重要な項目があります。
- モバイルフレンドリー
- ページの読み込み速度(ページスピード)
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
SEO対策1.モバイルフレンドリー
1つ目の項目は、モバイルフレンドリーです。モバイルフレンドリーとは、モバイル(スマートフォン)から快適にサイトを利用できることです。近年ではモバイルユーザーの増加に伴い、モバイルでのユーザビリティが重要になってきています。パソコンとモバイルでの画面サイズは異なるため、それぞれの特性にあった表示が必要です。
パソコンとスマートフォンの画面サイズに合わせて自動的に表示が切り替わるWebデザインのことを、「レスポンシブ」と言います。モバイルでの使いやすさに関しては、以下の4項目が評価ポイントとなります。
- フォントサイズが小さすぎないか
- ビューポートが設定されているか
- タップ要素同士が近すぎないか
- コンテンツサイズがビューポートに対応しているかどうか
自社サイトがモバイルフレンドリーであるかどうかは、Google公式ツールで状況を確認することができます。無料で利用できるツールなので、ぜひ一度使ってみてください。
 モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説
モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。
モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説
モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。
 レスポンシブデザインとは?今さら聞けない特徴やメリット・デメリットを解説
PCやスマホ、タブレットそれぞれのデバイスに最適なデザインでWebサイトを表示するレスポンシブデザインが今や当たり前になりました。レスポンシブデザインとは何か、何に注意して設計すべきかを基本的なところから解説します。
レスポンシブデザインとは?今さら聞けない特徴やメリット・デメリットを解説
PCやスマホ、タブレットそれぞれのデバイスに最適なデザインでWebサイトを表示するレスポンシブデザインが今や当たり前になりました。レスポンシブデザインとは何か、何に注意して設計すべきかを基本的なところから解説します。
SEO対策2.ページスピード
そして2つ目の項目は、ページの読み込み速度(ページスピード)です。モバイルユーザーの増加に伴い、移動中などでネット環境が良くない、すぐに情報が欲しい、といったニーズが存在しています。こうしたユーザーに向けて、すぐにページを表示できるかどうかも重要視されています。具体的な評価項目については、以下の5つとなっています。
- 重要度5:First Contentful Paint
ユーザーがメインとなるコンテンツが表示されたと判断するまでの時間
- 重要度4:速度インデックス
ページのコンテンツが見えるまでの時間
- 重要度3:インタラクティブになるまでの時間
コンテンツまたは、画像が初めて表示されるまでの時間
- 重要度2:CPUの初回アイドル
ユーザーがページの操作が可能になるまでの時間
- 重要度1:First Meaningful Paint
ユーザーが操作してから反応するまでの時間
自社サイトの読み込み時間の改善をする場合は、Google公式ツールでページの対応状況を確認することができます。無料で使用できるので、ぜひ活用してみてください。
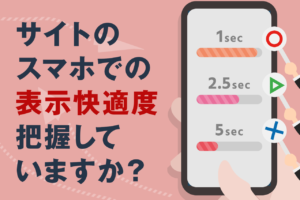 ページスピードインサイト(Google PageSpeed Insights)の使い方!見方や改善方法を解説
Google PageSpeed Insightsは、ページ速度を診断し、改善提案を提示する無料ツールです。この記事では、使い方や結果の見方、速度向上の方法を詳しく解説しています。
ページスピードインサイト(Google PageSpeed Insights)の使い方!見方や改善方法を解説
Google PageSpeed Insightsは、ページ速度を診断し、改善提案を提示する無料ツールです。この記事では、使い方や結果の見方、速度向上の方法を詳しく解説しています。
SEO記事の知識を身につけて効果的な記事を作成しましょう

この記事では、SEO記事の組み立て方やポイントを詳しく解説していきました。SEO記事において重要なのは「ユーザーのニーズ応えるページ」でした。ターゲットとゴールを設定し、作成するコンテンツがブレてしまうのを防ぎましょう。
そして、ページの使いやすさ(読みやすさ、わかりやすさ、つかいやすさ)も意識することも大切です。使いやすいページはユーザーの満足度を高めるだけでなく、Googleのクローラーに良質なコンテンツとして認識してもらうことができます。結果的に、そのコンテンツは上位表示されることにつながります。
SEO対策は簡単ではありませんが、努力と意識によってユーザーにとって価値あるページを目指していくことが可能となります。SEO対策でお困りの場合は、WEBサイト作成のプロであるニュートラルワークスがお手伝いできます。ぜひお気軽にご相談ください。
<無料>資料ダウンロード
AI記事作成代行サービス
SEOのプロがAIを活用した記事を制作!(1万円/1記事)