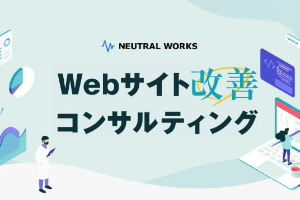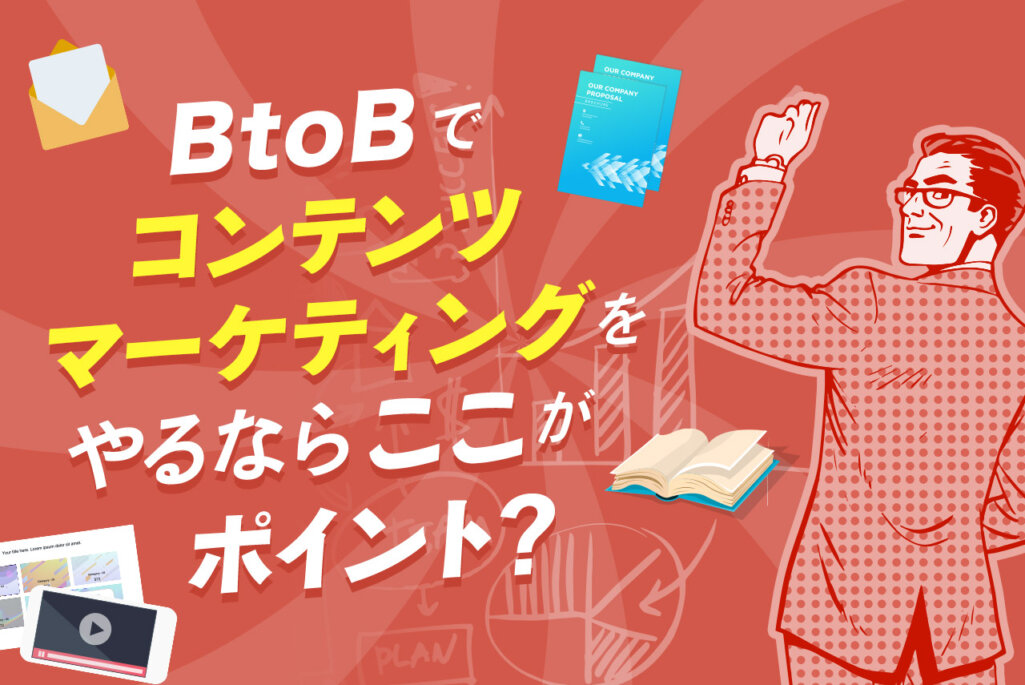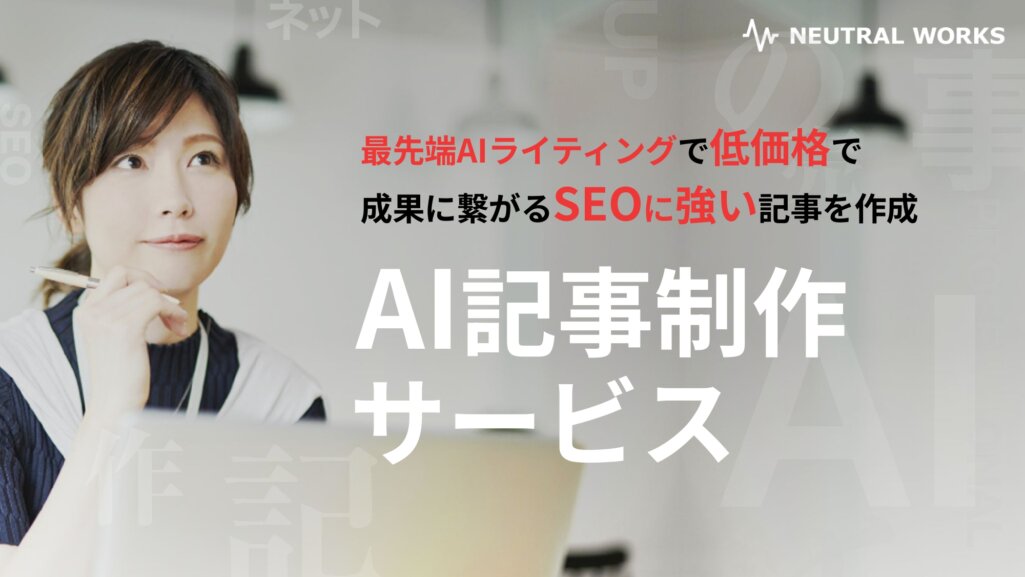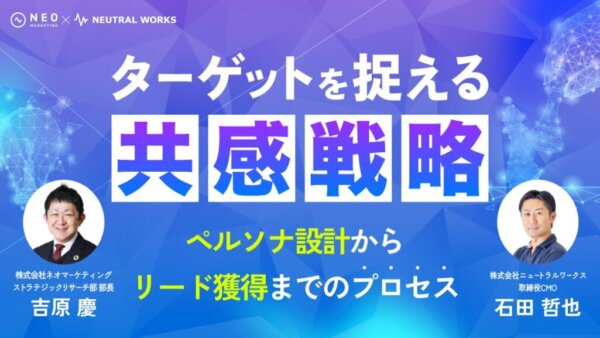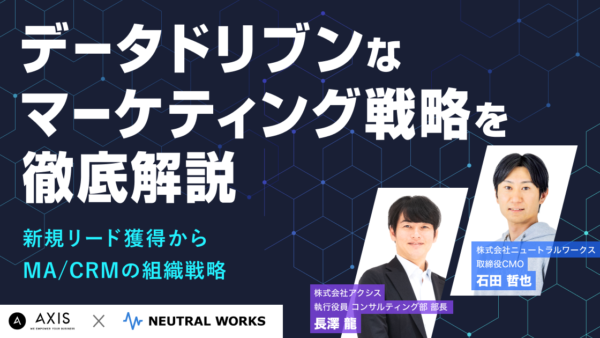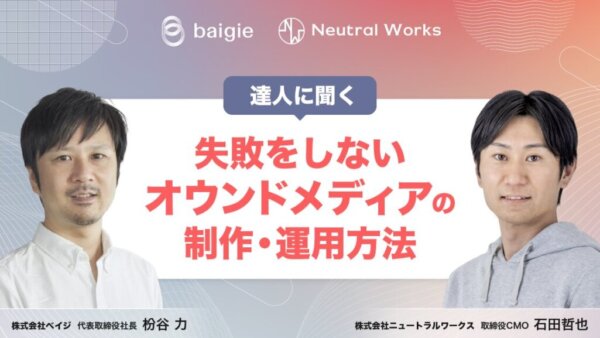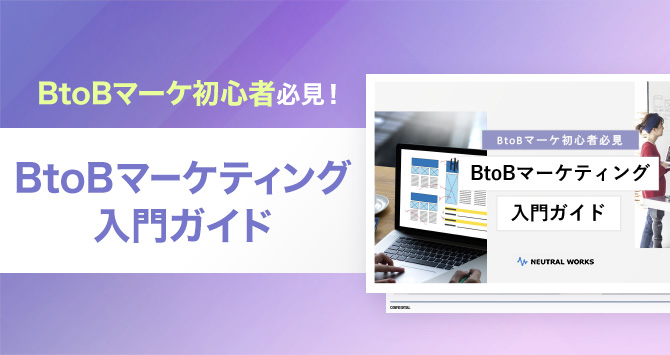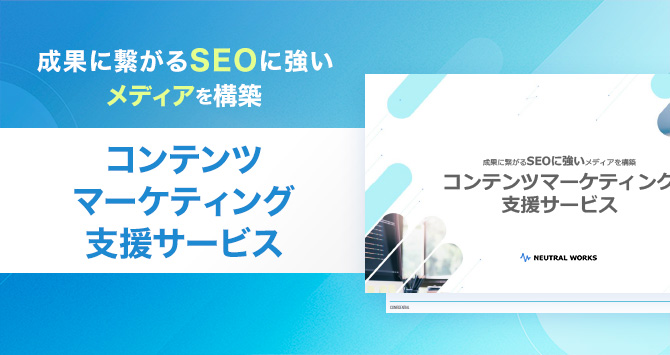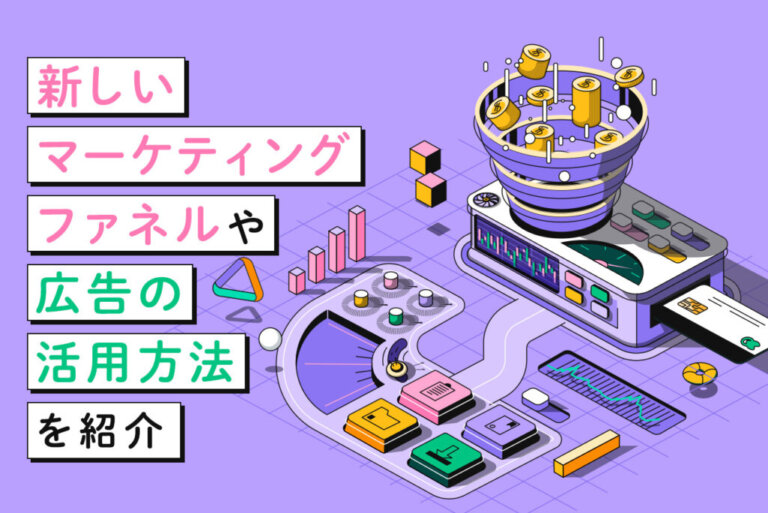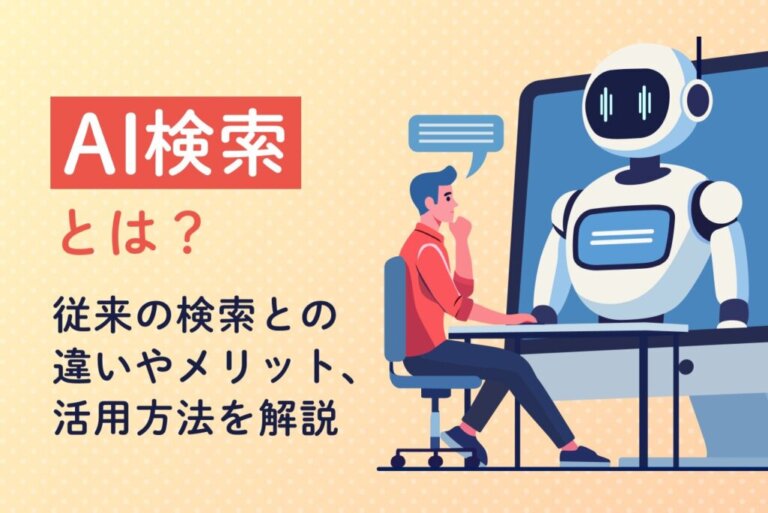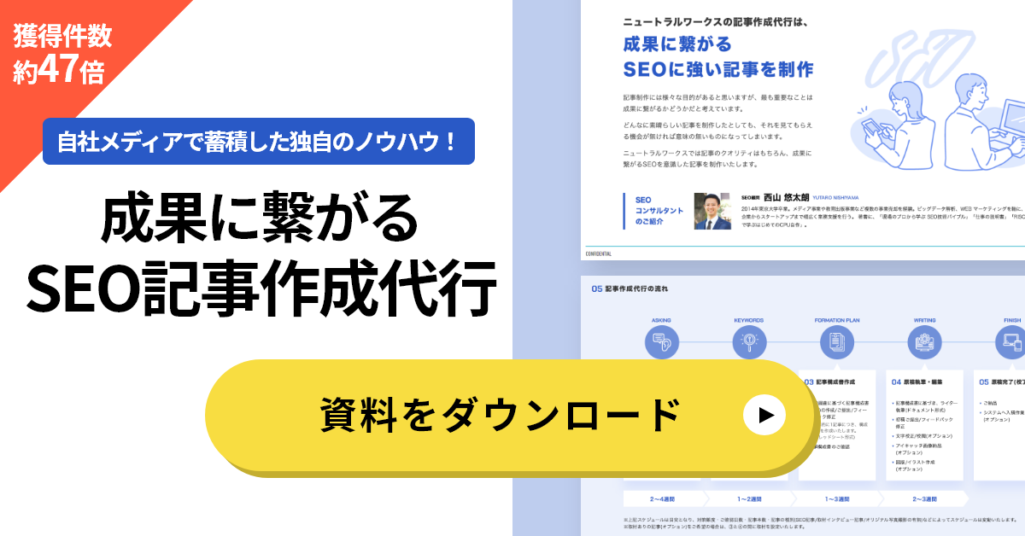コンテンツマーケティングを行う際は、「SEO」に注目が集まりがちですが、実はSNSもコンテンツマーケティングに有効な手法の一つです。SNSは、検索エンジンでの顧客獲得が難しいケースや、差別化をしにくい商材を扱う際に、ファンの獲得やブランド認知を高める効果を持っています。
この記事では、 SNSをコンテンツマーケティングで活用する際のメリット・デメリット、媒体ごとに異なるポイントを詳しく解説します。
導入の流れや注意点、媒体別の事例もまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
サイトの成果改善でお困りではないですか?
「サイトからの問い合わせを増やしたいが、どこを改善すべきか分からない…」そんなお悩みをお抱えの方、ニュートラルワークスにご相談ください。
弊社のサイト改善コンサルティングでは、サイトのどこに課題があるかを実績豊富なプロが診断し、ビジネスに直結する改善策をご提案します。
目次
- コンテンツマーケティングとSNSの関係性
- SNSを活用してコンテンツマーケティングを行うメリット
- コンテンツマーケティングでSNSを活用する方法
- 【Facebook】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- 【Instagram】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- 【Twitter】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- 【LINE】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- 【YouTube】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- 【TikTok】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- 【Pinterest】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- 【Wantedly】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
- SNSを活用したコンテンツマーケティングでの注意点
- コンテンツマーケティングにSNSを導入する流れ
- コンテンツマーケティングにおけるSNS活用のまとめ
コンテンツマーケティングとSNSの関係性

まずは、コンテンツマーケティングとSNSの関係性を把握しておきましょう。関係性を把握することで、コンテンツマーケティングにおけるSNSの重要さを理解できます。
そもそもコンテンツマーケティングとは
コンテンツマーケティングとは、企業のWebサイトに掲載しているブログやコラムなどを活用して、商品やサービスの売上向上を目指すマーケティング手法を指します。不特定多数のユーザーに向けて情報を発信することで、新規顧客やファンを獲得することが目的です。
コンテンツマーケティングにおいてSNSの拡散性は効果的
コンテンツを拡散するには、SNSの活用が効果的です。ブログなどによるコンテンツは、検索結果の上位に位置していない限り、閲覧されにくい傾向があります。さらに、SEOの施策はすぐに効果が現れないため、コンテンツが拡散され認知されるまでに時間がかかります。
一方、SNSは拡散力が非常に高いです。
検索語句がない場合はSNSが有用
「検索だけでは、対策キーワードが上位に上がらない」といったケースにおいては、SNSの活用が役立ちます。特に、一般消費財や日用品などは差別化しにくいことから、SNSの活用が有用です。
実際に企業で使われた例として、ロート製薬と花王のケースを紹介します。
事例1.ロート製薬
ロート製薬では、tiktokを活用して10代と20代向けに、スキンケアやリップ商品を音楽に合わせて紹介する宣伝を行いました。Twitterでは、季節のイベントなどに合わせて投稿したり、Facebookではしっかりとした文体で内容を書き込むなど、SNSの年代や人口に合わせて使い分けが行われています。
事例2.花王
花王は、Instagramを使って洗剤のアタックに関するユーザー生成コンテンツを募集する手法を取りました。ユーザーが投稿した写真をエピソードを交えて紹介するといった方法で、ユーザーとのコミュニケーションを生かした宣伝です。
グローススピードが必要な場合もSNSが役に立つ
SEOを活用してマーケティングを行っていく場合、検索エンジンに評価されるまで、一定の時間が必要です。つまり、改善時のインパクトは大きなものとなりますが、反映されるまでに時間がかかってしまうことから長期的な運用が必要なのです。
しかし、SNSはユーザーによる拡散やバズが存在することから、グローススピードが速い傾向にあります。その代わり、多くのユーザーに興味を持ってもらえるような投稿でなければなりません。バズやユーザーの拡散を引き起こすためには、競合他社との差別化や魅力ある宣伝を行う必要があります。
グローススピードの速さを活用するためにも、ユーザーニーズを意識した情報発信を意識していきましょう。
<無料>資料ダウンロード
【サイト運営者必見】お客様成功事例集
集客と売上がアップした成功実績が見られる!
SNSを活用してコンテンツマーケティングを行うメリット

SNSをコンテンツマーケティングとして採用するメリットを、大きく5つに分けて解説します。SNSを実際に活用して行く前に、まずはどのような長所があるのか把握しておきましょう。
1.施策実行のコストが低い
SNSは、誰もが気軽に情報発信できることから、広告コストをかけずにコンテンツを広められます。
- コンテンツを内製化できれば低コストではじめられる
- 新規顧客を獲得するための広告コストが小さい
- 成果を出せれば売上につながるため、スモールスタートができる
低コストで情報発信できるため、少しでも成果を出せれば、スモールスタートであっても一定の成果を上げられます。
2.ロイヤルティの獲得が可能
SNSは、多くの人にコンテンツを見てもらえる可能性を秘めています。そのため、ユーザーが満足する質の高いコンテンツを提供できれば、 顧客ニーズを満たすと同時に情報共有を行うことが可能です。
- 質の高いコンテンツを用意できれば、多くのニーズを満たせる
- 同じようなニーズを持っている人同士でつながりやすい特徴を持っているため、質の高いコンテンツは口コミで広がりやすくなる
- 拡散されると「あの会社の SNS を見よう」と意識してもらえる可能性が高まる
SNSは、気軽に誰でも閲覧できることから、ファンに向けた情報発信のツールとしても役立ちます。
3.ブランド認知の獲得
SNSは、ただ単に情報を発信するだけでなく、顧客の反応を確かめる方法としても使いやすいです。
- 情報収集を行う段階から顧客にアプローチでき
- コンテンツを作れば、不特定多数の人に見てもらえる
- 同じ悩みに対して口コミでコンテンツが広がる
同じ悩みを持っているユーザーの口コミも期待できることから、より幅広く顧客を獲得できるようになるでしょう。
4.即効性が高い
SNSは、拡散を活用することで、サイト改善を行うクロススピードが早められます。
- SNSのバズや拡散を通じてグローススピードを早められる
- SEOでは届かないユーザにも拡散を通じてコンテンツを届けられる
また、拡散されれば多くの人の目に触れるため、普段では届かないようなユーザーにもコンテンツを届けられる強みを持っています。情報を提供した後の顧客の反応の速さは、他の宣伝方法にはない大きなメリットとなるでしょう。
5.採用コストが下がる
SNSの活用は、サービスや商品の宣伝などだけでなく、 採用コストを下げる手段としても使われています。
- SNSを通じて会社の様子や働き方などが事前にイメージしやすくなる
- 給与や待遇などの採用基準とは別に、会社への興味を持ってもらいやすい
- 採用サイトなどに比べ、働いている人のイメージがわきやすくなる
SNAは、会社のイメージを伝えるツールとしても、多くの企業に活用されています。
コンテンツマーケティングでSNSを活用する方法
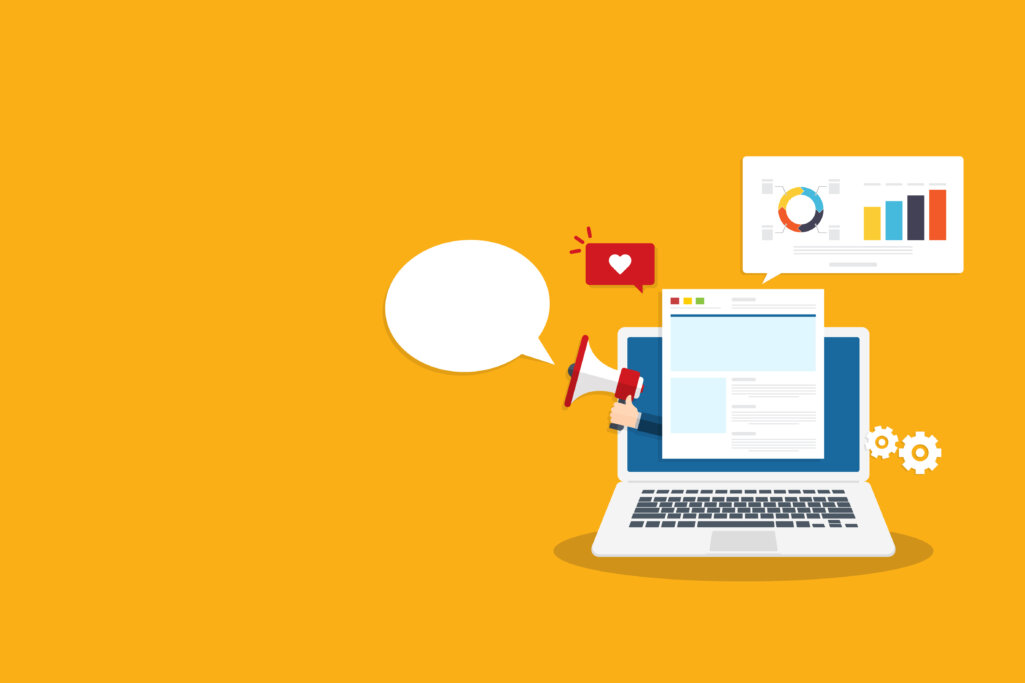
続いて、コンテンツマーケティングにおける、SNSの活用方法を見ていきましょ。
コンテンツ内にSNSシェアボタンを用意して拡散させる
もっとも簡単な方法は、コンテンツ内に、SNSのシェア・いいね・ツイートなどのボタンを設置することです。コンテンツを見たユーザーが、良い情報だと判断してくれれば、いいね・リツイートボタンを押してもらえるなど、さらなるコンテンツの拡散が期待できます。
自社のSNSアカウントでコンテンツを拡散する
SNSで配信するコンテンツは、自社サイトのコンテンツと同様に、有益な情報を提供する必要があります。利用するSNSによって、ユーザー層や利用用途が異なるため、それぞれのSNSに合った方法で配信しましょう。
SNS広告を使って拡散する
SNS広告を出稿し、コンテンツを拡散する方法も効果的です。費用はかかりますが、コンテンツの配信と広告の両方を行うことで、相乗効果の発揮が期待できます。
SNS広告は、ユーザーの登録情報をもとに、精度の高いターゲティングが行うことが可能です。商品・サービスへの興味を持つユーザーへの広告配信が可能となるため、広告が受け入れてもらいやすいという特徴があります。
【Facebook】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
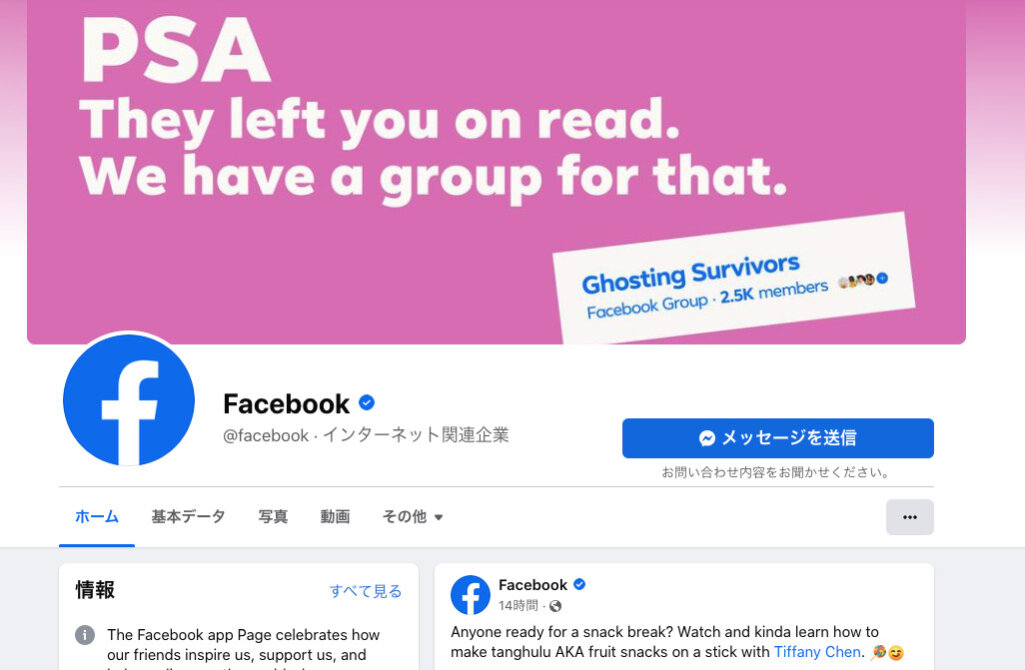
https://www.facebook.com/facebook/
Facebookは、個人アカウントとは別に複数のページ作成もできるため、メディアやサービス、あるいは商品などの名前でページを作成し、それぞれに特化した情報を届けることが可能です。
さらに、Googleなどの検索エンジンの検索結果にもページが表示されることもあるため、 SNSの内部と外部で、両方からのアクセスをえられる点も魅力となるでしょう。
メリット・デメリット
Facebookは、商品を気に入ったユーザーがいれば、より需要のある情報提供が行えるようになります。
- ファンの獲得や認知の向上につながる
- 情報に信頼を持ってもらいやすくなる
- 改善点や問題点を把握することに役立つ
また、サービスや商品を使った人からのコメントをもらえるため、ファンの反応に合わせて良いところを伸ばしたり悪いところを改善したりすることにも役立つでしょう。興味のある情報であればより多くの人に口コミで広めてもらえる可能性も高まることから、情報の提供にも信頼を持ってもらいやすくなります。
反対に、デメリットはカスタマイズ性の低さと、コンテンツを提供し続ける継続性が必要になる点です。Facebookは、Webサイトを作成する時のように、自由にカスタマイズしてページを作成することができません。そのため、競合との差別化が図りにくいところがデメリットとなります。
また、ファンとの交流を続けるためにも、良質な情報の提供を続けていくことが必要となるため、定期的に情報提供を続けていくことが必要になる点は考慮していきましょう。
活用事例1.Facebookショップ
Facebookでは、無料でオンラインショップが開けられる「Facebookショップ」が利用できるため、商品を追加して自社の製品をアピールすることが可能です。
活用事例2.Facebook 広告
Facebookでは、年齢や性別、地域別のターゲットに合わせた広告を出稿できることから、タイムラインなどにFacebook広告を織り交ぜるなどの工夫ができます。他にもmライブ配信ができるFacebookライブや、ユーザーの問い合わせに自動でコンピューターが答えるメッセンジャーボードなど、ファンとの交流を効率的にする方法としても使われています。
【Instagram】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
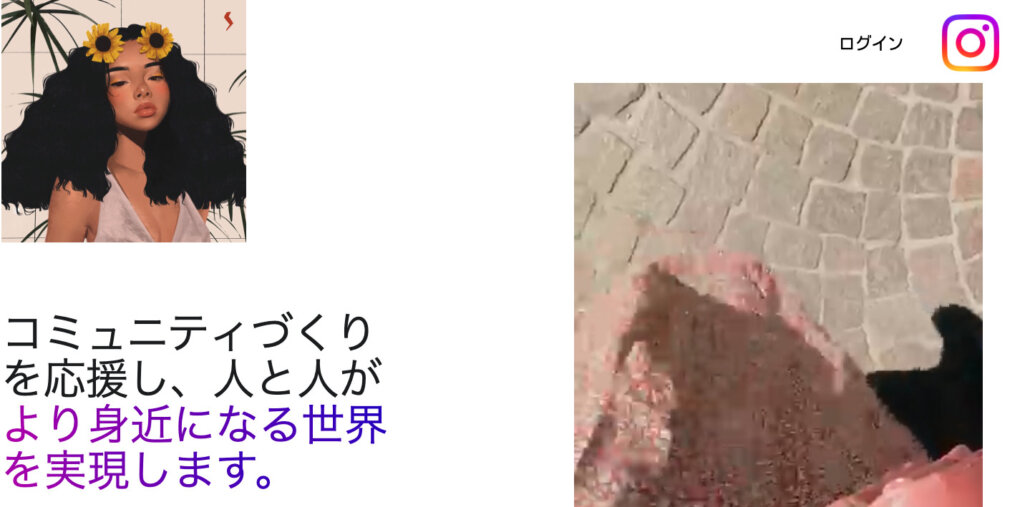
https://about.instagram.com/ja-jp/
Instagramは、動画や写真を投稿して、不特定多数の人と共有できるSNS型のアプリです。ライブ配信やコメントなどの機能を使って、さまざまな人とコミュニケーションを取れることから、マーケティング手段としても有効的な手段となるでしょう。
メリット・デメリット
Instagramのメリットは、ハッシュタグ検索でユーザーが自分の知りたい情報を手軽にキャッチできる点です。また、文章だけでなく画像や動画などの情報を扱うことができることから、ユーザーにより興味を持ってもらいやすいといった特徴も持っています。
さらに、集客率の高いハッシュタグを利用することで、多くの人々のアクセスを得ようと工夫している企業も少なくありません。
デメリットは、ボリュームのあるコンテンツの発信に向いておらず、拡散性がさほど高くない点です。ブランド力のある企業であれば、多くの興味関心を集めることはできますが、あまり知られていないようなケースでは、より魅力のある画像や動画をアップしなければなりません。
多くの企業がビジネスアカウントを活用していることから、より魅力的で差別化が図れる投稿が求められます。
活用事例1.マスメディアとの併用
企業の中には、テレビやラジオなどのマスメディアと併用して、サイト運営ではアプローチしづらい顧客の獲得を目的として使われるケースがあります。1日で投稿できるStories広告を活用したり、動画で重点的に宣伝を行ったりするなど、各企業が創意工夫しています。
活用事例2.フォロワー数の多いインフルエンサーを活用
フォロワー数の多いインフルエンサーに依頼することで、年齢層や性別などにピンポイントで宣伝を行う方法としてもInstagramは使われています。
【Twitter】コンテンツマーケティングの手法と活用事例

Twitterは、1回につき140文字までの投稿という制限があるものの、リツイートしてもらうことができれば、より多くのユーザーに拡散してもらえます。好みのユーザーがいれば、フォローして動向を追いかけることもできるため、顧客に素早く情報を届ける手段として多用されています。
知らないユーザーとも繋がれる特徴を生かして、ユーザーニーズに応えられる投稿を続けていくことが大切です。
メリット・デメリット
Twitterのメリットは、タイムリーにユーザーとの情報交換ができる点です。緊急性のある情報を発信したり、ユーザーの問い合わせに素早く対応したりできるため、効率的にユーザーとのコミュニケーションがとれるようになります。
他にもアンケート機能を使って、製品開発やサービスに取り入れる工夫や、人気を集めるツイートができれば、上位表示されるトレンドを活用することもできるようになるでしょう。
デメリットは、ユーザーのリテラシーに左右されてしまうところにあります。拡散性が高いということは、ユーザーに悪い印象を持たれてしまうとすぐに炎上してしまう危険性を併せ持っています。
何も考えずに投稿をしてしまうと、伝えようと思っていたメッセージが全く違う内容に捉えられるということも少なくありません。Twitterに投稿する際は、計画的にファンを獲得していく運用プランや、タイミングが重要です。
活用事例.企業アカウントを作ってTwitter広告を活用する
Twitterの企業アカウントを作成することで、 ユーザーとのコミュニケーションを図り、プロモーションやブランディングを行っていく方法です。広告をクリックさせるCTAが充実していることから、Twitter広告の活用もされています。
Instagramと同じようにインフルエンサーを活用した事例もあるため、より多くの人に拡散するツールとして多くの企業がさまざまな宣伝を行っています。
【LINE】コンテンツマーケティングの手法と活用事例

LINEは、マーケティング活用が盛んに行われており、メールに代わる宣伝方法として多くの企業が利用しています。LINE公式アカウントの友達数を、どれだけ増やし続けていくことができるかが、大きく影響していきます。
メリット・デメリット
LINEのメリットは、登録しているユーザーにスピーディーに情報を届けられると同時に、プッシュ通知で内容を確認してもらいやすいという点です。通知が来たらタップするだけで内容を確認できるため、面倒を嫌うユーザーにもアピールしやすくなります。
また、ショップカード機能を使えば店舗や会社と連動したサービスが提供できることから、ポイントの発行や特典を付けるなど、集客の確実性を高められるようになるでしょう。
デメリットは、顧客の住所や名前などの情報が得にくいことと、不要な情報はブロックされやすいといった点です。登録情報がプロフィール画像やUIDのみとなるため、情報集めにはあまり適していません。
なお、プッシュ通知で情報もすぐに確認できることから、必要がないと思われた情報はすぐにブロックされてしまいます。
活用事例1.ユーザーとのコミュニケーションツール
クーポンやショップカードなどを発行できるLINEは、個人チャットなどを活用して顧客とのコミュニケーションツールとしても活用されています。例えば、商品を宣伝して、セールやクーポン券の情報をユーザーに届けることで、店舗へ誘導することも狙えます。
活用事例2.LINE広告の活用
LINEは、最低単価1円から自社に合わせた広告宣伝が行えます。 LINEはもちろんのこと、 LINEのファミリーのアプリを開いたユーザーにも広告が表示されることから、多くのユーザーに広告を見てもらいやすくなるでしょう。広告を載せれば、LINE アプリ以外のサイトやアプリにつなげることも可能です。
【YouTube】コンテンツマーケティングの手法と活用事例

YouTubeは、世界中のユーザーが利用していることから、そのユーザー数の多さを活用して、企業自体の認知を高めることに役立ちます。誰もが知っているYouTubeだからこそ、企業の情報提供をうまく絡めていくことができれば、より多くのファンを発掘することもできるようになるでしょう。
メリット・デメリット
YouTubeのメリットは、ユーザー数の多さと動画広告の豊富さにあります。世代や属性を問うことなく多くのユーザーが動画を視聴しているYouTubeだからこそ、動画広告への展開は大きなビジネスチャンスであることは間違いありません。
自社で動画を撮影するのも一つの手法ですが、YouTube広告を使って動画の合間などに宣伝をすることも可能なため、動画の尺に合わせて宣伝の仕方を変えられます。
デメリットは、ユーザーがCVに到達するまでの時間が長いことです。YouTubeはただ動画をあげるだけでは興味を持ってもらうことはできません。コンテンツのテーマやユーザーの興味を引く編集など、ユーザーからの人気を集める手段に関しての知識が必要になります。動画を制作する時間なども考えなければならないため、継続的に動画を出し続ける大変さも併せ持っています。
活用事例.ブランディング動画でイメージアップ
視覚や音で情報を伝えられる動画の投稿ができるYouTubeは、顧客からの信頼度を高めるブランディング動画に適しています。ユーザーが動画を見て誤解してしまわないためにも、何を目的としてアプローチをしていくのか計画的に考えていくことも大切です。
CV率を高めるHOWTO動画
サービスや商品を実際にどのようにして使うのか紹介できるHOWTO動画は、見込み客に対しても視覚的にわかりやすく説明が行います。どのような使い勝手か分かれば、ユーザーも具体的なイメージができるようになり、CV率を高める効果も期待できます。
認知を広めるサービス紹介動画
サービス紹介動画は、自社がどのようなサービスを提供しているのか全く知らないというような顧客の興味を引くことに役立ちます。どのようなニーズを満たすことができるのか理解できる動画が作成できれば、ユーザーからの認知を得ることもできるでしょう。
【TikTok】コンテンツマーケティングの手法と活用事例
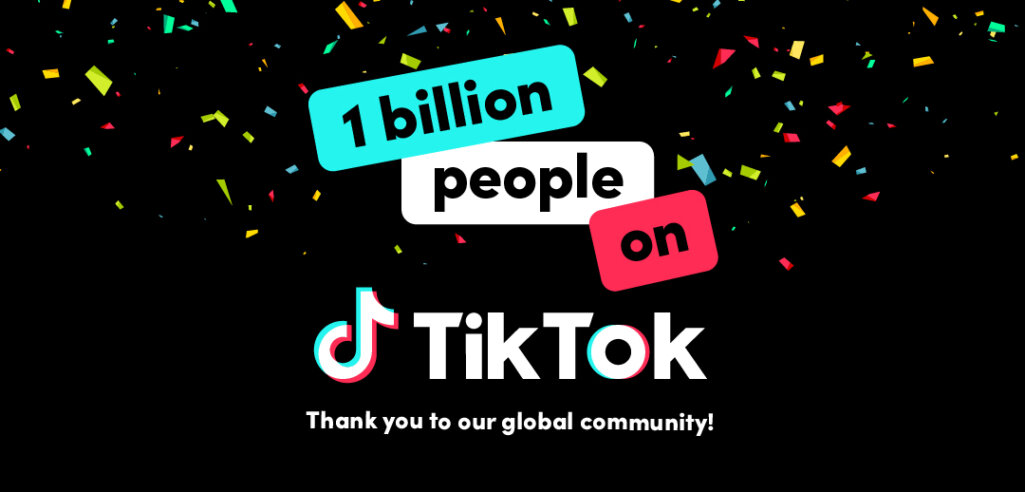
Tiktokは、ショートムービー動画プラットフォームとして、注目を集めているSNSです。Tiktok は10代を中心として人気のあるアプリとなっていますが、近年ではマーケティングの手法としても活用され始めています。
メリット・デメリット
tiktokをマーケティングに活用するメリットは、10代から20代に狙いを定めたマーケティングに効果的なところです。若者に人気の特徴をうまく活用すれば、他企業との差別化を図ったアピールを行えるようになります。
しかし、コンテンツマーケティングとして利用している企業は、YouTubeやFacebookなどに比べると あまり多くありません。30歳未満のユーザーが多くなるtiktokでは、若者が興味を持ちやすいファッションや音楽業界などのジャンルに偏りがちです。
そのため、自社の製品がtiktokに向いているのかどうか慎重に判断しなければなりません。また、広告性の高い動画は好まれない傾向にあるため注意が必要です。
活用事例.印象的な動画を投稿する
tiktokの活用事例では、話題性の高いダンス動画を活用したり、15秒という短い時間で印象的な動画を作成する手法が使われています。長すぎる広告は最後まで見てもらえないリスクが高いことから、短い動画に情報を集約して、「面白い!」「続きが見てみたい!」と思わせる工夫がなされています。
【Pinterest】コンテンツマーケティングの手法と活用事例

Pinterestは、好きな画像や写真を、専用のコルクボードにピン留めしてシェアが行えるサービスです。ボードはジャンルごとに分けられることから、製品情報や会社の様子などをフォルダ分けするように投稿が行えます。
インターネット上に画像をピン留めして情報を共有することが目的となるため、ブランドを周囲に認知してもらうための方法として活用されています。また、Pinterestは投稿した画像などに外部リンクを貼り付けることもできるため、画像から販売サイトや、公式サイトまで誘導する手段としても役立ちます。
メリット・デメリット
Pinterestのメリットは、Web上での認知度を高めると同時にアクセス誘導が行えることにあります。ユーザーが興味を引くような画像にURLを貼り付けることができるため、見てほしいページにユーザーを動かすアクセス誘導に効果的です。また、WebサイトのリンクはSEO効果もあるため、SEOを意識したマーケティングが行える点も強みとなるでしょう。
デメリットは、画像の良し悪しでマーケティングに大きく影響してくることです。文章などで興味を引くことができないPinterestは、いかに画像で興味を引くかが重要となってくるため、どんなにいい情報を扱っていても画像に興味を持ってもらわなければ意味がありません。
上位に表示される人気の画像などを参考に、まずは魅力的な画像とはどんなものなのか理解することから始めましょう。
活用事例.ブランドイメージを伝える
実際にどのような商品なのか紹介すると同時に、自社はどのようなものを扱っているのかといったブランドイメージを画像で宣伝している企業もあります。オーガニック系を扱う企業としてアピールをして興味関心を持ってもらうなどの工夫が行えます。
活用事例.デモンストレーションで商品の魅力を伝える
自社製品を使った結果などを画像として掲載して、実際にどのようなことができるのか画像で紹介している業者も多くあります。例えばカラーペンなどのアピールを行うときは、カラフルな絵を書いたり、芸術性に溢れる本格的な絵を書いたりと、商品力を見てもらうことが可能です。
【Wantedly】コンテンツマーケティングの手法と活用事例

Wantedlyは、無料で情報を提供できることから、うまく活用すればコストをかけずにマッチングができるようになるでしょう。給与条件は記載できませんが、理念や考え方を発信し、競合他社との差別化を図ることが目的とされています。自社だからこそ得られるやりがいや、社会貢献など、本質的な部分でユーザーからの信頼を得ることで採用につながります。
メリット・デメリット
Wantedlyのメリットは、社員の協力を得た採用活動が行えることと、多くの人に興味を持ってもらえることです。採用活動は一般的に企業が行うものですが、Wantedlyは社員を協力メンバーとして採用活動を行います。メンバーとなった社員は、友達に募集記事を届けられるようにしたり、シェアを依頼する通知がいくなどといったつながりが広がっていく形の募集が行えます。
また、採用を求めるユーザーは、興味があるから応募してみるといった選び方ができることから、会社に興味を持った人材を集めやすいといえるでしょう。
デメリットは、魅力を伝えられる実力が必要になる点です。いくら社員の協力をもらって働きかけを行っても、相手に魅力的だと思ってもらえなければ採用にはつながりません。情報を掲載する際もそうですが、実際に募集をしてきた人材にどれだけ魅力のある会社なのか伝えられるかが鍵となるでしょう。
活用事例.印象に残る募集要項を作る
Wantedlyを使っている多くの会社は、自社のイメージをより強く印象付けられるような募集要項にあるように工夫をしています。例えば、技術力を重視した採用で、自由記述ができる募集をかけたことで、人材のミスマッチングを防ぐことができたケースもあります。
また、社内の社員を活用して情報の拡散を行ったことで人材を獲得できたなどの報告が上がっています。Wantedlyは他の採用媒体よりも自由の利く募集が行えることから、さまざまな企業からの注目も集まってきています。
SNSを活用したコンテンツマーケティングでの注意点

ここでは、SNSを活用してコンテンツマーケティングを行う際の注意点をまとめます。それぞれのリスクやポイントを把握して、効果的なコンテンツマーケティングを目指していきましょう。
1.炎上リスクがある
不特定多数の人に情報を提供するSNSは、炎上リスクの高い方法でもあります。ブログやWebサイトなどに比べると、扱える情報量が少なくなってしまうことから、ユーザーの誤解が生じやすくなります。そのため、思わぬコンテンツが炎上してしまうことがあるのです。
また、コンテンツが広がるスピードも速いことから、コントロールできずに炎上になってしまうというケースも少なくありません。
SNSの炎上リスクを下げるためには、人の反感を生みやすいセンシティブな情報には触れない、不確かな情報を上げないなどの、運営管理をしておくことが必要です。SNSを活用する前に、運用ガイドラインを作るようにしておきましょう。
2.計測する数値を決める
SNSを活用してコンテンツマーケティングを行うのであれば、何を目的として宣伝を行うのか計測する数値を決めておくことをおすすめします。
例えば、ファンの育成を目指すのであれば、
- エンゲージメント率
- 口コミ率
ブランド認知獲得を重視するなら、
- リーチ数
- インプレッション数
- 投稿数
などが重要となってきます。
つまり、目的に合った数値を計測することが、目標を達成するためには必要不可欠なのです。具体的な数値を把握することができれば、商品やサービスのアップグレードを行うことにも役立ちます。どれだけの反応があったかなど、実用的なデータ収集は必ず行いましょう。
コンテンツマーケティングにSNSを導入する流れ

ここからは、コンテンツマーケティングにSNSを導入する際の流れを解説します。
コンテンツマーケティングは、
- 顧客維持
- ロイヤルティ醸成・成約
- ブランド認知
- 販売
- 口コミ評価
- リード獲得
- リード育成
- アップセルクロスセル
など、それぞれの目的に応じたコンテンツマーケティングの施策を取っていかなければなりません。
例えば、顧客維持を目的としたコンテンツマーケティングを行うのであれば、競合他社との差別化はもちろん、自社製品にしかないメリットを提供し続ける必要性が出てきます。現在は差があっても、いつか追い抜かれる可能性も想定しなければなりません。
他にも、販売目的なのであれば、他社製品との違いをアピールして商品を求めている人に適切な情報を届けたり、ブランド認知度を高めるためにSNSでアピールしたり、その都度適切な対応をしていきましょう。
SNSを使ってユーザーの反応を見ながら、どのような伝え方をすれば正しく理解してもらえるのか、どのような部分に問題があるのか検証し改善していくことを繰り返していけば、顧客維持もできるようになるでしょう。
まずは、何を目的にコンテンツマーケティングを行っていくのか決めて、それを持続していくためにはどのよう施策が必要になるのか組み立てていくことから始めてください。目的に合わない方法を取ってしまっては本末転倒なので、計画的なマーケティングが求められます。
1.顧客分析
コンテンツマーケティングの目的が決まったら、次はどんな相手に情報を届けるのかペルソナを決めていきます。
ペルソナとは顧客像のことを指し、
- 氏名・性別
- 年齢
- 職業・役職
- 年収
- 特技・趣味
- 居住地
- 家族構成・生い立ち
- 価値観
- ライフスタイルや休日の過ごし方
など細かい部分まで設定して、そのペルソナに適した投稿を行っていくことを目的とします。人物像の設定をより具体的にしていくことで、顧客がどのようなことを考えて行動を起こしているのかイメージを持ちやすくなるでしょう。効果的なマーケティングを行うためには、ターゲットを明確にして計画を立てていくことも必要不可欠です。
 ペルソナとは?役割と定義、設定ポイントを解説
この記事では、マーケティングにおけるペルソナの定義や重要性を詳しく解説し、ターゲットとの違い、効果的なペルソナ設定のポイント、そして具体的な活用方法についてもわかりやすく説明しています。
ペルソナとは?役割と定義、設定ポイントを解説
この記事では、マーケティングにおけるペルソナの定義や重要性を詳しく解説し、ターゲットとの違い、効果的なペルソナ設定のポイント、そして具体的な活用方法についてもわかりやすく説明しています。
2.カスタマージャーニーマップの作成
カスタマージャーニーとは、ユーザーが製品の購入に至るまでの、商品を認知した流れや、どのように関心を深めていったのか、行動や思考、感情などといったプロセスのことをいいます。カスタマージャーニーを作ることで、顧客目線で施策を考えると同時に、社内での共通認識が持てるメリットがあります。
顧客の行動理由が分かってくれば、どのような手段を取っていけば集客に繋がるのか考えられるようになります。さらに、その情報を社内で共通認識として共有することで、チームで顧客獲得に向けた目標を立てたり、施策を実行したりすることが効率的に行えるようになるでしょう。
コンテンツのブレをなくすためにも、カスタマージャーニーで顧客の行動を把握しておくことが肝心です。
 カスタマージャーニーマップとは?目的と作り方、事例を解説
カスタマージャーニーマップは、顧客が購入に至るまでのプロセスを視覚化し、マーケティング戦略の最適化に役立つツールです。カスタマージャーニーマップの目的や作成方法、実際の事例について解説しています。
カスタマージャーニーマップとは?目的と作り方、事例を解説
カスタマージャーニーマップは、顧客が購入に至るまでのプロセスを視覚化し、マーケティング戦略の最適化に役立つツールです。カスタマージャーニーマップの目的や作成方法、実際の事例について解説しています。
3.競合コンテンツの分析
次は競合コンテンツの分析です。業界の動向や市場の動向など、競合の取り組みといった外部環境を理解しましょう。競合コンテンツ分析を行っていく方法としては、自社顧客へのアンケートインタビューを実施したり、サポート部門や営業部門などからヒアリングを行い、内部環境を調べるなどの方法があります。
「なぜ、顧客が競合コンテンツに流れているのか」「競合相手は何を考えてそのようなマーケティングを行なっているのか」などの情報をキャッチできれば、より差別化した宣伝やSNS を活用した投稿が行えるようになるでしょう。
4.導入チャネルの設計
具体的なイメージができてきたら、今度はどのような流入経路に向けたコンテンツマーケティングを行っていくのか、導入チャネル設計も重要になってきます。顧客や競合がよく使っているものの分析も行い、より効果を発揮するようなチャネルを選択していきましょう。
また、自然検索に強い施策を練るのか、はたまた広告を活用した流入経路を考えていくのかなども影響してくるため、さまざまな可能性を想定したうえで、CV率を高められる方法も考えるようにしていくといいでしょう。
見当違いなチャンネルを選択してしまわないように、各SNSのメリット・デメリット、マーケティングの方法として向いているケースなども忘れずに把握しておくことも大切です。
5.KPI・KGI設計
KPI設計とは、目標達成のための中間的な指標を指し、KGI設計は最終目標を達成できたかどうかの指標のことです。これらを決めていくためにはコンテンツ運用時の指標を決めていくことが重要です。
中長期的な施策になるコンテンツマーケティングの成果をどんな数値で判断するのか決めて、その数値をクリアするための分かりやすく意味のあるKGIとKPIを設定していきます。また、指標を決める際は、コンテンツを投入する段階と、グロース段階で変更していくなど、全体的なプロセスを考えた指標設計が必要となります。
指標を低く見積もってしまうと、実際に得られる効果が減少してしまったり、指標を高く見積もりすぎると、余計なコストがかかってしまったりしてしまいかねません。KGIを達成するためには、目標を達成させるために必要な中間の行動を示すKPIを最適な数値で設定することができれば、CV率を高めることも可能です。
 KPI指標とは?KGIとの違い、設定例を分かりやすく解説
重要な指標を設定し、目標達成のために具体的な施策を考えるためにKGI、KPIを設定する手法が一般的です。では、具体的にどのようにKGI、KPIを設定すればいいのでしょうか?OKR、KSFの紹介とあわせて解説します。
KPI指標とは?KGIとの違い、設定例を分かりやすく解説
重要な指標を設定し、目標達成のために具体的な施策を考えるためにKGI、KPIを設定する手法が一般的です。では、具体的にどのようにKGI、KPIを設定すればいいのでしょうか?OKR、KSFの紹介とあわせて解説します。
6.コンテンツの設計
具体的な指標が決まったら、次は制作するコンテンツを具体的に設計していきます。最終目標を達成するための方向性を決めていきましょう。コンテンツ制作は内製化する場合と、外部パートナーを活用する場合の2つのケースがあります。
コンテンツ制作を内製化するメリット・デメリット
コンテンツ制作を内製化するメリットは、オペレーションがチームで円滑に進められることがあげられます。コンテンツ制作を内製化すれば社内スタッフだけで計画を進めていくことになるため、情報の共有やノウハウの蓄積などが効率的に行えます。
また、外注コストがかからなくなることも魅力です。しかし、コンテンツ設計を他の仕事と同時進行する必要性が出てくることから、短期間での大量生産は難しい傾向にあります。加えて、専門的な知識が求められたり体制作りをしなければならなかったりと、時間的なコストがかかってしまう点はデメリットとなりえます。
外部パートナーを活用するメリット・デメリット
パートナーを活用してコンテンツ制作を行う場合は、専門家に依頼することになるため、専門的な知見を得られると同時に最終目標に最短で進められるメリットがあります。また、社員に対する負担も和らげることができるため、人的リソースを最低限で回せることも強みとなります。
しかし、内製とは違いプロにほとんどを任せてしまうことになるため、ノウハウが蓄積しにくくなってしまう点には注意が必要です。他にも、自社が十分なコンテンツ制作に関しての知識を持っている場合、外注したほうが製作に時間がかかってしまうケースも存在しています。
そのような失敗をしないためにも、自社が十分な人材を確保できているのか、専門家と相談しながら進めたほうがいいのか、会社の状況に合わせて選択していきましょう。
7.運用体制の設計
コンテンツマーケティングを行うにあたって最大の壁といわれるのが、継続してコンテンツを運用していくことです。継続するためには計画性が必要となるため、工程ごとの責任を明確化したチーム編成が何よりも大切です。
コンテンツを継続するためのチーム編成を行うときは、
- 計画を進行し、進捗管理や予実管理をする「プランナー」
- コンテンツの質を管理するコンテンツ「管理者」
- 実務的にコンテンツを制作する「製作者」
- サイトのグロースハックや炎上対策を行う「運用者」
- 効果測定や課題分析などを行う「アナリスト」
などといった、それぞれの専門家や責任者が必要となります。
外注する際は全てを担当してもらえるケースもありますが、社内にも外注先との相談が行えるスタッフが必要になります。自社で行う場合は必ずチーム編成を行って、誰がどの分野で責任を持つのか所在をはっきりとさせておきましょう。
担当者が決まっていれば、どのように対処していけばいいのか、緊急時に誰が担当するのか慌てずに対処して行けるようになります。当然、専門的な知識も必要となってきますがコンテンツマーケティングを行っていくうえでは必要不可欠な存在です。
特に、アナリストは課題解決をするための方法も導き出していく必要があります。もし何かしらの問題があった場合や変更が必要な場合は、またプランナーから計画を立てていくことにもなるため、いつでも連携がとれるような体制づくりを行っておきましょう。
8.効果測定
運用体制の構築が終わり、実際にコンテンツをいくつか発信し始めたら今度は数値を計測する必要性が出てきます。事前に決めてあるKPI設計に基づいて数値検証を行うようにしましょう。数値に満たない場合はさらなるブラッシュアップを行い、設計をし直したり一部を修正したりなど軌道修正していきます。
問題なく安定した効果が測定できるようになったら、最終目標が達成できたかどうかを判断することになります。
最終目標を達成できていたら、それを継続していくのかまたまた強化していくのか、最終目標が達成できていない場合はもう一度改善を行っていきましょう。常に数値を検証しアップデートする準備ができていれば、トラブルが起きた時などにもスムーズに対策を取れるようになります。
9.改善グロース
改善グロースとは、KPIやKGIの数値に基づいて、成長するための改善を行うことを指します。
改善の基本は、改善のインパクトが大きくてある程度伸び幅が決まっているファネルの底から行なっていくことになります。
例えば、ECサイトの場合、なぜユーザーが購入に至らなかったのかその原因から調べ始めて、問題点を洗い出します。そこから何が足りないのか分析していけば、SNSを使ったコンテンツマーケティングの弱点や改善点を発見して行けるようになるでしょう。
コンテンツマーケティングにおけるSNS活用のまとめ

コンテンツマーケティングは、個人を対象としたB2Cとの相性が良い方法となります。しかし、コンテンツマーケティングの効果を高めていくためには、チャネルに適した数値計測やコンテンツ設計、導線の設計などさまざまなポイントを押さえなければなりません。
SNSを活用するコンテンツマーケティングは、広告宣伝とは異なることから、ノウハウを持っていない方や企業は外部パートナーを活用することをおすすめします。コンテンツマーケティングの企画にお悩みの際は、ぜひニュートラルワークスにご相談ください。
サイトの成果改善でお困りではないですか?
「サイトからの問い合わせを増やしたいが、どこを改善すべきか分からない…」そんなお悩みをお抱えの方、ニュートラルワークスにご相談ください。
弊社のサイト改善コンサルティングでは、サイトのどこに課題があるかを実績豊富なプロが診断し、ビジネスに直結する改善策をご提案します。
SNSのコンテンツマーケティングのよくあるご質問
- SNSのコンテンツマーケティングのメリットは?
-
SNSは、多くの人が利用するプラットフォームであり、コンテンツを共有しやすい環境です。また、SNSを活用することで、企業はターゲット層に直接アプローチすることができ、ブランド認知度を高め、顧客とのコミュニケーションを促進することができます。
- コンテンツマーケティングでのSNSの活用方法は?
-
SNSを活用するためには、まず自社のターゲット層がどのようなSNSを利用しているかを調査することが大切です。その上で、各SNSに合ったコンテンツを制作し、定期的に投稿することで、フォロワーを獲得し、エンゲージメントを高めることができます。
- SNSでコンテンツマーケティングをする注意点は?
-
SNSでコンテンツマーケティングをする際の注意点は、炎上リスクの回避です。偽装や不正手法を避け、公正かつ正確な情報を提供するようにしましょう。また、何を目的として宣伝を行うのか計測する数値を決めておくことをおすすめします。