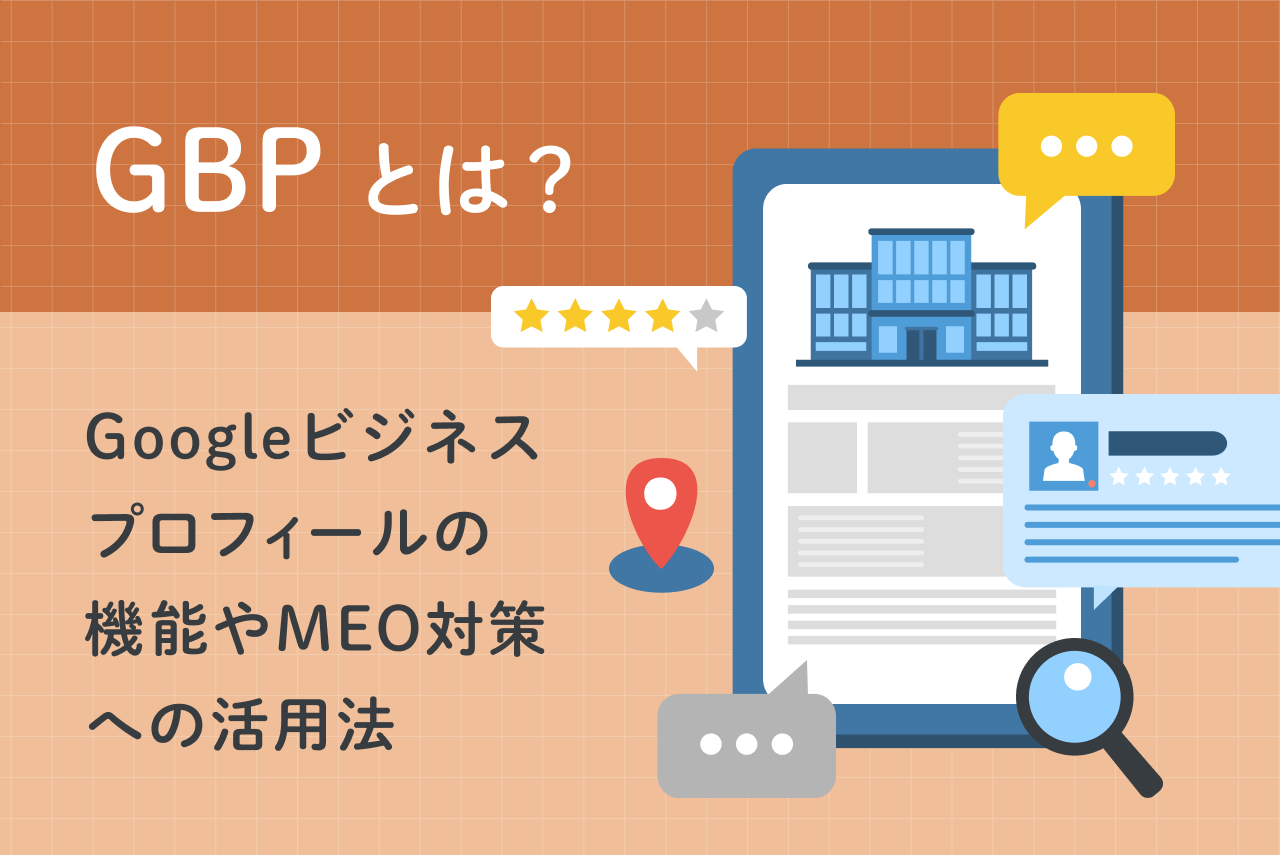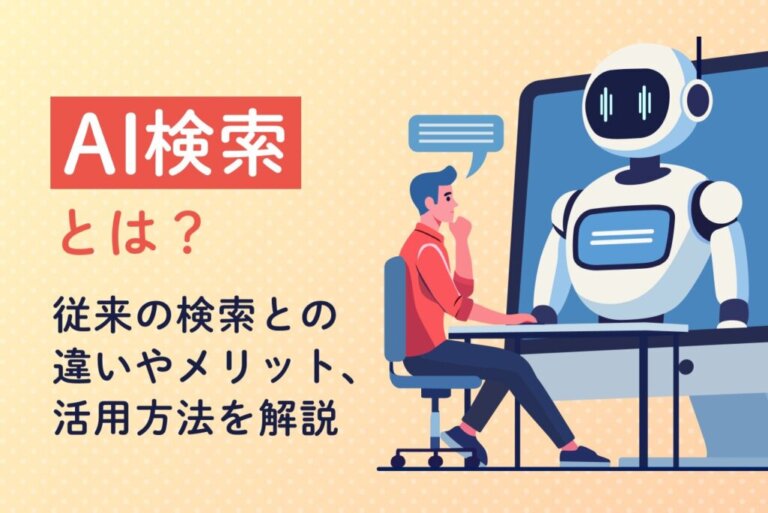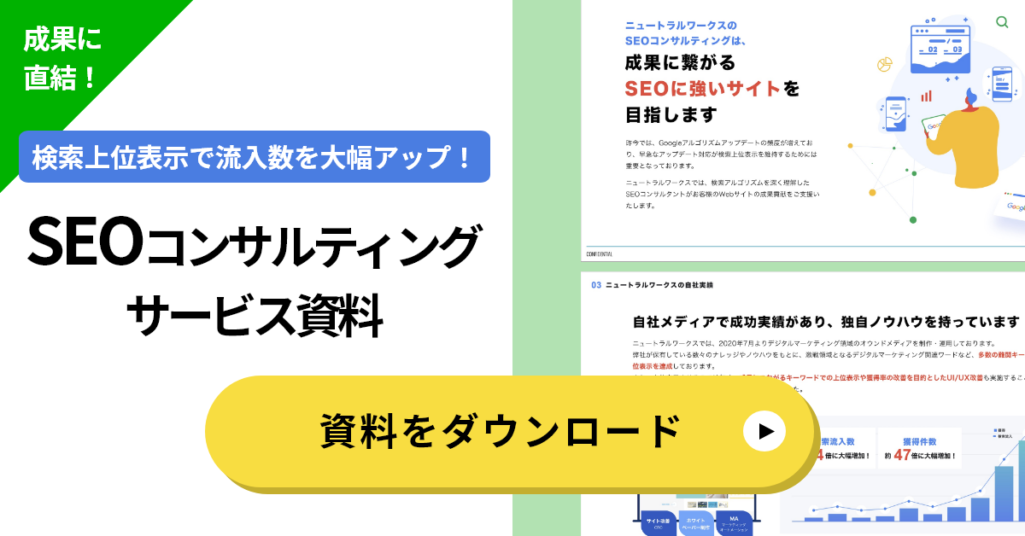この記事のポイント
この記事のポイントは以下です。
-
NAPって何?MEOでなぜ大事なの?
-
店舗名・住所・電話番号の統一情報(NAP)は、検索順位や信頼性に直結します。表記ゆれがあると評価が下がるため、全チャネルでの統一が必要です。
-
NAP情報を整えるにはどうすれば?
-
まず表記ルールを決め、全拠点・全チャネルの情報を見直します。専用ツールやチェックリストを使うと効率的です。
-
整えたNAPの効果はどう測る?
-
表示回数、電話件数、来店数などで確認できます。定期チェックと更新体制が、MEO成果の安定につながります。
ローカルSEOで競合に差をつけるために、MEO(Map Engine Optimization)の実践は欠かせません。特に、Googleマップやローカル検索における表示順位を左右する要素として、NAP(Name/Address/Phone)情報の正確性と統一性が重要視されています。
しかし、支店数が増えるほど情報のばらつきや管理の煩雑さが課題となります。本記事では、MEO成功者が実践しているNAP情報統一のチェックリストを中心に、実務に役立つ対策を網羅的に解説します。
<無料>資料ダウンロード
【店舗オーナー様必見】MEO対策代行サービス
短期間で優良顧客を集客できるMEOサービスをご紹介!
目次
NAPとは?MEO対策の基礎を整理しよう

NAPとは何か、そしてなぜその統一がMEOの成果に直結するのでしょうか?まずは基本に立ち返り、GoogleがどのようにNAP情報を評価し、ローカル検索順位に影響を与えているのかを解説します。
NAPの定義と構成要素(Name/Address/Phone)
NAPとは、Name(店舗名・会社名)、Address(住所)、Phone(電話番号)の頭文字をとったもので、Googleをはじめとする検索エンジンがローカルビジネスを識別するための基本情報です。
この情報がWebサイト、Googleビジネスプロフィール、業種別ディレクトリ、SNSなど各種チャネルに掲載されており、それらすべてにおいて「表記が一致」していることが求められます。
表記揺れ(例:「〇〇商店」と「〇〇ショップ」)や、記載の有無、情報の不一致があると、検索エンジンは「同一店舗かどうか」を判断できず、評価が分散してしまう可能性があります。まずは正しいNAP情報の定義を理解することが第一歩です。
 Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の使い方!活用法と改善ポイントも解説
Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は、Google検索やマップ上でビジネス情報を無料で管理・表示できるツールです。この記事では、基本的な使い方や活用法、改善ポイントを詳しく解説しています。
Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の使い方!活用法と改善ポイントも解説
Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は、Google検索やマップ上でビジネス情報を無料で管理・表示できるツールです。この記事では、基本的な使い方や活用法、改善ポイントを詳しく解説しています。
NAPがローカル検索順位に与える影響とGoogleの視点
Googleのローカル検索順位は主に「関連性」「距離」「知名度」の3要素で評価されていますが、この中でも「関連性」と「知名度」にNAPの正確性が大きく影響します。
たとえば、Googleビジネスプロフィール上の店舗名と公式Webサイトの表記が微妙に異なっていると、Googleのアルゴリズムはその情報を完全には一致するものと判断できず、検索結果に反映されないことがあります。
また、他サイト(ローカルディレクトリやSNS)に掲載されている情報と食い違っている場合も同様です。Googleは一貫性のある情報を「信頼性が高い」と評価するため、NAPの統一はローカル検索で上位表示を狙うための基本中の基本といえるでしょう。
最新アルゴリズムで求められるNAP一貫性:何が変わってきたか

近年のGoogle検索・GoogleマップにおけるローカルSEOアルゴリズムは、NAP情報の「一貫性」をより厳密に評価する傾向にあります。ここでは、MEOに影響するアルゴリズムの主要評価軸と、最近のアップデートがNAP統一にどう影響を与えているのかを具体的に見ていきます。
関連性・距離・知名度の3つの評価軸とNAPの関係性
Googleがローカル検索結果の順位を決める際に重視しているのが、「関連性」「距離」「知名度」という3つの評価軸です。これらの要素は、ユーザーの検索意図に対して最も適切なビジネス情報を提示するために活用されており、特に「関連性」と「知名度」はNAPの正確さと密接に関係しています。
たとえば、ユーザーが「◯◯市 カフェ」と検索したとき、Googleはその地域に該当する情報をもとに候補を抽出しますが、NAP情報に表記揺れや誤りがあると、正確に該当エリアの店舗だと認識されにくくなります。
また、知名度についても、NAP情報が各種ディレクトリやレビューサイトに一貫して掲載されていることで、外部評価が高まり、信頼性が増します。結果として、表示順位にも好影響を与えるのです。
 MEO対策で上位表示するためには?必要な要素から具体的な施策方法まで公開
MEO(Map Engine Optimization)対策は、Googleマップでの店舗情報の上位表示を目指す施策です。この記事では、上位表示に必要な要素や具体的な施策方法を詳しく解説しています。
MEO対策で上位表示するためには?必要な要素から具体的な施策方法まで公開
MEO(Map Engine Optimization)対策は、Googleマップでの店舗情報の上位表示を目指す施策です。この記事では、上位表示に必要な要素や具体的な施策方法を詳しく解説しています。
最近のGoogleマップ/検索アップデートとNAP情報への影響
Googleはローカル検索の品質向上を目的に、定期的にアルゴリズムを更新しています。近年では、ユーザー体験(UX)や正確なビジネス情報の提供がより重視されるようになり、NAP情報の整合性が検索順位への影響を強めています。
具体的には、2024年以降のアップデートでは、同一チェーン・ブランドであっても、拠点ごとの情報が正しく記載されていない場合には、ローカルパックから除外されるケースが報告されています。また、誤ったNAPが口コミやQ&Aに反映されていると、それもマイナス評価の一因となる可能性があります。
こうした背景から、NAP情報の統一は単なる「表記の問題」ではなく、Googleのアルゴリズムに対する「構造的な対応策」として捉えるべきなのです。特に多店舗展開している企業にとっては、更新漏れや支店ごとの誤差が致命的な検索順位低下につながる可能性があります。
 UI/UXとは?意味と違いをわかりやすく解説
この記事では、UI/UXのデザインに焦点をあてて解説します。近年競合サイトとの差別化を図るために、「UI」および「UX」が重要視されています。その理由やデザインする際のポイントなど、初めての方でも「UI」と「UX」について理解できるように紹介します。
UI/UXとは?意味と違いをわかりやすく解説
この記事では、UI/UXのデザインに焦点をあてて解説します。近年競合サイトとの差別化を図るために、「UI」および「UX」が重要視されています。その理由やデザインする際のポイントなど、初めての方でも「UI」と「UX」について理解できるように紹介します。
複数支店でのNAP統一:実践ステップと体制づくり

複数の支店や営業所を持つ企業にとって、NAP情報を正確かつ一貫して管理することは一層の難易度を伴います。このセクションでは、実務的な観点から、表記ルールの作成と情報統一のための組織的な運用体制の構築方法を解説します。
表記ルールを設ける:名前・住所・電話のフォーマット統一
最初のステップは、社内で共通の「NAP表記ルール」を明文化することです。これは単なる社名や電話番号の記載方法だけではなく、記号の使い方、建物名の有無、全角・半角、漢数字・アラビア数字の使い分けまで含めた詳細なガイドラインを設けることを意味します。
たとえば、「株式会社◯◯」と「(株)◯◯」のような略称表記の違い、「1丁目5-3」と「1-5-3」のような地名表記の揺れは、検索エンジンにとっては別の情報として認識される可能性があります。こうした表記ブレを防ぐためには、以下のようなフォーマットを定めておくとよいでしょう。
- 会社名は正式名称を使用(略称不可)
- 住所は郵便番号付き・都道府県から始める
- 電話番号は市外局番からハイフン区切りで統一(例:03-xxxx-xxxx)
このようなルールをドキュメント化し、社内の関係者や各支店に共有することで、情報のばらつきを未然に防げます。
各拠点/オンラインチャネルでの情報整合性チェック
表記ルールを設けた後は、すべての支店・チャネルにおいて、NAP情報がそのルールに基づいて統一されているかをチェックします。対象となるチャネルは多岐にわたり、以下のようなものが含まれます。
- 自社公式Webサイト(支店ページ含む)
- Googleビジネスプロフィール
- 地域ポータルサイト、業種別ディレクトリ
- SNSアカウント(Facebookページ、Instagramなど)
- 地図アプリ(Apple Maps、Yahoo!ロコなど)
この際、有効なのが「NAPチェックリスト」の導入です。各支店ごとに、上記チャネルのNAP情報を一覧化し、表記ブレがないか目視で確認する方法です。手動での作業が難しい場合は、ツールを使ったクローリング・分析を活用することも検討できます。
また、情報の統一だけでなく「情報の最新性」も確認しましょう。電話番号の変更、移転後の住所更新、営業時間の修正漏れなどは意外と頻発します。情報整合性を保つためには、チェックの実施頻度も定期的に設定しておくことが重要です。
コストを抑えたツールと運用フローで効率化する方法

中小企業にとって、MEO対策に割けるリソースは限られているのが現実です。そこで重要になるのが、手間やコストを最小限に抑えながらも、NAP情報の統一と運用を効率化する仕組みの構築です。
ここでは、実務に役立つ無料・有料ツールと、現実的な運用フローの設計方法を解説します。
効果的な管理ツールとその使いどころ(無料/有料)
NAP情報の管理においては、専用のMEO管理ツールを活用することで作業の効率が大きく向上します。これらのツールには、以下のような機能があります。
- Googleビジネスプロフィールとの連携による一括編集
- 表記ゆれ検出機能(ディレクトリ情報との比較)
- 定期レポートの自動生成
- 多店舗情報の一元管理ダッシュボード
中小企業であれば、まずは無料のGoogle公式ツールである「Googleビジネスプロフィール マネージャー」から始めるのがおすすめです。ある程度店舗数が多い場合は、低価格帯のMEO専用ツール(例:数千円/月〜)を検討する価値があります。
ポイントは、「すべての管理をツールに頼りすぎない」こと。手作業で確認すべき箇所と、ツールに任せて自動化すべき作業の境界線を明確にすることが、コストパフォーマンスの高い運用の鍵となります。
運用体制とチェック周期の設計:リソースを割く優先順位
ツール導入と並行して考えたいのが、社内の「運用体制」と「チェックの頻度」です。いくらツールが優れていても、活用する体制や人材が不在であれば運用は続きません。
まず重要なのは、誰がNAP情報の管理責任者となるのかを明確にすることです。多くの企業では、マーケティング部門や広報担当が担いますが、複数部門にまたがる場合は「統括担当者」として役割を一本化することが望まれます。
次に、チェックの周期を決めます。以下のようなスケジュールが一例です。
- 月1回:各チャネルのNAP情報チェック(更新漏れや表記ブレ確認)
- 四半期ごと:全支店情報の棚卸し、ガイドラインの見直し
- 随時:営業時間や移転など変更があった場合の即時反映
特に重要なのは、「変更が起きたときのフロー」を整備しておくことです。たとえば、電話番号が変わった際に誰が、どこに、いつまでに更新するかをマニュアル化しておけば、情報の不整合を最小限に抑えられます。
成果を可視化するKPIと長期的な維持戦略

NAP情報の統一が完了した後に重要になるのが、その成果を「可視化」し、継続的な改善へとつなげる仕組みの構築です。この章では、オンライン・オフライン両面のKPI(重要業績評価指標)と、それらを活用した長期的な維持・改善戦略について解説します。
オンライン指標とオフライン指標の連携(来店数・電話・レビュー)
MEO施策の効果を測定するには、Googleビジネスプロフィールをはじめとする各種ツールから取得できる「オンライン指標」と、実際の顧客行動に関する「オフライン指標」の両方を追跡・連携することが重要です。
【主なオンライン指標】
- Google検索での表示回数(インプレッション)
- マップ表示での位置順位
- ビジネスプロフィールへのアクセス数
- ルート案内のクリック数
- ウェブサイトへの遷移数
【主なオフライン指標】
- 電話件数(通話計測ツールで計測)
- 来店数(POS連携やスタッフカウント)
- 顧客レビュー数と平均評価
- クーポン使用数や予約数
これらのデータを月次や四半期ごとに記録・比較することで、NAP情報統一がローカル検索の成果にどう影響しているかを明確に把握できます。また、Googleアナリティクスやサードパーティの分析ツールと連携することで、さらに多角的な分析も可能です。
定期モニタリングと修正プロセス:表記揺れ・情報変更・アルゴリズム対応
NAP情報の統一は一度整備したら終わりではなく、継続的に「維持・修正・改善」していくことが求められます。特に以下の3つの観点でのモニタリングが不可欠です。
1.表記揺れの再発防止:
運用メンバーが異動・交代した場合や、新たな店舗が追加された際に、古い表記パターンが使われてしまうことがあります。社内ガイドラインの共有と更新履歴の管理を徹底することが重要です。
2.情報変更への即時対応:
電話番号の変更、営業時間の調整、支店の閉鎖や移転などがあった際は、すぐに全チャネルでの修正が必要です。そのためのフローを明文化しておくと、対応漏れを防げます。
3.検索アルゴリズムの変化への適応:
Googleのローカル検索アルゴリズムは定期的に変更されます。アップデート内容によっては、NAP情報の扱われ方も変化するため、業界ニュースやGoogleの公式アナウンスを常にチェックし、必要に応じて情報構成を見直すことが求められます。
継続的なモニタリングと改善を行うことで、NAP情報の精度と信頼性を維持し、MEO施策の長期的な成果を安定して確保できます。
NAP情報の信頼性を高める第三者サイトの活用法

MEOにおいては、Googleビジネスプロフィールの整備だけでは不十分です。外部サイトとの情報整合性が取れていなければ、Googleからの信頼性は低下します。
ここからは、第三者のディレクトリサイトや口コミサイトを活用して、NAP情報の信頼性を高める方法について解説します。
業種別ローカルディレクトリと口コミサイトの選定基準
Googleは、自社が保有する情報だけでなく、第三者サイトに掲載されているビジネス情報もクロールし、順位評価に反映しています。そのため、外部サイトにおいても正確で一貫性のあるNAP情報が掲載されているかどうかは、非常に重要です。
掲載先としては、以下のような業種別ディレクトリサイトや口コミサイトが挙げられます。
- 飲食業: 食べログ、ぐるなび、Retty など
- 美容業: ホットペッパービューティー、ミニモ
- 医療機関: EPARK、QLife、Caloo など
- 教育・塾: 塾ナビ、エキテン
選定時のポイントは、「検索上位に表示されやすい」「ユーザー利用率が高い」「Googleが高く評価している(被リンク数やドメインパワーがある)」といった信頼性です。まずは自社の業界で主に利用されている3〜5サイトを選び、そこに記載されたNAP情報の正確性を確認しましょう。
外部情報とGoogleビジネスプロフィールの整合性確認のポイント
第三者サイトの情報が、自社のGoogleビジネスプロフィールと一致しているかを確認するためには、次のようなプロセスを取り入れると効果的です。
- NAP項目を一覧表にまとめる:
自社のGoogleビジネスプロフィールを基準に、名前・住所・電話番号の項目を縦軸に、掲載先サイトを横軸にした一覧表を作成します。 - 表記の一致をチェックする:
全角・半角、略称、建物名の有無など、細かい違いにも注目して確認します。特に番地の表記や市区町村名の揺れが多いため、注意が必要です。 - 修正依頼または管理権限の取得:
掲載情報が正しくない場合、該当サイトの管理画面から修正申請を行うか、オーナー申請をして管理権限を取得することで対応できます。
このように、外部サイトとのNAP整合性を継続的にチェック・更新することで、Googleからの評価を高め、MEOの成果につながります。
社内でNAP統一を推進するための巻き込み戦略

NAP情報の統一はマーケティング部門だけで完結するものではありません。営業、店舗運営、システム、広報など、複数部門が関与するため、社内全体を巻き込んだ取り組みが必要です。この章では、社内での理解促進や協力体制の構築方法について紹介します。
部門横断的に情報を管理・連携する仕組み
NAP情報は、現場での変更や新規拠点の開設などが日々発生する性質のため、情報源が分散しやすく、属人的な管理に陥りがちです。これを防ぐには、部門横断で統一された管理体制を作る必要があります。
まずは、全社共通で使用する「NAP管理表」を作成し、各店舗や部署が変更時にその情報を更新・共有できるようにします。この管理表は、Googleスプレッドシートや社内クラウドツールを使えば、誰でもリアルタイムに確認・編集が可能です。
さらに、以下のような連携体制を構築すると運用がスムーズになります:
- 店舗運営:実地の住所や電話番号の最新情報を提供
- マーケティング:WebやGoogleビジネスプロフィールへの反映を担当
- 情報システム:社内DBや外部連携システムの整備・更新支援
- 広報・総務:公式リリースや印刷物との整合性確認
このように、部門ごとに役割を明確化し、責任範囲を共有することで、NAP統一が「全社的な業務」として認識されやすくなります。
経営陣・現場スタッフへの啓発と運用ルールの定着化
MEOやNAPの重要性は、マーケティング部門では理解されていても、現場スタッフや経営層には伝わっていないケースが少なくありません。そのため、社内全体への啓発活動が欠かせません。
特に、以下の2点に注力すると効果的です。
1.経営層への訴求:
「NAP情報が統一されていないことによって、どの程度の機会損失が生じているのか」「競合と比べて検索順位で不利になっている可能性」など、数値と事例を交えて説明することで、予算や人員の確保がしやすくなります。
2.現場スタッフへの周知と教育:
実店舗の住所変更や電話番号変更を把握しているのは、往々にして現場です。そこで、変更時の連絡ルールや定期報告のフローを作成し、店舗マニュアルや研修資料に組み込むことが推奨されます。
また、社内イントラや掲示板に「NAP変更時のチェックリスト」を掲載しておくと、意識づけとミス防止につながります。
NAP情報の更新ミスが引き起こすビジネス損失とは

NAP情報の更新を怠ると、単なる「情報のズレ」にとどまらず、実際のビジネス損失やブランド毀損に直結するリスクがあります。この章では、更新ミスによる具体的な影響と、そうしたリスクを回避するための予防策を解説します。
誤ったNAP情報がもたらすユーザー離脱とクレームの実例
住所や電話番号の誤表記は、ユーザー体験を著しく損ない、直接的な売上減少やクレームに発展する恐れがあります。たとえば、次のようなケースが現実に発生しています。
- 電話番号が古いまま: 顧客が問い合わせをしようとしても繋がらず、機会損失に。さらに「電話がつながらない=信用できない」という印象を与えてしまいます。
- 移転後の住所未更新: Googleマップのナビで旧店舗に案内されてしまい、来店できなかった顧客からの低評価レビューにつながる事例も報告されています。
- 営業時間の誤記載: 閉店後に来店した顧客が不満を持ち、SNSに悪評を書き込まれるリスクが高まります。
このような小さな更新ミスが、「ユーザーの信頼喪失」「口コミ評価の悪化」「再訪率の低下」といった深刻な結果につながりかねません。MEO対策は「検索順位を上げる」ためだけでなく、「顧客の期待に応える情報提供」でもあるという認識が重要です。
情報改ざん・なりすましのリスクとその対策
NAP情報の管理がずさんだと、外部からの“なりすまし”や“情報改ざん”といったリスクにもさらされます。たとえば、Googleビジネスプロフィールは一部ユーザーによって提案・変更ができる仕組みになっており、悪意ある第三者や競合が意図的に誤情報を登録する事例も報告されています。
このようなリスクに備えるには、次のような対策が有効です。
- オーナー権限の厳格な管理: 各店舗のGoogleビジネスプロフィールを公式にオーナー登録し、誰が編集できるかを明確にしておく。
- 変更通知の監視: Googleからの「ビジネス情報が変更されました」通知を見逃さず、内容を確認・承認する体制を整える。
- 外部サイトのモニタリング: 口コミサイトやディレクトリに登録された情報も、定期的にチェックするルーティンを設定する。
特に多拠点企業では、誰がどの拠点の情報に責任を持っているかを明確にし、「誰かがやるだろう」状態を防ぐ体制構築がカギとなります。
他社と差がつく!NAP最適化の事例ベストプラクティス

理論や方法を理解しても、実際にどう進めればよいか悩むことも多いのがNAP統一です。そこでこの章では、実際の企業にありがちなケースをもとに、効果的だった施策のベストプラクティスを紹介します。自社での展開イメージを描く参考としてご活用ください。
多拠点企業で成功したNAP整備の施策事例
ある中堅の飲食チェーン企業では、都内を中心に20以上の支店を展開していましたが、店舗ごとに管理者が異なるため、Webサイト、Googleビジネスプロフィール、ポータルサイトにおける情報に食い違いが多発していました。
そこで同社が実施した施策は以下の通りです。
- 全拠点のNAP情報を一括で整理し、「統一フォーマット」を策定
- Googleスプレッドシートで管理台帳を作成し、各店舗担当者と共有
- 情報更新の責任者を本部マーケティング部に一元化
- 変更があった場合は本部経由で全チャネルを即時更新する運用に変更
この取り組みにより、Google検索およびマップでの表示順位が平均2〜3位ほど改善され、特に新規顧客の来店数が増加したとのことです。また、レビューサイトでの誤情報によるクレームも大幅に減少し、運用の安定性が向上しました。
NAP管理を仕組み化して負担軽減に成功したケースの共通点
NAP情報の最適化で成功している企業の多くには、ある共通点があります。それは、「属人化を防ぎ、継続的に回る仕組みを作っている」という点です。以下のような取り組みが有効だったとされています。
- 社内ポータルに「NAP変更申請フォーム」を設置
→ 店舗からの情報変更がある際、都度メールで確認するのではなく、所定のフォームから提出することで漏れ・手間を削減。 - 月1回の自動チェックルールを設定
→ MEO管理ツールで表記ゆれを自動検出し、差分が出た場合のみ人が確認することで効率化。 - ナレッジ共有会を開催
→ マーケティング部門が全店の支店長向けにオンラインで対策方法を共有し、意識づけを促進。
これらの仕組みを導入することで、手間とコストを最小限に抑えながら、持続可能なNAP運用体制を構築できた点が共通しています。
業務に変化をもたらすNAP統一、今すぐ始めるあなたの一歩

NAP情報の統一は、単なる“表記の整備”ではなく、ローカル検索での可視性向上、顧客体験の改善、そしてビジネス全体の信頼性向上につながる本質的な施策です。
とくに複数の拠点を持つ企業においては、情報のばらつきや更新漏れが直接的な機会損失に結びつくため、早期の対策が求められます。
まずは、自社のNAP情報を全チャネルで一覧化し、表記の統一ができているかをチェックしてみてください。小さな改善でも、積み重ねることで検索順位や顧客評価に大きな変化が現れるはずです。
この機会に、社内でのNAP運用体制を見直し、継続的に管理できる仕組みを導入する一歩を踏み出してみましょう。
また、他のMEO関連ノウハウも併せて確認することで、さらに一歩進んだ施策へとつなげていくことができます。
<無料>資料ダウンロード
【店舗オーナー様必見】MEO対策代行サービス
短期間で優良顧客を集客できるMEOサービスをご紹介!