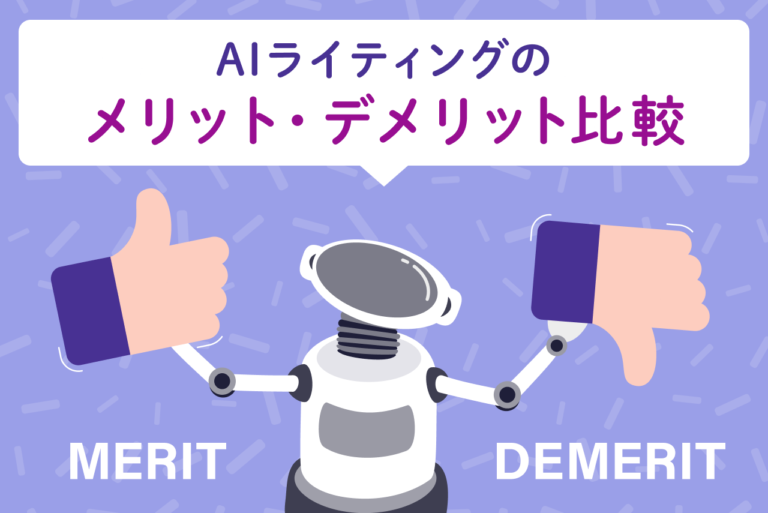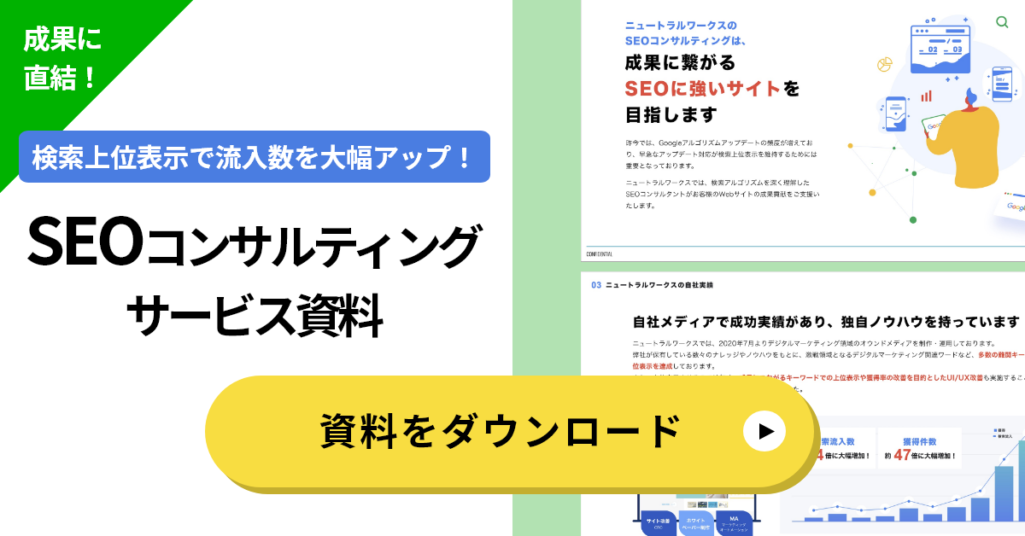この記事のポイント
この記事のポイントは以下です。
-
SEOに効果的なドメイン名の決め方は?
-
短くシンプルで覚えやすいドメイン名を選ぶことが重要です。目安として15文字以内にし、ブランド名やサービス内容が伝わるようにするのがベストです。
-
新規ドメインと中古ドメイン、どちらを選ぶべきか?
-
新規ドメインはSEOペナルティのリスクがなく、ブランディングの自由度が高い点がメリットです。中古ドメインは既にドメインパワーがある一方、過去にスパム行為があったドメインはリスクがあるため、購入前に履歴を確認することが重要です。
-
サブドメインとサブディレクトリはどちらがSEOに有利?
-
一般的に、サブディレクトリのほうがSEO効果を引き継ぎやすいとされています。一方、サブドメインは別サイトとして扱われるため、独立したコンテンツを展開する際に有効です。
SEO対策に強いドメイン名があるのか、気になったことはありませんか?
ドメイン名は、Webサイトを立ち上げる際に欠かせない要素のひとつです。適切なドメインを選ぶことは、ユーザーの印象やクリック率に関わり、結果的にSEO評価にも影響を与える可能性があります。集客力にも関わるため、ブランディングや利便性を意識した慎重な選定が求められます。
「SEOに強いドメインを選びたい」「集客につながるドメインの決め方を知りたい」そんな方に向けて、この記事ではSEOにおけるドメイン名の重要性や、効果的な決め方、ドメイン名を決める際の注意点などについて詳しく解説します。
<無料>資料ダウンロード
【プロにお任せ】SEOコンサルティング
見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決
目次
ドメイン名とは?

ドメイン名とは、インターネット上の住所のような役割を果たすWebサイトの識別名です。ユーザーが特定のWebサイトにアクセスする際に、長いIPアドレス(例:192.168.1.1)の代わりに使用されます。
例えば、「example.com」のような文字列がドメイン名にあたり、Webサイトのブランドや信頼性を示す要素としても機能します。
ドメイン名の3つの構成要素
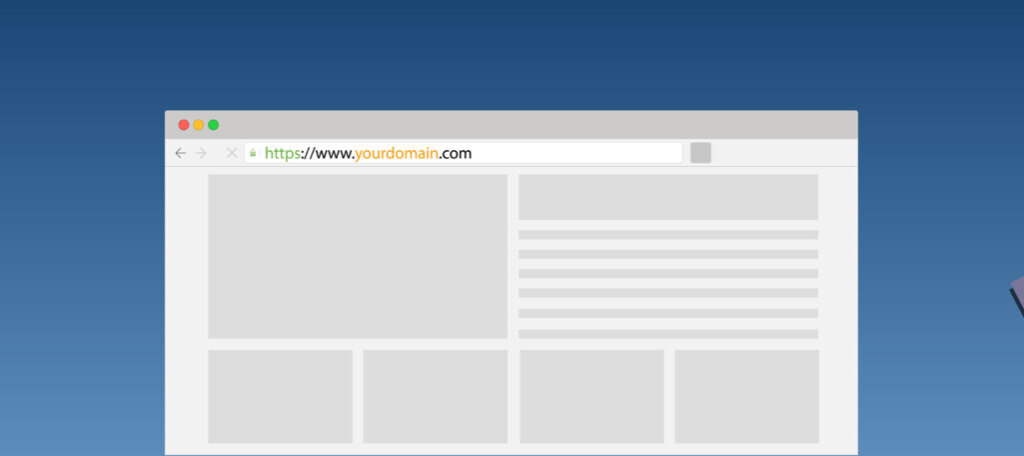
ドメイン名は複数の要素で構成されており、それぞれに役割があります。
1. TLD(トップレベルドメイン)
ドメイン名の最後に付く部分で、「.com」「.net」「.jp」などが該当します。主な種類は以下の通りです。
- gTLD(分野別トップレベルドメイン):.com、.net、.org など
- ccTLD(国別トップレベルドメイン):.jp(日本)、.us(アメリカ)、.uk(イギリス) など
TLDの選択は、特にccTLDにおいて検索対象国の設定に関わることがあり、間接的にSEOへ影響する場合があります。
2. SLD(セカンドレベルドメイン)
TLDの前にくる部分で、Webサイトの主要な識別子となる要素です。例えば、「example.com」の「example」の部分がSLDにあたります。
企業名やブランド名、サービス名などを入れることが一般的です。
3. サブドメイン
SLDの前に追加できる部分で、「blog.example.com」や「shop.example.com」のように、サイト内で異なるカテゴリーや用途を分けるために使用されます。
サブドメインはSEOに影響を与えるため、適切な設定が求められます。
ドメインとSEOの基本的な関係とは?

ドメイン名は、SEOに直接影響を与えるものではありませんが、その選び方や運用次第で間接的に評価に影響を与える重要な要素です。信頼感のある名称や覚えやすい文字列はクリック率の向上にもつながり、結果としてSEO全体によい効果をもたらす可能性があります。
ここからは、ドメインとSEOの関係について解説します。
ドメイン名はSEOに直接影響しない
現在のGoogleの検索アルゴリズムでは、ドメイン名にキーワードを含めても、それだけで検索順位が上がることはありません。
以前は効果があるとされていた時期もありますが、今では順位決定に与える影響はごくわずかです。検索エンジンが重視するのは、コンテンツの質や被リンク、ユーザー体験などの要素です。そのため、SEO効果を期待して無理にキーワードを入れる必要はありません。
ドメイン名はユーザー目線で決めるのが大切
適切なドメイン名の選択は、ユーザーの認知度やクリック率にも影響を与えます。特に、以下のようなポイントはユーザーの集客に、ひいては間接的にSEOへ関係します。
1. ブランド認知度の向上
短くてわかりやすいドメイン名は、ユーザーの記憶に残りやすく、SNSや口コミでの拡散にも有利です。
例えば、「travel-guide.com」のような直感的なドメインは、旅行関連のサイトであることが一目でわかるため、SEOと集客の両方にプラスになります。
2. URLのクリック率(CTR)向上
ユーザーが検索結果ページでリンクをクリックする際、ドメイン名が明確で信頼感があるとクリック率(CTR)が上がる傾向があります。
例えば、「best-hiking-shoes.com」のような明確なキーワードが含まれていると、検索結果に表示された際にターゲットユーザーがクリックしやすくなります。
 CTR(クリック率)とは?広告、SEOでの平均%、CTRの改善方法を解説
CTR(クリック率)は広告やSEOでのWeb集客を考えるのに欠かせない用語です。CTRの意味と、どのくらいの%なら問題ないのか、広告・SEOそれぞれでの改善方法を解説します。
CTR(クリック率)とは?広告、SEOでの平均%、CTRの改善方法を解説
CTR(クリック率)は広告やSEOでのWeb集客を考えるのに欠かせない用語です。CTRの意味と、どのくらいの%なら問題ないのか、広告・SEOそれぞれでの改善方法を解説します。
ドメインパワーと検索エンジンの評価
「ドメインパワー(ドメインオーソリティ)」とは、検索エンジンがドメインをどれだけ評価しているかを示す指標です。ドメインパワーが高いほど、SEOで有利になり、検索結果で上位表示されやすくなります。
ドメインパワーを決定する主な要因は以下の通りです。
1. 被リンク(バックリンク)
他の信頼性の高いサイトからリンクを受けることで、Googleはそのドメインを高く評価します。良質な被リンクが多いほど、ドメインパワーが向上します。
 被リンクとは?SEO効果のメリットから獲得方法やチェックツールを徹底解説
被リンクとは、他のウェブサイトから自サイトへのリンクを指し、SEOにおいて重要な役割を果たします。本記事では、被リンクの基本概念、SEO効果、獲得方法、チェックツールについて詳しく解説しています。
被リンクとは?SEO効果のメリットから獲得方法やチェックツールを徹底解説
被リンクとは、他のウェブサイトから自サイトへのリンクを指し、SEOにおいて重要な役割を果たします。本記事では、被リンクの基本概念、SEO効果、獲得方法、チェックツールについて詳しく解説しています。
 ドメインパワーとは?SEOでのドメイン評価の重要性と上げ方を解説
ドメインパワーは、Webサイトの信頼性や評価を示す指標で、SEOにおいて重要な役割を果たします。ドメインパワーの概要、評価方法、そして向上させるための具体的な施策について詳しく解説しています。
ドメインパワーとは?SEOでのドメイン評価の重要性と上げ方を解説
ドメインパワーは、Webサイトの信頼性や評価を示す指標で、SEOにおいて重要な役割を果たします。ドメインパワーの概要、評価方法、そして向上させるための具体的な施策について詳しく解説しています。
2. ドメインの年齢(運用期間)
新しいドメインよりも、長年運用されているドメインの方がSEO的に有利とされています。
ドメイン取得後、長期的な視点で運用を続けることが重要です。
3. コンテンツの質と一貫性
良質なコンテンツを継続的に提供することで、検索エンジンの評価が高まり、ドメインパワーが強化されます。特定のジャンルに特化したコンテンツを継続的に発信することで、専門性の高いサイトとして評価されやすくなります。
このように、ドメイン名自体だけでなく、その運用方法やSEO施策がドメインパワーに大きく影響します。
 E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOで重要なGoogleの評価基準を解説
E-E-A-Tは、Googleがウェブサイトの品質評価に用いる基準で、SEOにおいて重要な要素です。この記事では、各要素の意味やSEO対策への影響、具体的な改善方法について詳しく解説しています。
E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOで重要なGoogleの評価基準を解説
E-E-A-Tは、Googleがウェブサイトの品質評価に用いる基準で、SEOにおいて重要な要素です。この記事では、各要素の意味やSEO対策への影響、具体的な改善方法について詳しく解説しています。
 良質なコンテンツとは?SEOにおける要件を解説
SEOで重要な「良質なコンテンツ」とは、ユーザーのニーズに応え、正確で価値ある情報を提供するものです。この記事では、オリジナリティや読みやすさ、最新性などの具体的な要件を詳しく解説しています。
良質なコンテンツとは?SEOにおける要件を解説
SEOで重要な「良質なコンテンツ」とは、ユーザーのニーズに応え、正確で価値ある情報を提供するものです。この記事では、オリジナリティや読みやすさ、最新性などの具体的な要件を詳しく解説しています。
SEOを意識したドメイン名の決め方3つ

SEOやユーザビリティの観点から、適切なドメイン名を選ぶことは非常に重要です。先述の通り、ドメイン名はWebサイトの認知度やクリック率にも影響を与えるため、慎重に決定する必要があります。
ここからは、SEO評価に配慮したドメイン名選定のポイントについて解説します。
適切なTLDを選ぶ
一般的に、「.com」「.net」「.jp」などのTLD(トップレベルドメイン)は取得コストが比較的安く、信頼性も高いため、多くの企業や個人サイトで採用されています。
一方、「.store」「.xyz」などの新しいTLDはユニークな印象を与えられますが、認知度が低いため、SEO面でのメリットは限定的です。
また、TLDの選択はSEOだけでなく、ターゲットユーザーに与える印象にも影響します。例えば、企業サイトで「.com」を選ぶと一般的で信頼感があり、「.tech」はテクノロジー関連のサイトと認識されやすくなります。
ブランドや業種に適したTLDを選ぶことで、ユーザーの信頼感やクリック率が高まり、結果的にSEOにもよい影響を与える可能性があります。
サービスに関連したドメイン名にする
ドメイン名は、Webサイトの内容や目的が直感的に伝わるものを選ぶことが重要です。わかりやすいドメイン名は、ユーザーに覚えられやすく、クリック率向上などを通じて間接的にSEOにも好影響を与える可能性があります。
例えば、「tokyo-cafe.com」なら東京のカフェとすぐにわかるように、事業やサービスの特徴を反映すると効果的です。
また、かつてはキーワードを含むドメイン(EMD)がSEOに有利とされていましたが、現在では影響が弱まっています。それでも、「best-travel-guide.com」のように適度にキーワードを入れることで、検索意図と一致しやすくなるメリットはあります。
ただし、不自然な詰め込みは避け、シンプルでわかりやすいドメイン名を選ぶことが大切です。
使いやすく覚えやすいドメイン名にする
シンプルで直感的なドメイン名は、ユーザーにも検索エンジンにも評価されやすくなります。 以下のポイントを考慮し、伝わりやすく使いやすいドメイン名を選びましょう。
1. できるだけ短くする
短いドメインほど入力しやすく、記憶にも残りやすい傾向があります。
例えば、「apple.com」や「amazon.com」のような短くシンプルなドメインは、ブランディングにも有利です。目安として、15文字以内のドメイン名が理想的です。
2. 発音しやすく、タイピングしやすい名前にする
口頭で伝えやすいドメイン名は、認知度の向上につながりやすい ためおすすめです。
「tripadvisor.com」や「airbnb.com」のように、聞いたまま入力しやすい名称を選ぶとよいでしょう。一方で、複雑なスペルやハイフンの多用は避けるのが無難です。
3. 数字や記号を避ける
数字やハイフンを含むと、誤入力や認識ミスが発生しやすくなります。
例えば、「best-shoes-for-you.com」は長すぎてわかりにくいですが、「bestshoes.com」のようにシンプルな形なら、より直感的に伝わります。
必要に応じて中古ドメインの購入も検討する
ドメインを取得する際、「新規ドメイン」と「中古ドメイン」のどちらを選ぶかはSEOに影響を与えます。
| ドメインの種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 新規ドメイン | ・クリーンな状態でSEOペナルティのリスクがない
・ブランディングの自由度が高い |
・ドメインパワーがゼロからのスタート
・検索エンジンの評価を得るまでに時間がかかる |
| 中古ドメイン | ・すでに一定のドメインパワーを持っている可能性がある
・被リンクが豊富な場合、検索エンジンの評価を受け継げる |
・過去にスパムサイトとして使用されていたリスクがある
・取得前に履歴調査が必要 |
新規ドメインは、過去の履歴がなくクリーンな状態のため、SEOペナルティのリスクがありません。ただし、ドメインパワーをゼロから蓄積する必要があるため、検索エンジンの評価を得るまでに時間がかかります。一方で、ブランディングの自由度が高いというメリットがあります。
一方、中古ドメインは、すでに一定のドメインパワーを持っている場合があり、SEOの面で有利に働く可能性があります。特に被リンクが豊富な場合、検索エンジンの評価を受け継ぐことができます。
しかし、過去にスパムサイトとして使用されていた履歴があると、逆にSEOに悪影響を与えるリスクがあるため、取得前に「Wayback Machine」「Ahrefs」「Majestic」などのツールで履歴を確認することが重要です。
SEOを意識するなら、クリーンな中古ドメインを選ぶか、新規ドメインを長期的に育てることが基本戦略になります。
 中古ドメインとは?メリット・デメリット、失敗しない選び方を解説
中古ドメインは、過去に使用されていたドメインでSEO対策において新規ドメインと比較してメリットとデメリットがあります。この記事では、中古ドメインの特徴、選び方、SEOへの影響について解説しています。
中古ドメインとは?メリット・デメリット、失敗しない選び方を解説
中古ドメインは、過去に使用されていたドメインでSEO対策において新規ドメインと比較してメリットとデメリットがあります。この記事では、中古ドメインの特徴、選び方、SEOへの影響について解説しています。
サブドメインとサブディレクトリの選択
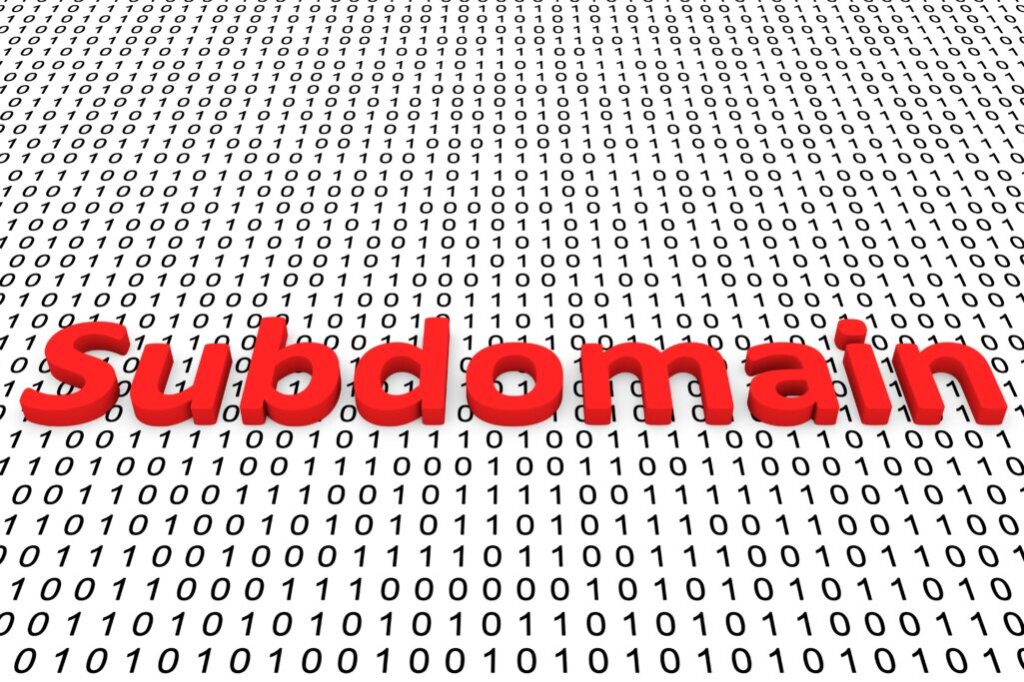
Webサイトを運営する際、新しいページを追加する方法として「サブドメイン」と「サブディレクトリ」のどちらを選ぶかは重要な判断となります。どちらを選択するかによって、SEOの評価やサイトの管理方法が変わるため、適切な使い分けを理解することが重要です。
新しいWebページ追加時の使い分け
新しいWebページを追加する際、サブドメイン(sub.example.com)とサブディレクトリ(example.com/sub/)のどちらを選択するかは、Webサイトの目的や運用方針によって異なります。
サブドメインを使用するケース
サブドメインは、メインサイトとは異なる独立したコンテンツやサービスを提供する場合に適しています。 Googleはサブドメインを別のサイトとして扱うため、SEO戦略を分けて運用する場合に有効です。
<サブドメインを活用すべきケース>
- ブログやメディアサイトを独立運用(例:blog.example.com)
- ECサイトと企業サイトを分ける(例:shop.example.com)
- 異なる言語や地域向けサイトを運営(例:jp.example.com / en.example.com)
- 特定のサービスやアプリを別ドメインで運用(例:app.example.com)
サブドメインを使用することで、コンテンツごとに独立したSEO対策を行えるため、特定のキーワードに最適化したい場合にも有効です。
サブディレクトリを使用するケース
サブディレクトリは、メインサイトの一部として新しいコンテンツを追加する場合に適しています。 Googleはサブディレクトリを同じサイトの一部として評価するため、ドメインパワーを分散させずにSEO効果を高められるのがメリットです。
<サブディレクトリを活用すべきケース>
- 企業サイト内にブログを設置する(例:example.com/blog/)
- 商品ページやカテゴリページを追加する(例:example.com/products/)
- FAQやサポートページを統合する(例:example.com/support/)
- 地域ごとのページを管理する(例:example.com/japan/)
サブディレクトリを使用することで、メインサイトの評価が新しいページにも引き継がれ、ドメインパワーを一元化できるため、SEOの観点では有利になります。
 サブディレクトリとサブドメインとは?SEOでの使い分けや違いを解説
サブドメインとサブディレクトリは、ウェブサイト構築時のURL構造に関する選択肢であり、SEOへの影響が異なります。この記事では、それぞれの特徴や使い分け、SEO効果について詳しく解説しています。
サブディレクトリとサブドメインとは?SEOでの使い分けや違いを解説
サブドメインとサブディレクトリは、ウェブサイト構築時のURL構造に関する選択肢であり、SEOへの影響が異なります。この記事では、それぞれの特徴や使い分け、SEO効果について詳しく解説しています。
SEO視点での最適なドメイン構造の選択
SEOの観点から、基本的にはサブディレクトリの使用が推奨されます。 その理由は、Googleがサブディレクトリをメインドメインの一部として評価し、SEO効果を最大限活用できるからです。
<サブドメインとサブディレクトリの比較>
| 項目 | サブドメイン (sub.example.com) | サブディレクトリ (example.com/sub/) |
|---|---|---|
| SEO評価の統合 | 別のサイトとして扱われるため、評価が分散する | メインサイトの評価を引き継ぐためSEOに有利 |
| 管理のしやすさ | 独立した管理が必要 | メインサイトと統一した管理が可能 |
| SEO効果 | ドメインパワーが分散するため、SEO効果が弱まりやすい | 既存のドメインパワーを活用できるため有利 |
| 適した用途 | 異なるコンテンツ・サービス・言語向け | 既存サイトの延長で新しいページを追加 |
<サブディレクトリが推奨される理由>
1.ドメインパワーを集中できる → サイト全体のSEO評価が向上しやすい
2.内部リンクの効果を活用できる → サイト内のページ間でSEO効果を共有
3.検索エンジンがサイトを統一的に評価する → 一貫したSEO戦略を展開しやすい
<サブドメインを選ぶべき特別なケース>
ただし、サブドメインが適している場合もあります。 例えば、企業のコーポレートサイトとは別に、ECサイトやブログを運営する場合や、異なる地域・言語のターゲット向けにサイトを分ける場合です。
また、Googleの公式見解では「サブドメインとサブディレクトリのどちらを選んでもSEOには大きな違いはない」とされていますが、実際の運用では、サブディレクトリのほうがSEO効果を享受しやすい傾向があります。
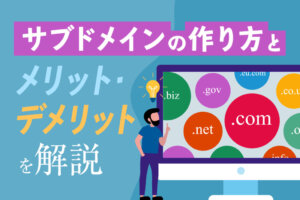 サブドメインとは?メリット・デメリット、作り方を解説
サブドメインは、メインドメインの前に別名を付けることで、特定のコンテンツやサービスを独立して運営できる仕組みです。サブドメインの基本概念、メリット・デメリット、作成手順について詳しく解説しています。
サブドメインとは?メリット・デメリット、作り方を解説
サブドメインは、メインドメインの前に別名を付けることで、特定のコンテンツやサービスを独立して運営できる仕組みです。サブドメインの基本概念、メリット・デメリット、作成手順について詳しく解説しています。
ドメインパワーを強化する3つのコツ

ドメインパワーを高めることで、検索エンジンからの評価が向上し、サイトの検索順位が上がりやすくなります。ここでは、ドメインパワーを強化するための具体的な方法を紹介します。
良質なコンテンツを発信する
検索エンジンは、価値のあるコンテンツを提供するサイトを高く評価します。 ユーザーにとって有益な情報を継続的に発信することで、サイトの信頼性が向上し、検索順位の上昇につながります。特に、専門性が高く、定期的に更新されるコンテンツは、Googleの評価を受けやすくなります。
また、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ作成を行うと、検索エンジンからの評価がより高まり、結果的にドメインパワーの向上につながります。
良質な被リンクを獲得する
被リンクは、他のWebサイトからの評価の証として検索エンジンに認識されます。特に、権威性の高いサイトや関連性のあるサイトからの被リンクは、ドメインパワーの強化に大きく貢献します。
良質な被リンクを獲得するには、以下の方法が有効です。
- 自然にシェアされるコンテンツを作成する(業界のリサーチ記事・統計データ・有益なガイドなど)
- ゲスト投稿(寄稿)を活用し、信頼性の高いサイトからリンクを得る
- SNSやWebメディアでの拡散を促進し、オーガニックにリンクを増やす
ただし、質の低い被リンクやスパムリンクは逆効果となるため、リンクの品質管理も重要です。
 良質な被リンクと低品質な被リンクの特徴と対策とは
被リンクには、サイト評価を高める良質なものと、ペナルティの原因となる低品質なものがあります。本記事では、それぞれの特徴と、低品質な被リンクへの対処法を解説しています。
良質な被リンクと低品質な被リンクの特徴と対策とは
被リンクには、サイト評価を高める良質なものと、ペナルティの原因となる低品質なものがあります。本記事では、それぞれの特徴と、低品質な被リンクへの対処法を解説しています。
サイトを長期的に運営する
ドメインパワーは、一朝一夕で強化できるものではなく、長期的な視点で育てることが重要です。そのためには、以下のSEO戦略を意識することが必要です。
- 長期間運用することを前提に、継続的にサイトを成長させる
- サイト構造を最適化し、内部リンクを活用して評価を高める
- 定期的なSEOメンテナンスを実施し、検索エンジンのアルゴリズムの変化に対応する
これらの施策を継続的に実施することで、サイトの信頼性が高まり、検索エンジンからの評価が安定的に向上します。
 内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説
内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。
内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説
内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。
ドメイン名を決める際の注意点

ドメイン名はWebサイトの「住所」となる重要な要素です。一度決めると簡単に変更できないため、慎重に選ぶ必要があります。 変更するとSEOの評価がリセットされたり、ユーザーがサイトを見つけにくくなったりするリスクがあるため、長期的に運用できるドメイン名を選ぶことが大切です。
ここからはドメイン名を決める際の注意点を解説します。
日本語ドメインの使用を避ける
日本語ドメイン(例:「会社名.日本」「美味しい和食.com」)は、一見わかりやすいように見えますが、SEOや運用の面でデメリットが多いため推奨されません。
特に問題となるのは、URLが「Punycode(ピュニコード)」に変換されることです。例えば、「美味しい和食.com」は「xn--tck5a5c7f0a7c.com」のような英数字のコードに変換されるため、視認性が悪くなり、URLを直接入力しづらくなります。
また、SNSやメールでURLを共有する際に、不自然な文字列になってしまい、クリック率が下がる可能性があります。
さらに、日本語ドメインは海外のユーザーには理解されにくく、グローバル展開を考えている場合には不向きです。日本語入力ができないデバイスではアクセスしづらくなることもあるため、利便性の面でも英字のドメインを選ぶほうが適しています。
SEOの観点でも、日本語ドメインが特別に有利になることはなく、むしろ管理の手間が増えることがデメリットとなります。一般的な英字ドメインを使用するほうが、運用のしやすさや検索エンジンの評価の面で有利になるでしょう。
ドメイン名は一度決めたら変更できない
ドメイン名は基本的に長く使い続けることが前提であり、途中で変更するのは大きなリスクを伴います。特に、検索エンジンの評価やユーザーの認知度に影響を与えるため、慎重な判断が必要です。
ドメイン変更のリスクとして、検索エンジンの評価を失う可能性があります。Googleなどの検索エンジンは、ドメインの歴史や被リンクをもとに評価を行っています。
新しいドメインに変更すると、それまでの評価がリセットされ、検索順位が下がることがあります。また、長年使っていたドメインを変更すると、ユーザーがサイトを見つけにくくなり、アクセス数が減少することもあります。
さらに、外部サイトから獲得した被リンクの影響も薄れる可能性があり、SEOに悪影響を及ぼすことがあります。そのため、ドメイン名を決める際には、サイトの目的やブランドに適した名称を選び、長期的に使用できるかを考えた上で決めることが重要です。
ドメイン名変更にはSEOリスクがある

ドメインを変更すると、SEO評価がリセットされ、検索エンジンの認識が変化することで、検索順位に影響を及ぼす可能性があります。特に、旧ドメインで獲得した被リンクの評価が失われると、新しいドメインではその恩恵を受けられず、検索順位の低下につながることがあります。
また、Googleのインデックスに登録されていた旧ドメインのページが削除されると、一時的に検索結果から消えてしまい、アクセス数の減少を招くことがあります。検索エンジンが新ドメインを適切に認識するまでには時間がかかるため、影響が長期にわたる可能性もあります。
さらに、ドメインパワーのリセットも大きな課題となります。これまで蓄積してきた検索エンジンからの評価がゼロに戻るため、新ドメインでは改めて信頼性を築く必要があり、検索順位の回復までに時間がかかることが考えられます。
 Googleインデックスとは?インデックスされない場合の登録方法も解説
Googleインデックスとは、ウェブページがGoogleのデータベースに登録され検索結果に表示される状態を指します。この記事では、仕組みやインデックスされない場合の対処法について解説しています。
Googleインデックスとは?インデックスされない場合の登録方法も解説
Googleインデックスとは、ウェブページがGoogleのデータベースに登録され検索結果に表示される状態を指します。この記事では、仕組みやインデックスされない場合の対処法について解説しています。
SEOへの影響を抑えるドメイン変更の方法

ドメイン変更によるSEOへの影響を抑えるには、以下の手順を確実に実施することが重要です。
1. 301リダイレクトを設定する
「301リダイレクト」を適用し、旧ドメインのページを新ドメインに転送します。これにより、Googleが旧ドメインの評価を新ドメインへ移行しやすくなります。
例:
https://olddomain.com/page1
→ https://newdomain.com/page1
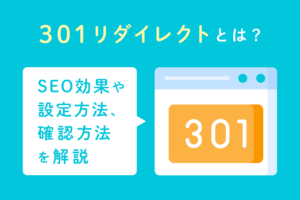 301リダイレクトとは?SEOへの影響とやり方を解説
301リダイレクトは、URLを恒久的に変更する際に使用され、旧ページから新ページへSEO評価やアクセスを引き継ぐ重要な手法です。この記事では、その設定方法や効果、注意点を詳しく解説しています。
301リダイレクトとは?SEOへの影響とやり方を解説
301リダイレクトは、URLを恒久的に変更する際に使用され、旧ページから新ページへSEO評価やアクセスを引き継ぐ重要な手法です。この記事では、その設定方法や効果、注意点を詳しく解説しています。
2. Google Search Consoleで「アドレス変更」を申請
Google Search Consoleの「アドレス変更ツール」を活用し、新ドメインへの移行をGoogleに通知します。これにより、検索エンジンのインデックス更新が早まり、順位の下落を防ぐことができます。
 Googleサーチコンソールとは?使い方と登録方法や設定を解説
Webサイトの集客状況を分析する際にGoogleアナリティクスと同じくらい役立つのがGoogleサーチコンソールです。サーチコンソールへの登録方法やGoogleアナリティクスとの連携方法について、わかりやすく解説します。
Googleサーチコンソールとは?使い方と登録方法や設定を解説
Webサイトの集客状況を分析する際にGoogleアナリティクスと同じくらい役立つのがGoogleサーチコンソールです。サーチコンソールへの登録方法やGoogleアナリティクスとの連携方法について、わかりやすく解説します。
3. サイトマップ(XML)の更新・送信
新ドメインのサイトマップを作成し、Google Search Consoleへ送信します。これにより、検索エンジンが新しいURLを迅速に認識できるようになります。
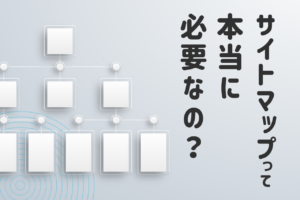 サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果
Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。
サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果
Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。
4. 内部リンクを新ドメインに変更
旧ドメインのURLが残っていると、不要なリダイレクトが発生し、SEOに悪影響を及ぼします。 そのため、すべての内部リンクを新ドメインのURLに更新する必要があります。
5. 被リンクの移行を依頼
高品質な被リンクを持つサイトの管理者に連絡し、新ドメインのURLへ変更してもらう方法です。 これは手間がかかりますが、SEOへのネガティブな影響を軽減することにつながります。
6. SNS・メール・広告のURLを更新
SNSプロフィールやメール署名、広告のURLを新ドメインに変更し、ユーザーがスムーズに移行できるようにします。
7. 検索順位を定期的にチェック
Google Search ConsoleやGoogle Analyticsを活用し、トラフィックや検索順位の変動を監視します。 大幅な順位低下が見られた場合は、リダイレクトやサイトマップの設定を再確認しましょう。
SEOを意識したドメイン名を選び、効果的に運用しよう

ドメイン名は、Webサイトの認知度やユーザーの印象に関わる重要な要素であり、SEOにも間接的に影響を与える可能性があります。信頼感があり、覚えやすいドメインを選ぶことで、クリック率やアクセスのしやすさにもつながります。
ドメイン名を決める際は、短くて覚えやすく、ブランドやサービスと関連性のある名称を意識しましょう。また、新規ドメインと中古ドメインの特徴を理解し、運用方針に適した選択を行う必要があります。
さらに、ドメインパワーを強化するには、良質なコンテンツの発信や被リンクの獲得が不可欠です。サブドメインとサブディレクトリの適切な使い分けや、ドメイン変更時の影響を考慮した運用も求められます。
長期的な視点でSEO対策を行い、検索エンジンとユーザー双方に評価されるWebサイトを構築していきましょう。
<無料>資料ダウンロード
【プロにお任せ】SEOコンサルティング
見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決