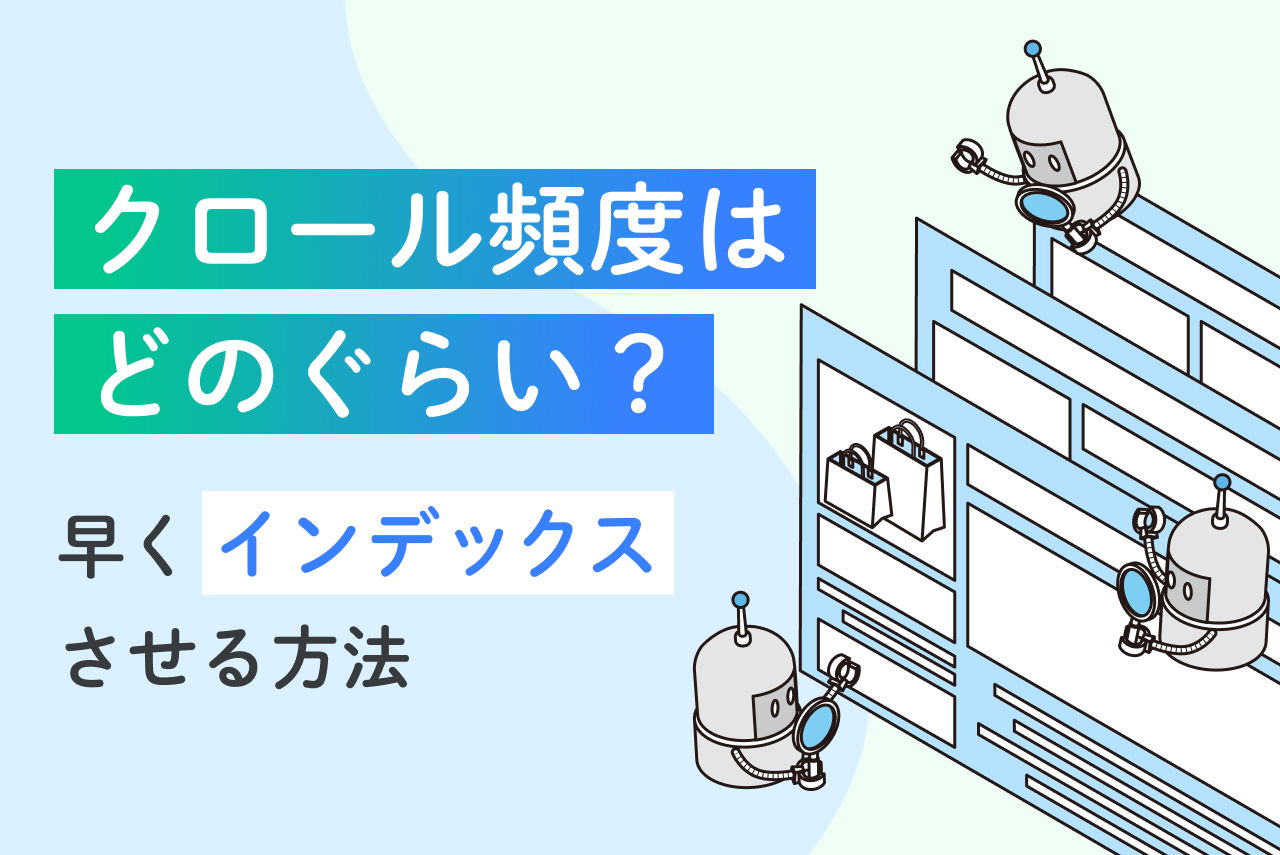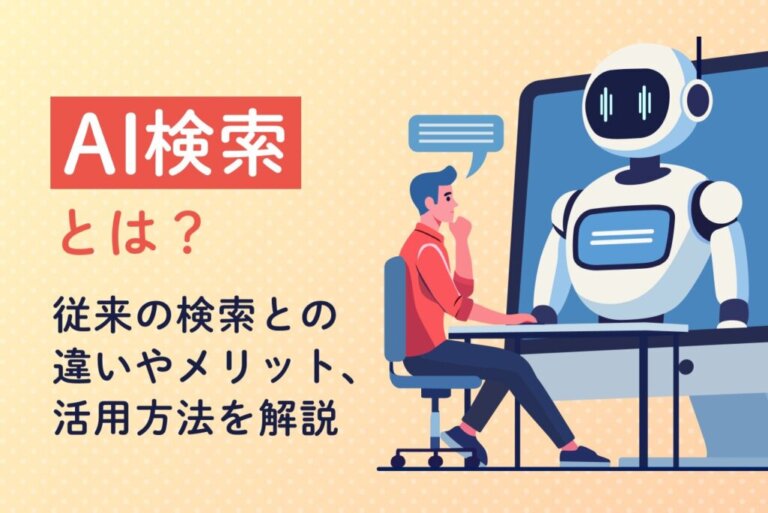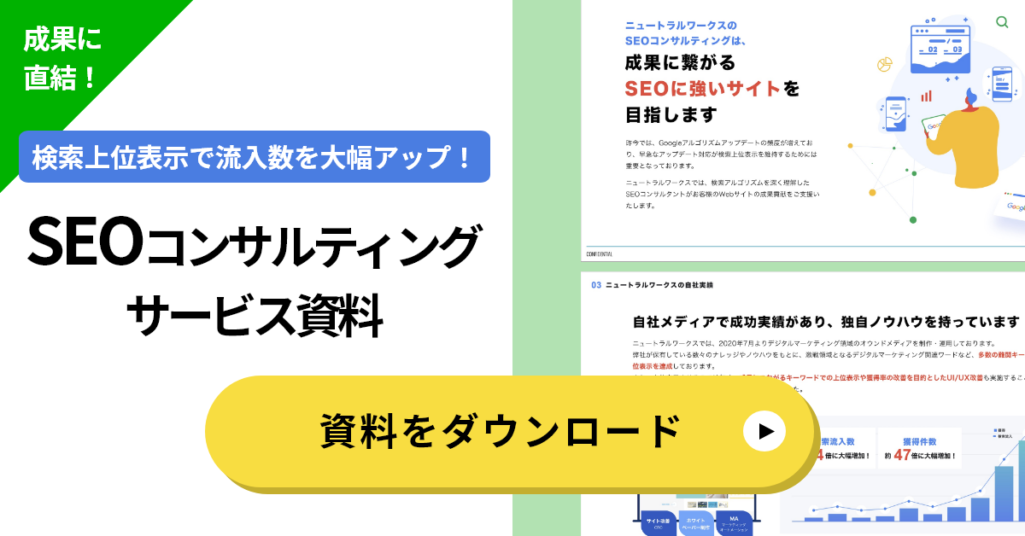この記事のポイント
この記事のポイントは以下です。
-
Googleのクロール頻度とは?どのように決まるのですか?
-
クロール頻度はGooglebotがサイトを巡回する頻度で、更新頻度やコンテンツの質、リンク構造、サーバーの応答速度などにより決まります。
-
自社のサイトがどのくらいクロールされているか調べるには?
-
Googleサーチコンソールの「クロールの統計情報」で巡回頻度や応答時間を確認できます。URL検査ツールで個別ページの状況もチェックでき、アクセスログではクローラーの訪問履歴が分かります。
-
Googleのクロール頻度を上げるためにできることは?
-
クロール頻度を高めるには、robots.txtで不要なURLを除外し、サーバー応答速度の改善、XMLサイトマップの最適化、内部・外部リンクの強化、高品質なコンテンツ提供、AMP導入などの施策が有効です。
Googleのクロール頻度は検索順位や可視性に影響を与え、新しいコンテンツが素早くインデックスされることで、SEO効果の向上や競合との差別化が可能になります。しかし、「なかなかインデックスされない」「クロール頻度を上げたい」と悩む方も多いのではないでしょうか?
本記事では、クロール頻度を高める具体的な方法として、サイトマップや内部リンクの最適化などの実践的な対策を解説し、検索エンジンに迅速に認識されるためのポイントを紹介します。
<無料>資料ダウンロード
【プロにお任せ】SEOコンサルティング
見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決
目次
Googleのクロール頻度とは?

クロール頻度とは、Googleのクローラー(Googlebotなど)がWebサイトを巡回する頻度を指します。頻度が高いほど、新しいコンテンツや更新内容が素早く検索エンジンに認識され、インデックスへの反映も早くなります。
クロール頻度は、サイトの更新頻度やコンテンツの質、内部リンク構造、外部リンクの有無、サーバーの応答速度など、複数の要因によって決まります。Googleは、価値があると判断したサイトを優先的に巡回するため、クロール頻度の最適化はSEOにおいて重要な施策です。
一方で、頻度が極端に低い場合は、新しいページがなかなか検索結果に反映されず、機会損失につながる可能性があります。自身のサイトがどれくらいクロールされているかは、Googleサーチコンソールの「クロールの統計情報」などで確認できます。
 Googleインデックスとは?インデックスされない場合の登録方法も解説
Googleインデックスとは、ウェブページがGoogleのデータベースに登録され検索結果に表示される状態を指します。この記事では、仕組みやインデックスされない場合の対処法について解説しています。
Googleインデックスとは?インデックスされない場合の登録方法も解説
Googleインデックスとは、ウェブページがGoogleのデータベースに登録され検索結果に表示される状態を指します。この記事では、仕組みやインデックスされない場合の対処法について解説しています。
Googleのクロール頻度の決定要因

GoogleのクローラーがWebサイトをどれくらいの頻度で巡回するかは、いくつかの要因によって決まります。特に「クロールバジェット」と「クロールの必要性の有無」は重要な判断基準です。これらの仕組みを理解することで、より効果的なSEO対策が可能になります。
クロールバジェット
クロールバジェットとは、Googleが1つのWebサイトに対して一定期間内にクロールできるページ数の上限を指します。Googleはサーバーへの負荷を避けるため、サイトごとにクロール速度を自動的に調整しています。
このバジェットは、主に以下の2つの要因によって変動します。
- サイトの応答状況:
サイトが高速かつ安定して応答している場合、Googleはクロール上限を引き上げます。 一方、エラーが頻発したり応答が遅かったりすると、クロール頻度が下がります。 - Googleサーチコンソールでの設定:
Webサイト所有者は、Googleサーチコンソール上でクロール上限を制限できます。 ただし、設定値を高くしても、それだけでクロールが増えるわけではありません。
クロールバジェットが多いサイトほど、多くのページが巡回されやすくなり、結果としてインデックスのスピード向上やSEO効果の改善が期待できます。
 クロールバジェットの詳細と最適化方法まとめ
クロールバジェットの詳細と最適化方法を解説した記事です。クロールバジェットの基本概念からその最適化方法までを詳しく解説し、サイトの検索パフォーマンスを最大化するための具体的な対策を紹介しています。
クロールバジェットの詳細と最適化方法まとめ
クロールバジェットの詳細と最適化方法を解説した記事です。クロールバジェットの基本概念からその最適化方法までを詳しく解説し、サイトの検索パフォーマンスを最大化するための具体的な対策を紹介しています。
クロールの必要性の有無
クロールバジェットが十分にあっても、Googleが「クロールする必要がない」と判断したページは、巡回頻度が下がります。Googleは限られたリソースを有効活用するため、重要性の低いページへのクロールは抑制する傾向があります。
クロール頻度に影響する要素としては、アクセス数や運営期間の長さなどが挙げられます。信頼性が高く、ユーザーの関心を集めているサイトは、より頻繁にクロールされます。
一方で、更新頻度が低かったり、コンテンツの質が低かったりするサイトは、クロールの優先度が下がります。
新規サイトについても、Googleからの評価が定まるまではクロールが少なく、インデックスまでに時間がかかる傾向があります。定期的な更新と質の高い情報提供が、クロール頻度の向上に不可欠です。
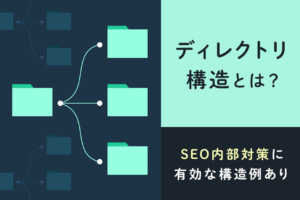 ディレクトリ構造とは?SEO内部対策に有効な構造例あり
ディレクトリ構造の基本的な仕組みを解説し、SEO内部対策に有効な具体例を紹介しています。検索エンジンに評価されやすい設計方法やその効果、ユーザー体験を向上させるポイントを詳しく学べる内容です。
ディレクトリ構造とは?SEO内部対策に有効な構造例あり
ディレクトリ構造の基本的な仕組みを解説し、SEO内部対策に有効な具体例を紹介しています。検索エンジンに評価されやすい設計方法やその効果、ユーザー体験を向上させるポイントを詳しく学べる内容です。
Googleのクロール頻度の確認方法

クロール頻度を確認する方法について、確認手順などを紹介します。
Googleサーチコンソールの活用
Googleサーチコンソールを使うと、サイトのクロール状況やクローラーの動き、エラーの発生状況などを可視化できます。中でも、「クロールの統計情報」や「URL検査ツール」などの機能を活用すれば、クロール頻度やインデックス状況を多角的に把握でき、検索パフォーマンスの改善に役立てることが可能です。
以下では、それぞれの機能の特徴と活用方法を紹介します。
クロールの統計情報
「クロールの統計情報」では、Googleクローラーがどの程度サイトを巡回しているかを確認できます。手順は以下のとおりです。
クロールの統計情報の確認手順:
1.Googleサーチコンソールにログインする
2.対象のプロパティを選択する
3.左側メニューの「設定」をクリック
4.「クロールの統計情報」を選択する
この画面で確認できる代表的な情報は以下のとおりです。
- 1日あたりのクロール済みページ数
- サーバー応答時間の推移
- エラー発生頻度や種類
クロールの統計情報の解析
「クロールの統計情報」には、以下のような詳細データが含まれます。
- クロールリクエスト数
- レスポンスコードの分布
- クロールされたページ数
- クロール成功率 など
各項目の意味を正しく理解することで、サイト運営への影響を明確に把握できます。
例えば、クロールリクエスト数の増加は、Googleクローラーがサイトに対してより積極的に巡回しているサインと考えられます。一方で、レスポンスコードのエラーが多い場合は、クローラーがページにアクセスできていないことを示し、検索評価やユーザビリティに悪影響を及ぼす可能性があります。
定期的にレポートを確認し、傾向を把握・改善につなげましょう。
URL検査ツール
URL検査ツールを使えば、特定のページがインデックス登録されているか、クロール済みかを個別に確認できます。クロールエラーが発生している場合は、原因の特定と修正により、クローラーが円滑に巡回できる状態を維持しやすくなります。
サーバーのアクセスログの分析
サーバーのアクセスログを分析することで、Googleなどのクローラーがいつ・どのページにアクセスしているかを詳細に把握できます。
ユーザーエージェントやIPアドレスを確認すれば、どのクローラーがどれくらいの頻度で訪問しているかを特定できます。また、ログデータを活用して、以下のような分析が可能です。
- 時間帯別のクロール頻度
- ページ別のクロール状況
- クロールの偏りや集中傾向
こうした分析により、クローリングのピーク時間や優先ページを可視化でき、クロール戦略の見直しや最適化に役立てることができます。
 クローリングとは?スクレイピングとの違いや検索エンジンに重要な対策方法を解説
クローリングは、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを巡回し情報を収集するプロセスです。この記事では、基本概念、スクレイピングとの違い、検索エンジン最適化のための対策方法について解説しています。
クローリングとは?スクレイピングとの違いや検索エンジンに重要な対策方法を解説
クローリングは、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを巡回し情報を収集するプロセスです。この記事では、基本概念、スクレイピングとの違い、検索エンジン最適化のための対策方法について解説しています。
Googleのクロール頻度を上げる7つの方法
GoogleのクローラーがWebページを巡回する頻度は、インデックスの速さやSEO効果に直結します。クロール頻度が高いほど、新しい情報が早く検索結果に反映されやすくなり、検索流入のチャンスも広がります。
ここでは、クロール頻度に影響を与える要因や確認方法、そしてクロールを促進するための7つの具体的な方法を紹介します。
クロール頻度に影響する主な要因
まずは、Googleがサイトをどれくらいの頻度でクロールするかに影響する要素を把握しておきましょう。これらの要因を改善することが、クロール頻度の向上につながります。
- クロールされるURLの質と数:
不要なページが多いと、クローラーが分散され、重要なページの巡回が遅れる恐れがあります。 - サーバーの応答速度:
サイトの表示が遅いと、クローラーが一度に巡回できるページ数が減り、巡回頻度が下がります。 - サイト更新の頻度や規模:
定期的な更新があると、Googleはサイトを「活動的」と判断し、クロール回数を増やす傾向があります。 - 外部リンクの質と量:
他サイトから多くのリンクがあるページは重要とみなされ、優先的にクロールされます。
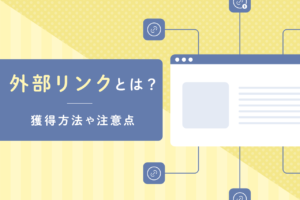 外部リンクとは?SEO対策効果と外部リンク獲得方法を解説
この記事では、外部リンクに関する事柄を紹介します。獲得方法のみならず、混在しやすい「内部リンク」「サイテーション」との違いや、取り扱ううえで注意すべきポイントなど、外部リンクについてより深く理解できるように解説します。
外部リンクとは?SEO対策効果と外部リンク獲得方法を解説
この記事では、外部リンクに関する事柄を紹介します。獲得方法のみならず、混在しやすい「内部リンク」「サイテーション」との違いや、取り扱ううえで注意すべきポイントなど、外部リンクについてより深く理解できるように解説します。
クロール状況の確認方法
現在のクロール状況を把握することで、問題点や改善の余地が見えてきます。Googleサーチコンソールを使えば、以下のような情報が確認できます。
- クロールの統計情報:
「設定」>「クロールの統計情報」で、1日あたりのクロール数やサーバー応答時間などが確認できます。 - URLごとのクロール状況:
「URL検査ツール」で、特定のURLがクロール・インデックスされているかを個別に確認できます。
これらを活用し、どのページがクロールされていないか、どこに技術的な問題があるのかを把握しておきましょう。
クロール頻度を上げる具体的な方法
ここからは、クロール頻度を高めるための実践的な施策を紹介します。それぞれの方法は単体でも効果がありますが、複数を組み合わせて実施することで、より高い効果が期待できます。
1.クロールされるURLを厳選する(robots.txtの活用)
クローラーが不要なページまで巡回してしまうと、重要なページへのクロールが遅れる原因になります。これを防ぐために、robots.txtを活用してクロール対象を制限することが効果的です。
管理画面や検索結果ページなど、インデックスの必要がないページは Disallow指定で除外しましょう。設定ミスによるクロール漏れを防ぐため、作成後はGoogleサーチコンソールでの確認も忘れずに行いましょう。
 robots txtとは?書き方と設置方法、noindexとの違いを解説
本記事では、robots.txtについて、役割やnoindexとの違い、クローラーの種類や記述方法まで詳しく解説しています。robots.txtを使ってクローラーをうまく制御するためにも、正しい知識を持って活用しましょう。
robots txtとは?書き方と設置方法、noindexとの違いを解説
本記事では、robots.txtについて、役割やnoindexとの違い、クローラーの種類や記述方法まで詳しく解説しています。robots.txtを使ってクローラーをうまく制御するためにも、正しい知識を持って活用しましょう。
2.サーバーの応答速度を上げる
クローラーは、応答速度の遅いサイトを避ける傾向があります。快適な巡回環境を整えることは、クロール効率の改善につながります。
キャッシュ機能の導入、CDNの利用、サーバースペックの見直しなどが代表的な改善策です。また、Google PageSpeed Insightsなどのツールで現状を可視化し、定期的にパフォーマンスをチェックすることも重要です。
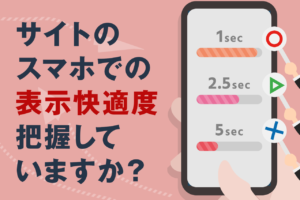 ページスピードインサイト(Google PageSpeed Insights)の使い方!見方や改善方法を解説
Google PageSpeed Insightsは、ページ速度を診断し、改善提案を提示する無料ツールです。この記事では、使い方や結果の見方、速度向上の方法を詳しく解説しています。
ページスピードインサイト(Google PageSpeed Insights)の使い方!見方や改善方法を解説
Google PageSpeed Insightsは、ページ速度を診断し、改善提案を提示する無料ツールです。この記事では、使い方や結果の見方、速度向上の方法を詳しく解説しています。
3.サイトマップを最適化・送信する
XMLサイトマップは、Googleにサイト構造を伝える重要なファイルです。主要ページのURLを網羅し、定期的に更新することで、新しい情報が素早く認識されやすくなります。
Googleサーチコンソールで「サイトマップ」セクションから送信するだけで、クローラーが最新のURLを効率よく取得できます。自動更新ツールを使えば、運用の手間も軽減されます。
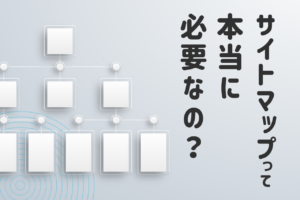 サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果
Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。
サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果
Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。
4.内部リンクと外部リンクを最適化する
リンク構造は、クローラーの巡回ルートに大きく影響します。内部リンクの整理や、重要ページへのリンク集中は、クロールの優先度を高める有効な手段です。
さらに、外部サイトからの良質なリンク(被リンク)は、サイト全体の信頼性を高め、Googleにとって「巡回すべきサイト」と判断されやすくなります。
 内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説
内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。
内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説
内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。
5.コンテンツの質を高める
検索エンジンは、ユーザーにとって有益な情報を優先的にクロールします。質の高いコンテンツは、クローラーからの注目度が高まり、更新頻度も高く維持しやすくなります。
情報の網羅性や独自性、ユーザーニーズとの整合性を意識し、定期的に見直し・更新することが、クロール頻度を上げるうえで欠かせません。
 良質なコンテンツとは?SEOにおける要件を解説
SEOで重要な「良質なコンテンツ」とは、ユーザーのニーズに応え、正確で価値ある情報を提供するものです。この記事では、オリジナリティや読みやすさ、最新性などの具体的な要件を詳しく解説しています。
良質なコンテンツとは?SEOにおける要件を解説
SEOで重要な「良質なコンテンツ」とは、ユーザーのニーズに応え、正確で価値ある情報を提供するものです。この記事では、オリジナリティや読みやすさ、最新性などの具体的な要件を詳しく解説しています。
6.AMPページを活用する
AMP(Accelerated Mobile Pages)は、高速表示を実現するモバイル向けページ仕様です。軽量で構造が明確なため、クロールしやすく、インデックス速度が向上する傾向があります。
導入の際は、AMPの技術要件を満たすようHTMLやCSSの制約に注意しつつ、UXを損なわないよう慎重に設計しましょう。
 AMP(アンプ)とは?UI/UX改善やSEO効果などメリット・デメリットを解説
AMP(アンプ)を導入するWebサイトが増えてきて、そろそろ導入したいと考えている方へ、AMPを導入するメリット、デメリット、そして導入方法についてまとめました。
AMP(アンプ)とは?UI/UX改善やSEO効果などメリット・デメリットを解説
AMP(アンプ)を導入するWebサイトが増えてきて、そろそろ導入したいと考えている方へ、AMPを導入するメリット、デメリット、そして導入方法についてまとめました。
7.クロールリクエストを送信する
Googleサーチコンソールの「URL検査ツール」を使えば、特定ページのクロール・インデックス登録を手動でリクエストできます。すぐに反映させたい重要な変更がある場合に有効です。
次のようなタイミングでは、クロールリクエストの活用によって効果が期待できます。
- 新規コンテンツの公開直後
- 既存ページを大幅にリライトした後
- 重要なイベントやキャンペーンページの公開後
ただし、頻繁な送信はスパムとみなされる恐れがあるため、必要なときに限定して行うようにしましょう。
 スパムとは?インスタやツイッターで被害を受けた場合の対処法も紹介
スパムの定義や種類、InstagramやTwitterでの被害事例、そして被害を受けた場合の対処法について詳しく解説しています。ソーシャルメディア利用時の安全対策に役立つ情報を提供しています。
スパムとは?インスタやツイッターで被害を受けた場合の対処法も紹介
スパムの定義や種類、InstagramやTwitterでの被害事例、そして被害を受けた場合の対処法について詳しく解説しています。ソーシャルメディア利用時の安全対策に役立つ情報を提供しています。
Googleにインデックスされない原因と対処法
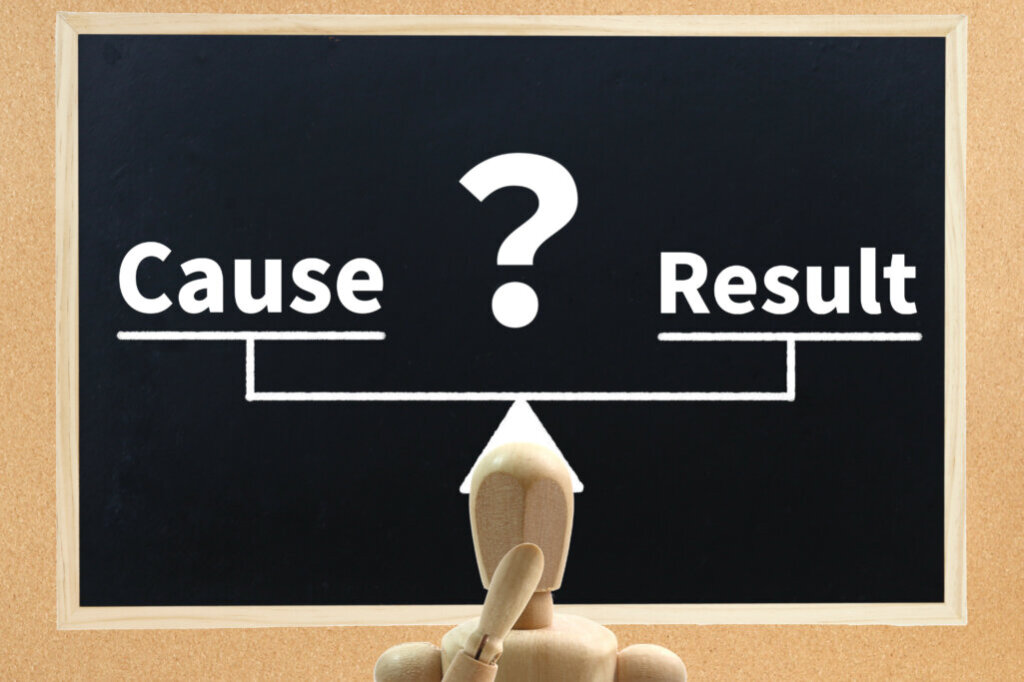
WebページがGoogleにインデックスされない場合は、「クロールされていない」と「クロールされたがインデックスされない」の大きく2つの原因に分けられます。
まず、クロール自体が行われていないケースでは、robots.txtによるブロック、URLの正規化ミス、内部リンクの不足などが主な原因です。Googleサーチコンソールでサイトマップが未送信になっていると、クロールの遅れを招くこともあります。
一方、クロールはされているにもかかわらずインデックスに登録されない場合は、重複コンテンツや品質の低いページと判断されている可能性があります。また、Googleのガイドラインに違反する自動生成コンテンツや隠しテキストなどがあると、インデックス対象から除外されることがあります。
対策としては、サーチコンソールでクロール状況を確認し、ブロックや設定ミスを修正するのが基本です。そのうえで、コンテンツの独自性やユーザーの利便性を高める工夫を行い、インデックスされやすい状態を整えましょう。
 重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説
重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。
重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説
重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。
Googleのクロール頻度最適化でSEO効果を高めよう

Googleのクロール頻度は、検索順位や可視性に大きく影響する重要な要素です。クロールが頻繁に行われると、新しいコンテンツが素早くインデックスされ、SEO効果やオーガニック検索からの流入増加につながります。
クロール頻度を高めるには、サイトの更新頻度を維持し、高品質なコンテンツを提供することが重要です。また、XMLサイトマップの最適化や内部リンクの強化、AMPの活用などの技術的な対策を行うことで、クローラーの巡回が効率化され、インデックス速度が向上します。
さらに、Googleサーチコンソールでクロール状況を確認し、サーバーのレスポンス速度を最適化することも有効です。クロールとインデックスの関係を理解し、データ分析を活用しながらSEO戦略を最適化していきましょう。
<無料>資料ダウンロード
【プロにお任せ】SEOコンサルティング
見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決