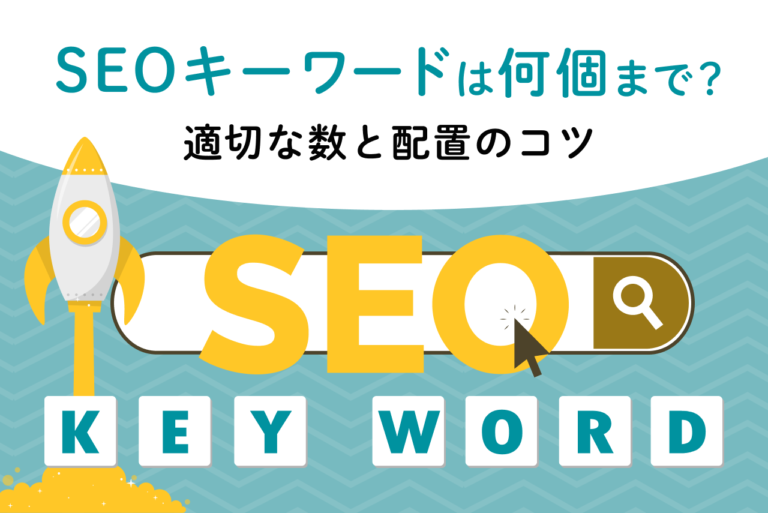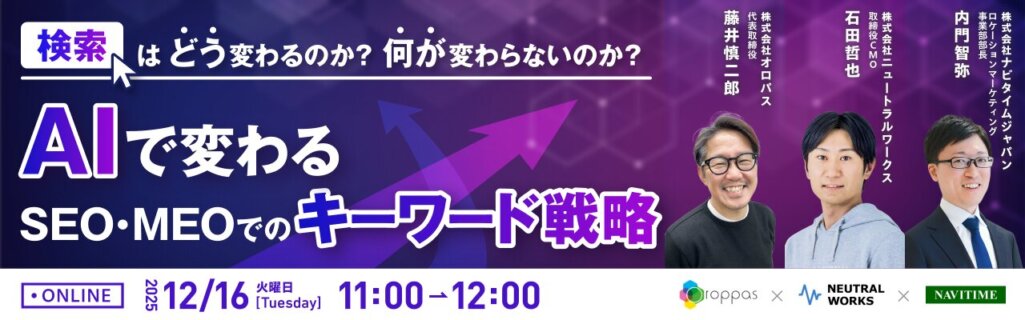この記事のポイント
この記事のポイントは以下です。
-
更新頻度はSEOに影響する?
-
はい、影響します。ただし、単に頻繁に更新すればよいわけではありません。検索エンジンは質の高い更新を重視します。更新頻度はクロールやユーザーの信頼性にも関わるため、内容の充実と定期的な見直しがポイントです。
-
どれくらいの頻度でコンテンツを更新すればよい?
-
一般的には、新規記事は週1〜2本、既存記事のリライトは3〜6ヶ月に1回が目安とされています。ただし、ジャンルや社内リソースによって最適な頻度は異なります。無理なく継続できるペースで、質の高い記事を安定的に公開することが重要です。
-
毎日更新すればSEOで有利になる?
-
必ずしもそうとは限りません。更新頻度だけで評価されるのではなく、ユーザーの検索意図を満たし、有益な情報を提供しているかがポイントです。内容が薄い記事を量産すると、逆にサイト評価が下がる可能性もあるため注意が必要です。
「SEO効果を上げるには、どのくらいの頻度で更新すればよいのか」「更新しないと順位が下がるのでは?」といった疑問を抱える方は多いでしょう。
実際には、単に更新回数を増やすだけで順位が上がるとは限らず、コンテンツの質やテーマ、ジャンル、運用体制によって最適な更新頻度は異なります。また、更新作業を継続するには、計画的な運用やリソース管理も不可欠です。
この記事では、SEOに効果的な更新頻度の考え方や目安、頻度を保つための工夫、更新時に注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。
<無料>資料ダウンロード
【プロにお任せ】SEOコンサルティング
見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決
目次
更新頻度はSEOに直接影響しない

SEOにおいて、ページの更新頻度が検索順位に直接的な影響を与えることは基本的にありません。検索エンジンは、更新されたという事実よりも、その内容がユーザーにとって有益かどうかを重視して評価します。
そのため、日付の変更や意味のない加筆といった表面的な更新では、評価につながらないどころか、「検索順位を操作しようとしている」と判断され、逆効果になる可能性もあります。
ここからは、SEO評価に影響を与える要素として重要な「コンテンツの質」と、更新頻度が評価に寄与するケースについて解説します。
コンテンツの質こそが評価の鍵
Googleが最も重視しているのは、「ユーザーの検索意図をどれだけ満たしているか」という点です。そのため、SEOにおいてはコンテンツの質を高めることが最も重要な施策といえます。
たとえば、既存のページに対して新しい情報を加えたり、内容を見直して構成を整理したりすることで、ユーザーにとっての利便性が向上します。このようなユーザー体験を意識した更新は、検索エンジンからも評価されやすくなります。
一方で、検索順位を上げるためだけに表面的な修正を繰り返すと、かえって評価が下がる可能性もあるため注意が必要です。本質的な価値提供につながる内容の更新こそが、SEOに効果的に働くのです。
更新頻度が間接的に影響するケース
更新頻度そのものが検索順位に直接影響することはありませんが、一定の条件下では間接的にプラスに作用するケースもあります。以下のような状況では、定期的な更新が評価につながる可能性があります。
- 情報の鮮度が求められるジャンル(例:ニュース、法改正、医療・健康分野など)
内容がすぐに古くなるテーマでは、更新が信頼性の証となり、ユーザーにも検索エンジンにもよい印象を与えます。 - サイトが継続的に運用されているシグナルとして機能する場合
定期的に更新されているサイトは「放置されていない」と認識されやすく、Googleのクローラーに頻繁に巡回されやすくなります。 - 既存ページの加筆・修正による精度向上
コンテンツの内容を現状に合わせて見直すことで、検索意図へのマッチ度が上がり、順位向上につながることがあります。
このように、更新頻度そのものよりも、「どう更新するか」「何のために更新するか」が問われているという点を意識することが大切です。
SEOでは更新頻度よりコンテンツの質が重要

SEO対策においては、単に更新頻度が高いだけではコンテンツの評価は高まりません。内容が薄く、ユーザーにとって価値の低い情報を頻繁に追加しても、検索順位の向上にはつながらず、場合によっては逆効果となることもあります。
Googleが導入している「Helpful Content System」では、ユーザーにとって本当に役立つかどうかが評価の基準とされています。検索エンジン向けに調整された内容ではなく、実際のユーザーの課題を解決するコンテンツを継続的に提供できているかどうかが、重要なポイントです。
また、検索順位にはユーザー体験(UX)も大きく影響します。長期間更新されていないページは、「情報が古いのではないか」という不信感を与えるおそれがあります。一方で、最新の情報が反映されたページはユーザーの信頼を得やすく、結果として滞在時間や回遊率の向上にもつながります。
このように、SEOで成果を出すには「更新頻度そのもの」よりも、「質の高い情報を継続して届けること」が本質的に重要です。ユーザーの信頼を得ることこそが、検索エンジンからの高評価にも直結します。
参考:A guide to Google Search ranking systems
有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成
 UI/UXとは?意味と違いをわかりやすく解説
この記事では、UI/UXのデザインに焦点をあてて解説します。近年競合サイトとの差別化を図るために、「UI」および「UX」が重要視されています。その理由やデザインする際のポイントなど、初めての方でも「UI」と「UX」について理解できるように紹介します。
UI/UXとは?意味と違いをわかりやすく解説
この記事では、UI/UXのデザインに焦点をあてて解説します。近年競合サイトとの差別化を図るために、「UI」および「UX」が重要視されています。その理由やデザインする際のポイントなど、初めての方でも「UI」と「UX」について理解できるように紹介します。
SEO対策で更新頻度が重要視されるケース

Googleは検索キーワードの特性に応じて、情報に「新しさ」がどの程度求められているかを判断しています。特に、次のような変化の早い分野では、新しい情報が優先的に評価されやすくなります。
- 時事ニュースや速報性のある情報
- 季節ごとのイベントや特集
- 流行中の商品・サービス、話題性のあるテーマ
- 技術や制度などの変更が頻繁な分野
こうしたジャンルでは、素早く情報を更新し、トレンドに対応する姿勢がSEO上でも有利に働きます。一方で、歴史や学術などの普遍的なテーマでは、頻繁な更新は不要であり、正確性や網羅性が重視されます。
つまり、コンテンツのテーマや検索意図に応じて、更新頻度の重要度は変わるということです。検索ユーザーが求めている「情報の鮮度」に合った運用方針を定めることが、SEO効果を高めるポイントとなります。
SEOに効果的な更新頻度の目安

検索順位を高めるためには、コンテンツの更新が欠かせません。ただし、単に更新頻度を上げるだけでなく、新規記事の公開と既存記事のリライトをバランスよく行うことが重要です。
自社のジャンルや運用体制に合わせて最適な更新ペースを見極めることで、無理なくSEO効果を高めることができます。
ここでは、それぞれの更新施策における具体的な頻度の目安とポイントを解説します。
新規記事の公開
新規記事の公開は、サイト全体の情報量を増やし、SEO評価を高めるうえで重要な施策です。一般的には、週1〜2回のペースで更新するのが理想とされており、特に競合の多いジャンルでは、一定の頻度を保つことでGoogleに「アクティブで成長中のサイト」と認識されやすくなります。
ただし、リソースに余裕がない場合は、月2〜4本程度の更新でも問題ないでしょう。重要なのは、無理のない範囲で継続することと、内容の質を落とさないことです。
トピックの優先順位をつけ、事前に計画を立てたうえで新規記事を公開することで、SEO効果を最大化できるでしょう。
既存記事のリライト
既存記事のリライト(内容の見直し・修正)は、検索順位の維持や再浮上を図るために欠かせない施策です。一般的な目安としては、3〜6ヶ月に1回の頻度で、アクセス数や検索順位の変動を確認しながら見直すのが理想です。
特に、情報が古くなりやすい分野や、検索順位が落ちてきた記事については、早めに対応することで機会損失を防げます。タイトルや見出し、本文の表現の見直しに加え、図表の更新や最新情報の追加も重要です。
また、ページに「最終更新日」を明記することで、検索エンジンにもユーザーにもコンテンツの鮮度をアピールできます。定期的なリライトは、コンテンツの信頼性を高め、サイト全体のSEO評価向上にもつながります。
 リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説
SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。
リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説
SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。
自社サイトに最適な更新頻度の決め方

最適な更新頻度は、「頻繁に更新すればよい」という単純な話ではありません。検索意図や競合状況、ユーザー行動、ビジネス目標、運用体制など、複数の要素を総合的に考慮して判断する必要があります。以下は、更新頻度を見極めるうえで有効な5つの視点です。
| 確認ポイント | 内容の概要 |
|---|---|
| 1. 検索クエリの鮮度ニーズ | トレンド性や時事性が高いキーワードでは、情報の新しさが評価されやすく、頻繁な更新が求められます。一方で、歴史や科学など普遍的なテーマでは、正確性や網羅性が重視されます。 |
| 2. 競合ページの更新頻度 | 競合ページの更新タイミングや内容の変化を把握することで、上回る情報鮮度を保つ戦略が立てやすくなります。Web Archive や順位変動の定点観測も有効です。 |
| 3. ユーザーの訪問頻度 | 再訪頻度の高いユーザーが多い場合、定期的な更新が期待値に応え、エンゲージメント向上につながります。訪問間隔に応じた更新計画が理想です。 |
| 4. ビジネス目標との整合性 | PV・CV・収益といった指標から逆算して、更新頻度を設計することも重要です。広告型やリード獲得型など、事業モデルに応じた調整が求められます。 |
| 5. 運用リソースとのバランス | 現実的な体制で継続可能な範囲に収めることが大前提です。無理な更新体制は品質維持を難しくし、長期的には成果に結びつきにくくなります。 |
このように、各要素を総合的に判断し、自社に合った現実的かつ戦略的な更新方針を設計することが、SEO効果を最大化するうえで重要です。
 CV(コンバージョン)とは?意味やCVRを上げる方法を解説
コンバージョン(CV)は、Webサイト上での成果を指し、資料請求や会員登録などが該当します。この記事では、CVの意味やCVR(コンバージョン率)を向上させる方法を解説しています。
CV(コンバージョン)とは?意味やCVRを上げる方法を解説
コンバージョン(CV)は、Webサイト上での成果を指し、資料請求や会員登録などが該当します。この記事では、CVの意味やCVR(コンバージョン率)を向上させる方法を解説しています。
SEOコンテンツを更新する際の3つの注意点

コンテンツを更新すれば必ずしもSEOに効果が出るとは限りません。内容や方法を誤ると、かえって検索順位を落とすリスクもあります。ここでは、更新時に注意すべきポイントを具体的に解説します。
注意点1:低品質記事はリライトもしくは非公開にする
過去に公開した記事の中には、現在のSEO評価基準に照らすと「低品質」と見なされるものが含まれている可能性があります。これらを放置しておくと、サイト全体の評価を下げるリスクがあるため、定期的な棚卸しと対応が必要です。
ただし、「古い記事=SEOに悪影響」と一概に判断するのは適切ではありません。情報が古くても、内容が普遍的で今でも有用な記事であれば、検索順位を維持し続け、引き続きSEOに貢献するケースもあります。
重要なのは、古い記事を一律に扱うのではなく、必要に応じて加筆・修正を行い、丁寧にメンテナンスすることです。
 低品質コンテンツとは?SEOへの影響と見分け方・改善方法
低品質コンテンツがSEOに与える影響とは?検索順位を下げる原因や見分け方、リライトや削除による改善方法を徹底解説します。
低品質コンテンツとは?SEOへの影響と見分け方・改善方法
低品質コンテンツがSEOに与える影響とは?検索順位を下げる原因や見分け方、リライトや削除による改善方法を徹底解説します。
非公開や削除を検討すべき記事の特徴
以下は、非公開(noindex)や削除を優先的に検討すべき記事の特徴です。
- アクセス数やインプレッションが極端に少ない
- 内容が薄く、独自性や専門性が乏しい
- 他の記事と重複している、またはカニバリゼーションを起こしている
- 情報が古く、現在の制度やデータと一致していない、または引用元のリンクが切れている
このような記事を放置すると、検索エンジンに「価値の低い情報が多いサイト」と見なされる可能性があるため、適切な対応が求められます。
 noindexとは?SEO対策を正しく理解してインデックスをコントロール
SEO対策の施策の1つとしてnoindexという言葉を聞いたことはありませんか?検索結果に特定のページを表示させないために設定するのがnoindexですが、なぜSEO対策になるのでしょうか?基本的なところから解説します。
noindexとは?SEO対策を正しく理解してインデックスをコントロール
SEO対策の施策の1つとしてnoindexという言葉を聞いたことはありませんか?検索結果に特定のページを表示させないために設定するのがnoindexですが、なぜSEO対策になるのでしょうか?基本的なところから解説します。
ユーザーニーズに応じたリライトで再評価を狙う
一方で、検索ニーズと関連性があり、一部でも有用な情報を含んでいる記事は、リライトによって価値あるコンテンツとして再評価される可能性があります。
以下のような対応が有効です。
- 最新情報や統計データの追加
- 見出しや構成の見直し、内容の補強
- 関連記事との統合による情報の集約
- タイトルやキーワードの最適化
- 最終更新日の明記による「更新されている印象」の付加
こうした対応を通じて、検索エンジン・ユーザーの双方からの評価を高めることができます。放置せずに定期的な見直しを行い、コンテンツを丁寧にメンテナンスしましょう。
 リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説
SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。
リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説
SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。
注意点2:重複コンテンツは統合・削除する
同じテーマを扱う記事が複数存在したり、引用が多すぎたりすると、Googleから重複コンテンツと判断される可能性があります。重複した内容が多いと、サイト全体の情報に独自性がないと判断され、SEO評価を下げる原因になりかねません。
このような場合は、重複する記事同士を統合する、削除する、あるいは構成や内容を大きく見直すといった対応が必要です。特にリライト時には、既存の記事と内容が重なっていないかを事前に確認しておくことが重要です。
また、引用が多くなる場合は、自社の見解や業務上の知見を補足することで、独自性を担保することが求められます。記事の重複や冗長性を定期的に見直し、検索エンジンから正しく評価される構成へ最適化することが、SEO改善に効果的です。
 重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説
重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。
重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説
重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。
注意点3:専門家の監修で信頼性を高める
金融・医療・法律など、ユーザーの健康や経済、安全に影響を与えるテーマは、Googleの検索評価においてYMYL(Your Money or Your Life)領域と位置づけられ、特に厳格な評価基準が適用されます。
これらのジャンルでは、誤った情報がユーザーに深刻な影響を与えるリスクがあるため、信頼性の高い情報提供が強く求められます。
そのため、YMYLに該当するコンテンツでは、専門家による監修や執筆、著者情報の明記などが信頼性の担保に直結します。特に記事を更新する際には、情報が最新かつ正確であり、専門的な裏付けがあるかを確認することが重要です。
 YMYLとは?Googleが求める品質とSEOにおける対策ポイント
人々の生活に影響を与える政治やお金、健康などの情報を扱うYMYLについて重要視される理由や対策方法についてまとめています。Google やユーザーからの評価を高めるためにも、ガイドラインを守った高品質なサイト運営を目指しましょう。
YMYLとは?Googleが求める品質とSEOにおける対策ポイント
人々の生活に影響を与える政治やお金、健康などの情報を扱うYMYLについて重要視される理由や対策方法についてまとめています。Google やユーザーからの評価を高めるためにも、ガイドラインを守った高品質なサイト運営を目指しましょう。
SEOコンテンツの更新を継続する4つのコツ

SEOで成果を出すには、質の高いコンテンツを継続的に発信し続けることが欠かせません。とはいえ、日々の業務の中で更新を続けるのは簡単ではないのが実情です。
ここからは、コンテンツ更新を無理なく習慣化するための工夫や、継続を支える4つの運用のコツを紹介します。
コツ1:ツールの活用で更新作業を仕組み化する
コンテンツ更新を継続するには、「いつ・誰が・何を」行うのかを明確にし、事前に計画を立てることが欠かせません。そのために役立つのが、コンテンツカレンダーとプロジェクト管理ツールの併用です。
1〜3ヶ月単位で、以下のような要素を整理・共有しておくことで、更新作業を仕組み化できます。
- 記事のテーマ・タイトル案
- 対象キーワード
- 担当者
- 執筆・校閲・公開までのスケジュール(編集工数・リードタイム含む)
- 対応する季節イベントやトレンド
これらの管理には、次のようなツールが便利です。
| ツール名 | 特徴・活用ポイント |
|---|---|
| Googleスプレッドシート | 柔軟にカスタマイズでき、同時編集にも対応 |
| Notion | タスク管理や議事録と連携しやすいオールインワン型 |
| Trello | カード形式で進捗を視覚的に把握できる |
| Airtable | 表とデータベースの機能を備え、柔軟性が高い |
こうしたツールを活用すれば、属人化を防ぎながらチーム全体での進捗管理と計画的な更新運用が可能になります。
 プロジェクト管理ツール23選を比較!無料ツールも紹介
プロジェクト管理ツールはタスク管理や情報共有を効率化します。本記事では、無料ツールを含む23種類のプロジェクト管理ツールの特徴や機能を比較し、選び方のポイントを詳しく解説しています。
プロジェクト管理ツール23選を比較!無料ツールも紹介
プロジェクト管理ツールはタスク管理や情報共有を効率化します。本記事では、無料ツールを含む23種類のプロジェクト管理ツールの特徴や機能を比較し、選び方のポイントを詳しく解説しています。
コツ2:新規記事とリライトを使い分ける
SEOで成果を上げるには、新規記事の追加と既存コンテンツのリライトを目的に応じて使い分けることが重要です。
新規記事は、これまで拾えていなかった検索キーワードに対応し、新たな検索流入の獲得を狙う施策です。自社サイトに不足しているテーマや、高い検索ボリュームがある未対策キーワードは、新規での対応が有効です。
一方、リライトは、すでに公開済みの記事の検索順位やCTR、アクセス数を改善する施策です。以下のような基準で、優先順位を見極めましょう。
【リライトの優先順位を見極める判断基準】
- 検索順位が10〜30位にとどまり、あと一歩で上位を狙える記事
- 掲載順位は高いが、クリック率(CTR)が平均を下回っている記事
- 内容が古くなっている、または競合に情報量で劣っている記事
これらは、Google Search ConsoleやGoogleアナリティクスを使って分析可能です。さらに、Ahrefs や SEMrushを使えば、競合との比較や、被リンク状況、流入キーワードの網羅性まで把握できます。
リライトの際は、タイトルや見出しの調整に加えて、検索ニーズの変化を踏まえた情報の追記・再構成・ビジュアル要素の最適化も行うと効果的です。
コツ3:リソースが少ないなら無理をしない
中小企業や個人運営のメディアでは、コンテンツ更新に多くの時間や人手を割けないこともあります。その場合は、無理に量を追わず、継続可能なペースで質を重視することが重要です。
月1本の更新でも、価値ある記事を出し続ければSEO効果は期待できます。ネタに困った際は、問い合わせ対応や社内資料からテーマを拾うことで、負担を抑えながら更新が可能です。また、新規作成にこだわらず、既存記事のリライトを中心に運用を組み立てる戦略も効果的です。定期的な見直しで、情報の鮮度と検索順位を保つことができます。
「毎週1回」「毎月1回」など、あらかじめ無理のない更新頻度を決めておくと運用が安定します。頻度が低い場合は、リライトや内部リンク強化を並行することで、クロール頻度の低下も補えます。
継続性と質を両立する仕組みが、少ないリソースでも成果を出すための鍵となります。
 内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説
内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。
内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説
内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。
 クローリングとは?スクレイピングとの違いや検索エンジンに重要な対策方法を解説
クローリングは、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを巡回し情報を収集するプロセスです。この記事では、基本概念、スクレイピングとの違い、検索エンジン最適化のための対策方法について解説しています。
クローリングとは?スクレイピングとの違いや検索エンジンに重要な対策方法を解説
クローリングは、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを巡回し情報を収集するプロセスです。この記事では、基本概念、スクレイピングとの違い、検索エンジン最適化のための対策方法について解説しています。
コツ4:外注も検討する
コンテンツの更新は、基本的には社内で内製する体制が理想的です。しかし、繁忙期やリソース不足などで対応が難しくなる場面もあるでしょう。そうしたときは、無理に社内だけで抱え込まず、外注を柔軟に取り入れることで、更新頻度を落とさずに運用を続けることが可能です。
ポイントは、外注を「イレギュラー対応」としてではなく、業務フローの一部としてあらかじめ組み込んでおくことです。例えば、毎月の発注スケジュールを事前に設定したり、構成案や編集指示をテンプレート化することで、スムーズな依頼と作業のルーティーン化が図れます。
内製と外注を状況に応じて使い分けることで、無理なく継続できる運用体制が整い、長期的に安定したSEO更新が実現できます。
更新を外注する際の2つのポイント

コンテンツの更新頻度を維持するには、外部パートナーの活用も有効な選択肢です。特に社内リソースが限られている場合、外注によって作業を安定化させることができます。
ただし、任せ方を誤ると期待した成果につながらないこともあります。ここでは、「信頼できる業者の選び方」と「丸投げを避けた運用体制づくり」という2つの観点から、外注を円滑に進めるための基本的な考え方を紹介します。
ポイント1:信頼できる業者を選ぶ
継続的な更新を外注に任せる場合は、信頼できるパートナー選びが成功の鍵となります。選定時には、SEO支援の実績、得意ジャンル、キーワードや構成案の対応力などをチェックしましょう。
さらに、納期の正確さ・コミュニケーションのスムーズさ・フィードバックへの対応力なども重要な判断基準です。単にライティングスキルがあるだけではなく、継続的に協力できる運用パートナーかどうかを見極める視点が求められます。
 SEO対策は外注すべき?費用やメリット、選び方を解説
SEO対策を外注する際の費用相場やメリット、業者選定のポイントを解説しています。外注時の費用相場や業者選定のポイントも紹介し、効果的な施策の実践をサポートします。
SEO対策は外注すべき?費用やメリット、選び方を解説
SEO対策を外注する際の費用相場やメリット、業者選定のポイントを解説しています。外注時の費用相場や業者選定のポイントも紹介し、効果的な施策の実践をサポートします。
ポイント2:業者に丸投げしない
コンテンツの更新業務をすべて外注する「フルアウトソース型」は、社内リソースが限られている企業にとって有効な選択肢です。ただし、すべてを任せきりにするのではなく、最初にしっかりと方針・ルールを共有し、信頼できるパートナーと連携することが成功の鍵となります。
特に注意したいのが、構成案の意図や読者像のすり合わせ、進行管理のルール作り、定期的な品質チェックの体制です。更新頻度を安定させるためにも、「丸投げ」ではなく「協業」のスタンスで臨むことが、長期的な成果につながります。
 オウンドメディアの記事を外注するメリットと費用感、選び方を解説
オウンドメディアの記事外注は、社内リソースの節約や専門的な視点から高品質なコンテンツを提供するメリットがあります。外注のメリット・デメリット、費用感、適切な外注先の選び方について解説しています。
オウンドメディアの記事を外注するメリットと費用感、選び方を解説
オウンドメディアの記事外注は、社内リソースの節約や専門的な視点から高品質なコンテンツを提供するメリットがあります。外注のメリット・デメリット、費用感、適切な外注先の選び方について解説しています。
自社に合った更新頻度でSEO効果を上げよう

SEOにおける更新頻度は、「多ければ多いほど良い」という単純な話ではありません。大切なのは、自社の目的や体制、リソースに合った現実的なペースで、質の高いコンテンツを継続的に提供することです。
また、新規記事の追加だけでなく、既存記事のリライトや情報の更新もSEOにおいて重要な評価ポイントとなります。更新頻度を支える体制を整えるとともに、必要に応じて外部パートナーの力を借りることも、無理のない運用には有効です。
まずは、自社の現状に最適な更新頻度を見極め、実現可能な範囲で着実に取り組むことが、SEOで安定した成果を出すための第一歩となります。
<無料>資料ダウンロード
【プロにお任せ】SEOコンサルティング
見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決