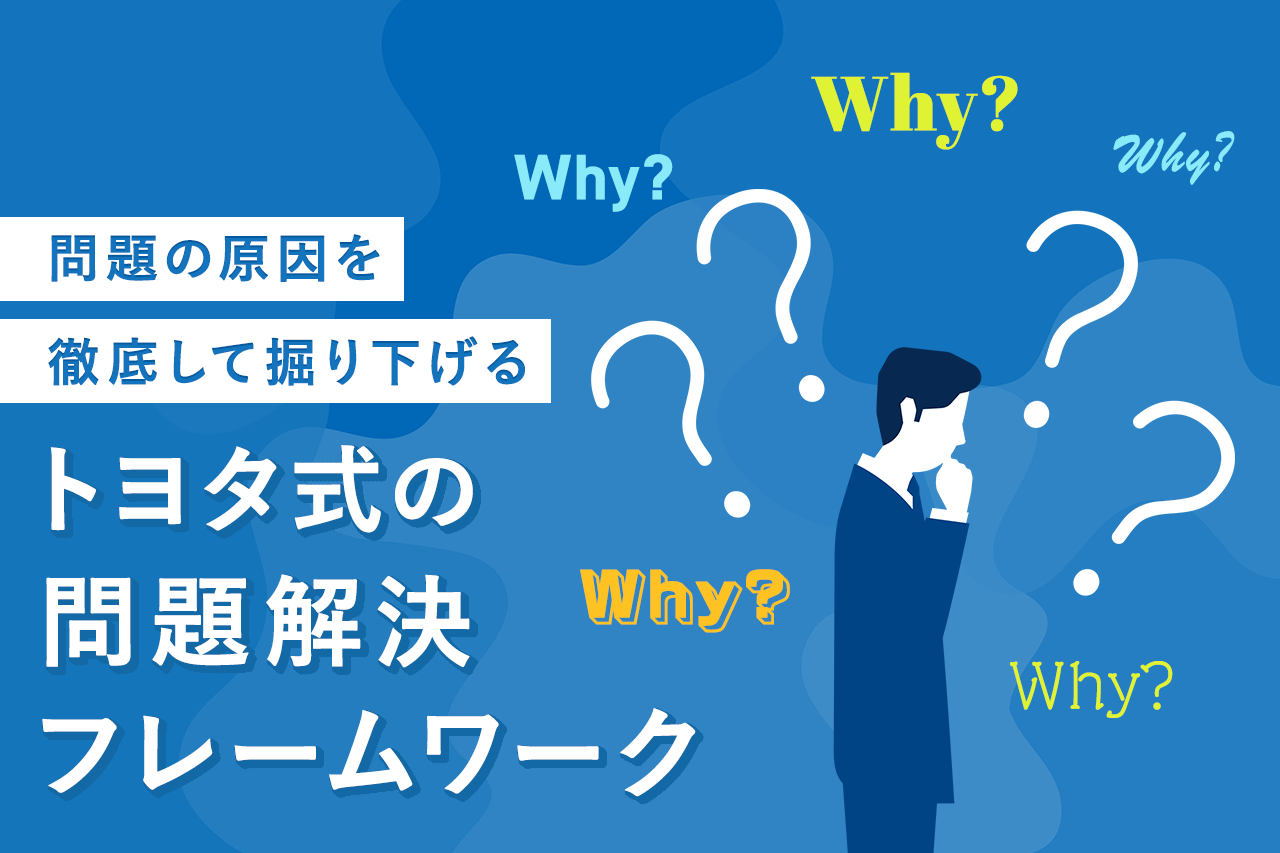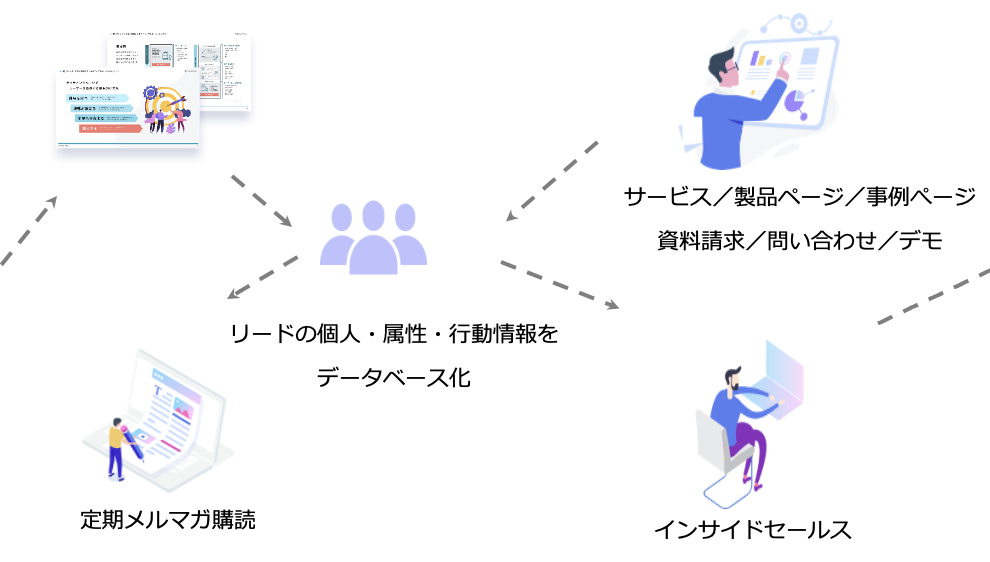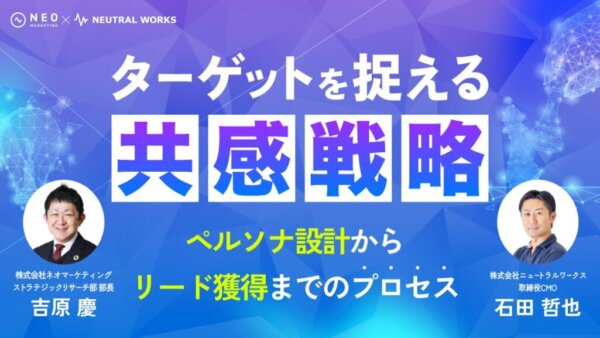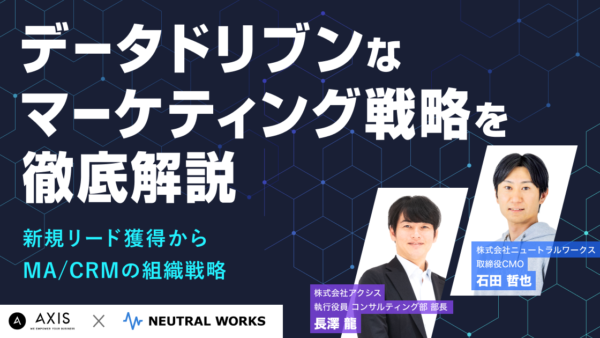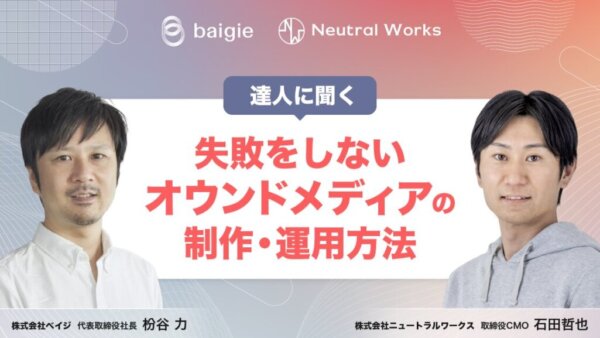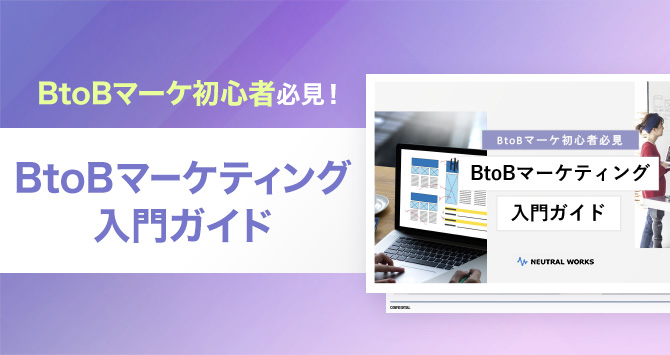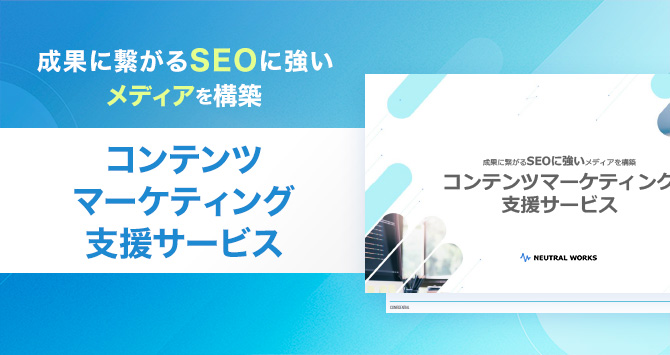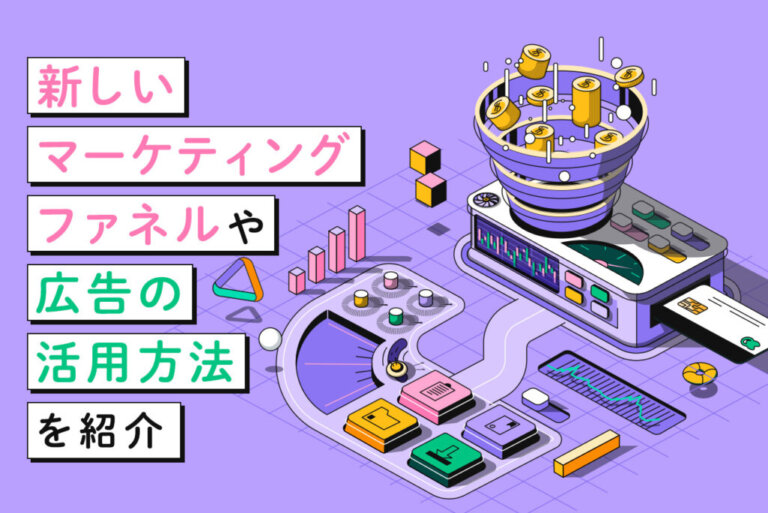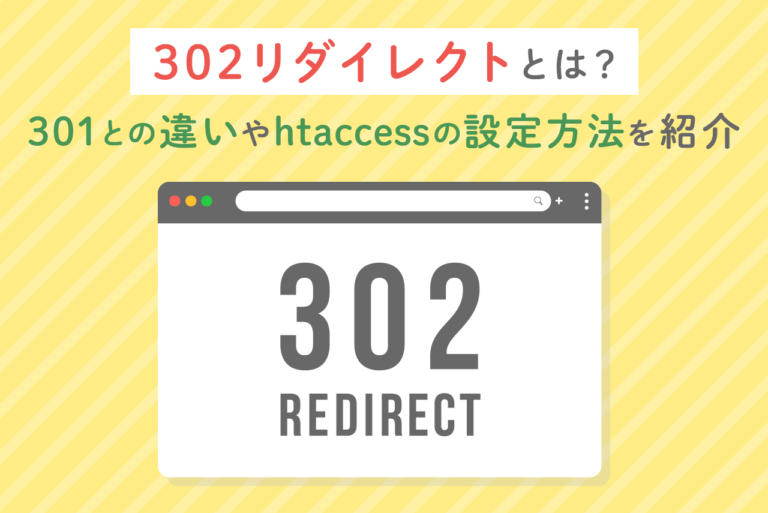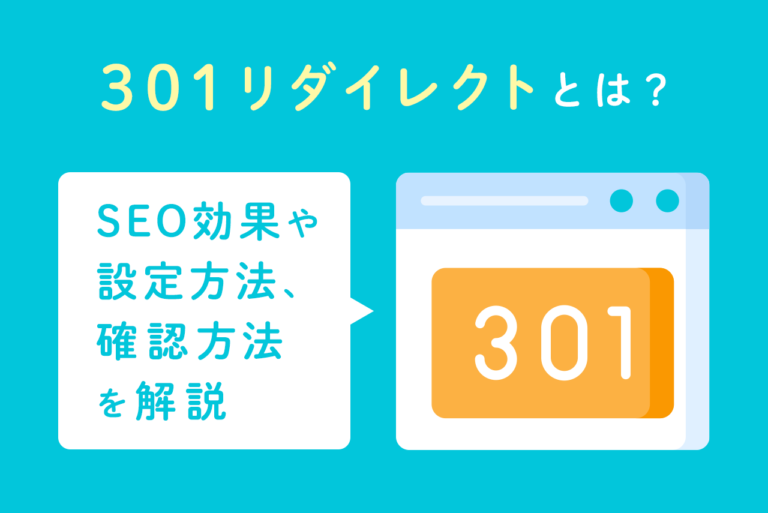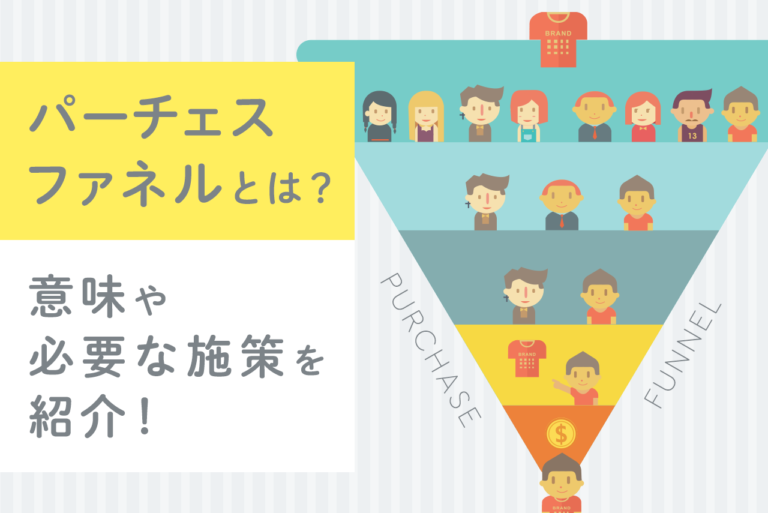トヨタが実践していたことで知られる「なぜなぜ分析」とは、どういった分析手法なのでしょうか?簡単そうに思える「なぜなぜ分析」ですが、実践するにはいくつかのコツや注意点があります。そこでこの記事では「なぜなぜ分析」について、分かりやすく解説します。
<無料>資料ダウンロード
【サイト運営者必見】お客様成功事例集
集客と売上がアップした成功実績が見られる!
目次
なぜなぜ分析とは

なぜなぜ分析は、トヨタ自動車から生まれた問題解決のフレームワークです。トヨタ自動車工業の元副社長である大野耐一氏の著書『トヨタ生産方式』によって広く知られるようになりました。
「なぜなぜ分析」では、一つの問題に対して「なぜ?」と問題が起こった原因を見つけ出し、さらに見つかった原因に対して「なぜ?」とその原因が起こった原因をさらに見つけることを繰り返していきます。さらに、問題の根本的な原因を明確にして改善策を練るための手法です。
大野耐一氏が著書の中で「5回の『なぜ』を自問自答する」と説明したことから、英語では「5Whys」と呼ばれることもあります。
<無料>資料ダウンロード
【売上アップ】Webサイト改善コンサルティング
本物のプロが、集客と売上に繋がるWebサイトに改善!
なぜなぜ分析のやり方をトヨタでの実践例で紹介

では、大野耐一氏の著書『トヨタ生産方式』で紹介されている、なぜなぜ分析のやり方を紹介します。
例題:機械が動かなくなった原因の特定
著書の中では例題として「機械が動かなくなった」という問題を解決するために、なぜなぜ分析を行っています。
1回目のなぜ:機械が動かなくなったのはなぜ?
答え「オーバーロードがかかり、ヒューズが切れたから」
2回目のなぜ:オーバーロードがかかったのはなぜ?
答え「オーバーロードがかかったのは、軸受部の潤滑が十分でないから」
3回目のなぜ:十分に潤滑しないのはなぜ?
答え「十分に潤滑しないのは、潤滑ポンプが十分くみ上げていないから」
4回目のなぜ:十分くみ上げられないのはなぜ?
答え「十分くみ上げられないのは、ポンプの軸が摩擦してガタガタになっているから」
5回目のなぜ:摩擦したのはなぜ?
答え「摩擦したのは、ストレーナー(濾過器)が付いていないので切粉が入ったから」
5回の「なぜ?」を繰り返した結果、例題では「ストレーナーを取り付ける」という対策にたどり着きました。このように、なぜなぜ分析は企業では主に品質管理や労働安全管理の現場で取り入れられている問題解決方法です。
なぜなぜ分析のやり方

次に、なぜなぜ分析のやり方の手順を解説します。
手順1. 問題(事象)の設定
問題とはあるべき姿と現状のギャップです。あるべき姿「機械が止まらずに動く」に対して、現状「機械が動かなくなった」のギャップを具体的な表現で問題提起することがなぜなぜ分析のスタートです。具体的な表現で問題提起するとは以下のようなことを指します。
悪い例:「なぜ残業時間が多いのか?」
良い例:「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」
上記の例では、残業時間の削減をゴールに設定するのではなく、より具体的に「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」という根本的な問題をゴールに設定するほうが、より明確に解決方法が見出せるでしょう。
手順2. 「なぜ」を繰り返し問題を細かく要素分解する
具体的・現実的な問題を設定したら、それを丁寧に観察することで「なぜ」を繰り返します。事実を正しく認識することで、問題の階層を掘り下げることが重要です。下記は「なぜ」の問い方の例です。それぞれの視点を意識して目の前の事象を観察することで、問題を深く理解することができます。
- なぜこの事象が起こるのか?
その事象が起こるまでの連鎖を観察します。現地まで行き、問題の現象を実際に見ることで理解できます。最初にこの現象が起き、次にこの現象が誘発されて、この問題の事象が発生する、という連鎖を見つけます。
- なぜこのような事象が起こり得るのか?
現象が連鎖して問題の事象が発生するのはなぜか、物理的に説明します。自宅のブレーカーが落ちたため停電した、というように文章化できます。
- どの要素とどの要素がどう関係するとこの現象になるのか?
問題の事象は常に発生しているわけではないでしょう。複数の要素が関係した結果として問題となる場合がほとんどです。なぜ自宅のブレーカーが落ちたのかは、消費電力の多い家電を同時にたくさん使ったのかもしれません。さらに気温が低くエアコンが自動的に通常より強く動いたためかもしれません。実際の現場を観察することで原因を究明します。
- なぜこの不具合発生メカニズムが成立するのか?
問題が発生するメカニズムを探します。問題となる事象は物理現象なので、その現象を引き起こす条件となる要素を見つけるのが目的です。正常な状態に「どのような要因が加わると不具合が発生するか」という差分を見ていくのもヒントになります。
- なぜその成立する条件を阻止できないのか?
不具合が発生する条件が理解できたら、その成立条件を阻止する方法を考えます。不具合を引き起こす条件が同時に成立しないように阻む方法、一つの条件が他の条件に連鎖するのを防ぐ方法などが見つかれば、問題は発生しません。
補足:「なぜ」の答えは一つに限定する必要はない
なぜなぜ分析を進めていく際に、それぞれの「なぜ」の答えを一つに限定して直線的に深掘りしていく必要はありません。一つの問題に複数の原因があり、さらにそれらの原因も複数の要素に分解できる。これを繰り返すと、なぜなぜ分析もロジックツリーのように分岐していくこととなります。
現実的には、一つの「なぜ」には複数の原因が存在している可能性もあり、一つに絞り込んでしまうと他の要素を見落とす危険もあります。「なぜ」の連鎖が3本考えられたとすれば、その3本を問題解決方法の仮説として検証していけば良いのです。
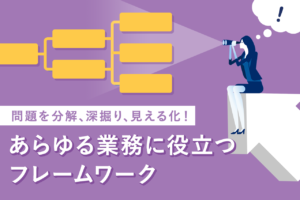 ロジックツリーとは?作り方、テンプレートも紹介
ロジックツリーはあらゆるビジネスでの役立つフレームワークです。企画業務に携わる人だけではなく、営業・人事…あらゆる職種の人に役立ちます。問題を分解し、具体的な解決策を見つける方法をロジックツリーを作成して見つけましょう。
ロジックツリーとは?作り方、テンプレートも紹介
ロジックツリーはあらゆるビジネスでの役立つフレームワークです。企画業務に携わる人だけではなく、営業・人事…あらゆる職種の人に役立ちます。問題を分解し、具体的な解決策を見つける方法をロジックツリーを作成して見つけましょう。
分析を始める前に知っておきたい5つのチェックポイント

効果的に分析するには、明確化すべき事柄や意識すべきポイントがあります。以下に挙げてみましょう。
- 問題点を具体的に提示できているか?
- 主観で分析していないか?
- あいまいな答えで進行していないか?
- 明確で具体性のある文章に落とし込めているか?
- 導き出した解決策は実行できるか?
なぜなぜ分析を行う場合、複数人で取り組むことをおすすめします。なぜなら、客観的な視点、多面的な考え方が可能だからです。複数人の視点や考え方があると、意味のある問題定義ができ、根本的な原因に迫ることが期待できるでしょう。
なぜなぜ分析をする際の注意点

なぜなぜ分析は、簡単に思える方法ですが、実践してみると分析が迷走したり解決策にたどり着かない場合もあります。ただ「なぜ?」を繰り返すだけでは、根本的な原因にたどり着かず解決方法を見出せないのです。なぜなぜ分析を行う際の注意点を解説します。
個人の問題に帰結させず、組織としての改善点を見つける
なぜなぜ分析では、個人に原因を求めず組織として仕組みやシステムの問題を見つけることで、効果的な改善策につながります。一見すると個人の問題だと思ってしまいがちなことでも、根本的な解決策を見つけるためには、組織の仕組みや制度、システムの流れなどを客観的に見つめてなぜなぜ分析を行うことが大切です。
悪い例
「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」→「気合が足りないから」
良い例
「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」→「仕事が多いから」
このように「なぜ、そうなるのか」ではなく「何が原因で、そうさせているのか?」を深掘りしていきましょう。
「なぜ?」は具体的な一つの現象に絞り込む
なぜなぜ分析では、答えを具体的に絞り込むことが大切です。次の「なぜ?」につなげるためにも、答えは具体的に分解して考えてみましょう。
悪い例
「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」→「仕事が多いから」
ここで挙げた答えには、本人の担当の仕事、他者から依頼された仕事、後輩のサポートの仕事、明日の準備のための仕事など複数の答えが混ざっています。
良い例
「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」
- 本人の担当の仕事が手付かずだから
- 他者から依頼された仕事が多いから
このように「なぜ?」の答えを細かく分解し、状況に合わせて次の「なぜ?」の対象を一つに絞って分析を繰り返していきましょう。
「なぜ?」はすべて関連するようにつなげていく
なぜなぜ分析では、現象のつながりを途切れさせないようにしましょう。一見つながっているように見えて、具体的なつながりが途切れている例があります。
悪い例
「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」→「仕事が多いから」
この例では、定時退社と仕事の量は具体的なつながりがないのです。具体的なつながりに注目してみると「他者から依頼された仕事が多く、本人の仕事が手付かずだから」という原因が見えてきます。
良い例
「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」→「他者から依頼された仕事が多いから」
現象が具体的につながっているかは、分析結果から「だから」でつないで確認してみると分かりやすいでしょう。「仕事が多い、だから定時退社できない」と「他者から依頼された仕事が多い、だから定時退社できない」では、後者のほうがより論理的な分析になっていますね。
「なぜ?」は自分、組織がコントロールできる範囲で考える
なぜなぜ分析では「なぜを5回繰り返せ」といわれています。しかし、5回という回数は絶対ではありません。このなぜなぜ分析のゴールは、表面上の問題を深掘りして根本的な原因を探り出し、解決策にたどり着くこと。根本的な原因を突き止められれば、なぜなぜ分析が何回になっても構わないのです。
ただし、2、3回でなぜなぜ分析を終えてしまうと、根本的な原因の解決には至らず、同じトラブルがまた発生してしまうことが多くあります。なぜなぜ分析の回数が多すぎても、自分でコントロールできる範疇外にまで問題が広がってしまい、解決が難しくなります。
たとえば、なぜなぜ分析で「なぜ定時で仕事が終わらないのか?」という問題の分析を繰り返して「他者から依頼される仕事が多すぎるから」という原因にたどり着いたとします。
ここで「仕事が多すぎる」という原因を深掘りしてしまうと「なぜ仕事量が多いのか?」「会社が人手不足なのはなぜか?」といった自分でコントロールできる範囲外の問題になり、解決できなくなってしまいます。
この場合、「なぜ他者の分の仕事を依頼されるのか?」という問題の分析に舵を切り、「仕事の分担が偏っている」などの原因を見つけること。その結果、自分でコントロールして解決できる方法を見出せるようになります。
根本原因を突き止められない「なぜなぜ分析」の失敗事例

ここまで、「なぜなぜ分析」のやり方、チェックポイント、注意点を解説してきましたが、それでもやはり現場でうまくいかないケースは少なくありません。そこで、よくある失敗事例を紹介しますので、失敗を回避することにつなげてください。
【失敗事例1】スタートの問題点があいまい
スタートになる問題点があいまいだと、その後の回答はどんなに頑張ってもあいまいなものにしかなりません。「納期が遅れたのはなぜか?」といった問題点の提示では情報が少なくあやふやです。相手は誰で、いつのことで、どれくらい遅れたのか、そういった具体的な情報も提示しましょう。
「新しい取引先と8月3日に契約し、2週間後の17日に納品としたところ、8月20日に納品されたのはなぜか?」、これで問題がかなり具体的になりました。これで掘り下げていくと、根本原因に近づいていくでしょう。
【失敗事例2】個人の問題にしてしまう
個人の問題にしてしまうケースは少なくありません。問題提示を「Aさんがマニュアル通りに作業せず機器が故障したのはなぜか?」としたときに、Aさんが忘れてしまったから、Aさんが疲れていたからといった回答になってしまうと、おそらく再発防止につながりにくくなってしまいます。
Aさんがマニュアル通りに作業しなかったことに気付けない現場の仕組みにフォーカスし、客観的に問題を掘り下げていくことが肝要です。
なぜなぜ分析のまとめ

なぜなぜ分析は、問題の解決策を見つけたりや再発を防止したりするための分析法です。根本的な原因を特定することは可能ですが、解決策を見つけるために原因を見出すのであって、問題の責任の所在をはっきりさせたり、個人の責任を追及したりする方法ではありません。そもそも問題の原因が一つでない場合も多いのです。
この記事の例でいえば、定時退社できない原因は仕事の分担だけでなく「上司より先に帰れない雰囲気」も原因になっているかもしれません。一度間違った方向でなぜなぜ分析を進めると、すべてが違う方向に向かってしまいます。
恣意的な分析にならないよう、見直しと修正を行いながら進めましょう。なぜなぜ分析はコツさえ掴めば問題解決に力を発揮する分析方法です。上手に活用してみてくださいね。
<無料>資料ダウンロード
【売上アップ】Webサイト改善コンサルティング
本物のプロが、集客と売上に繋がるWebサイトに改善!
なぜなぜ分析のよくあるご質問
- なぜなぜ分析とは?
-
一つの問題に対して「なぜ?」と問題が起こった原因を見つけ出し、さらに見つかった原因に対して「なぜ?」とその原因が起こった原因をさらに見つけることを繰り返していくことで、問題の根本的な原因を明確にして改善策を練るための手法です。
- なぜなぜ分析のやり方は?
-
まず、あるべき姿に対して、現状のギャップを具体的な表現で問題提起します。次に、提起した具体的・現実的な問題を丁寧に観察することで「なぜ」を繰り返します。
- なぜなぜ分析をする際の注意点は?
-
個人に原因を求めず組織として仕組みやシステムの問題を見つけること、答えを具体的に絞り込むこと、現象のつながりを途切れさせないようにすること、自分や組織がコントロールできる範囲で考えること、などの点に注意することが重要です。