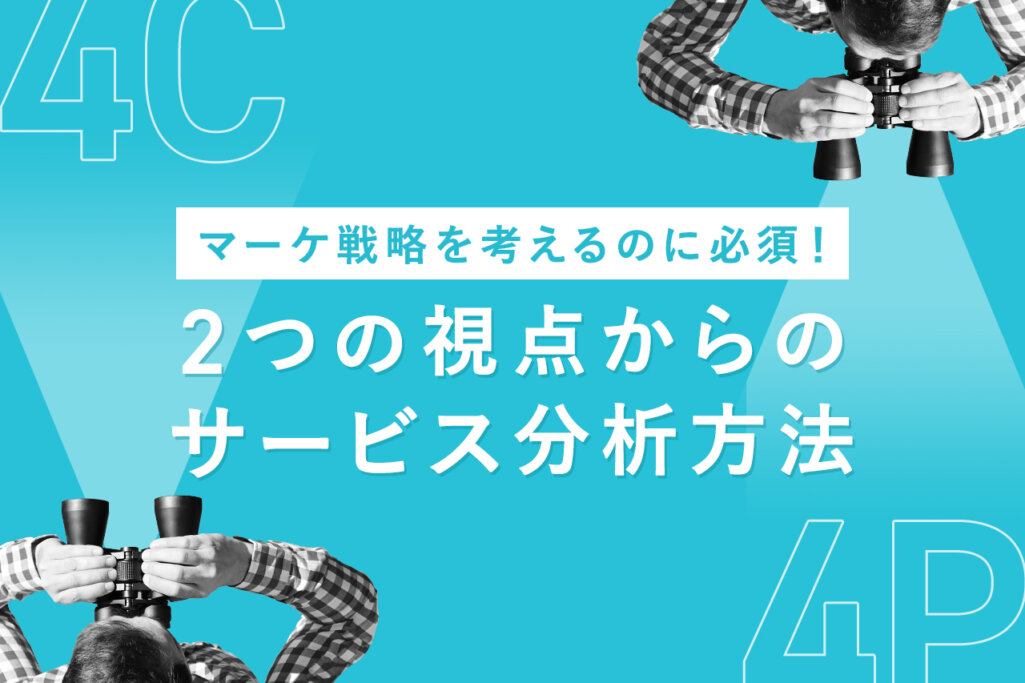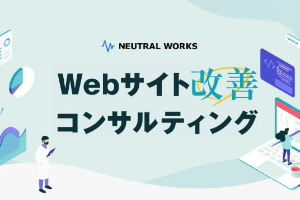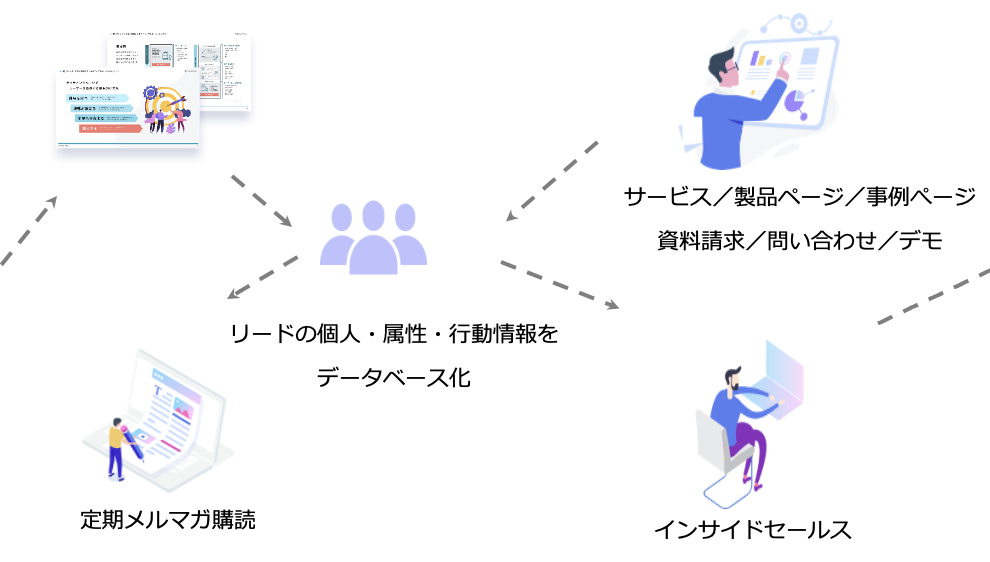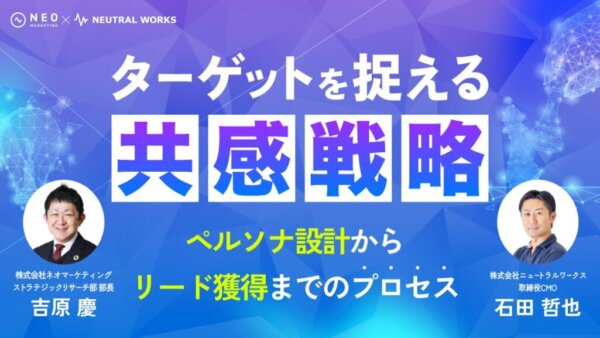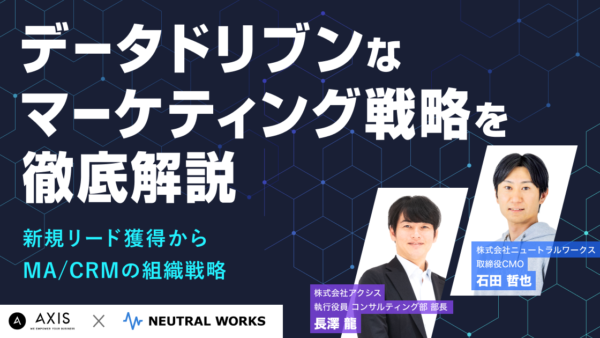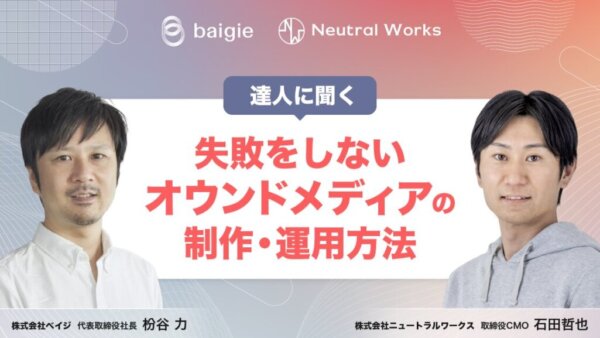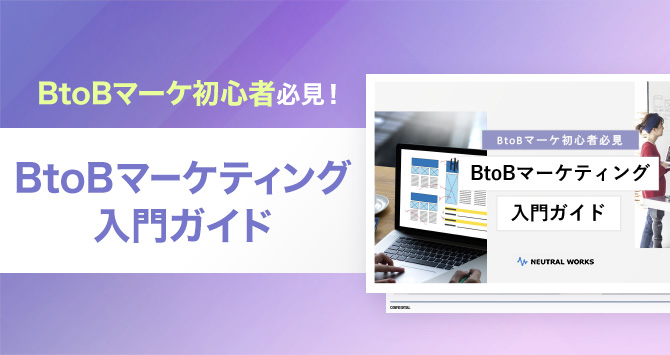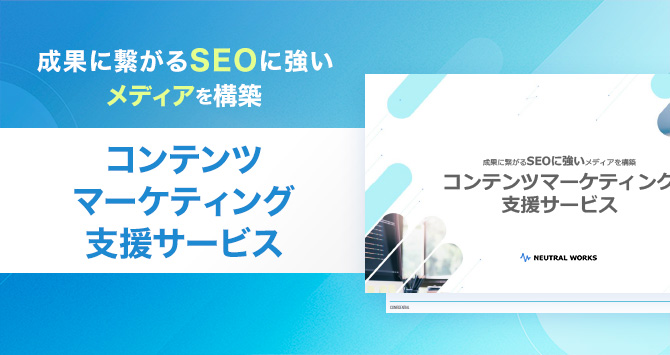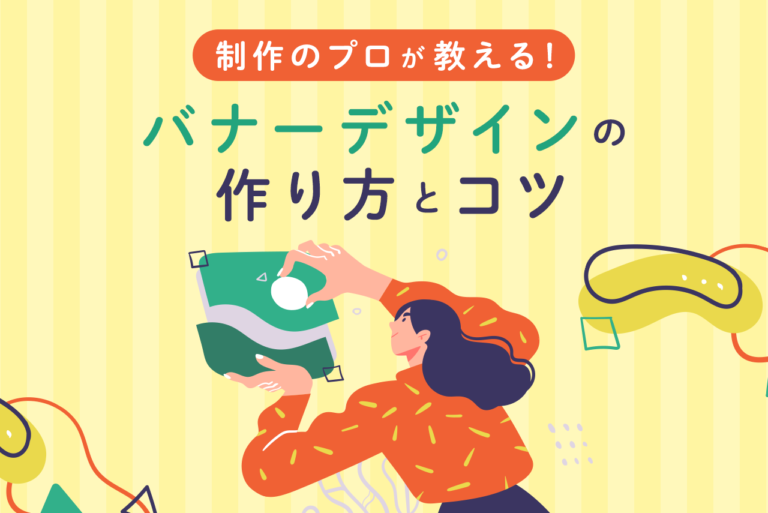ビジネスを行う上で、営業戦略やマーケティング手法は無数にあります。その中から考えるべきポイントをパターン化し、誰でもできるように体系化したものをフレームワークといいます。
そのマーケティングのフレームワークの一つが、「4P分析」です。アメリカのマーケティング学者エドモンド・マッカーシーが1960年に提唱したもので、現代のマーケティングでも生かせる考え方となっています。
この記事では、4P分析と4C分析について解説するとともに、それぞれの違い、事例もまとめています。無料テンプレートもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
サイトの成果改善でお困りではないですか?
「サイトからの問い合わせを増やしたいが、どこを改善すべきか分からない…」そんなお悩みをお抱えの方、ニュートラルワークスにご相談ください。
弊社のサイト改善コンサルティングでは、サイトのどこに課題があるかを実績豊富なプロが診断し、ビジネスに直結する改善策をご提案します。
4P分析とは
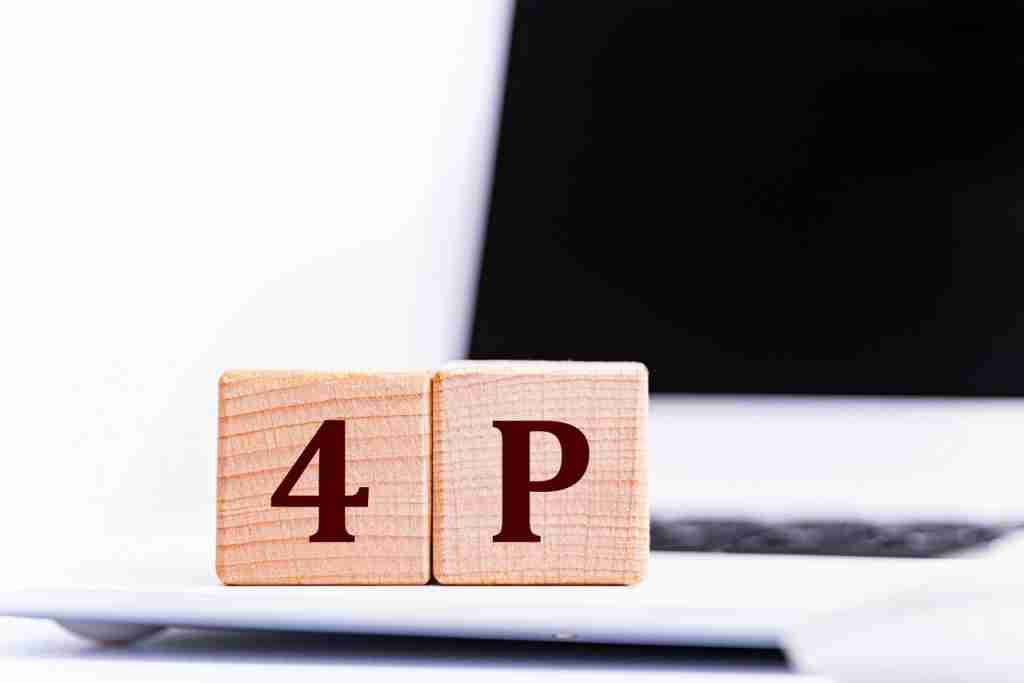
4P分析に使われる4Pとは、以下の用語の頭文字です。
- Product(プロダクト:製品)
- Price(プライス:価格)
- Place(プレイス:流通)
- Promotion(プロモーション:販売促進)
4Pは、「どのような製品を・どれくらいの価格で・どの販売チャネルで売っていくのか」「どのようなターゲット層にどうアプローチするのか」などのマーケティング戦略を考えるときに使われる要素です。
以下より、4P分析テンプレートのダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
<無料>資料ダウンロード
【無料テンプレート】4P分析
マーケティングの基本をおさえる!無料テンプレートをダウンロード
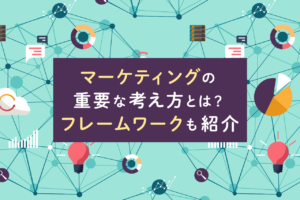 マーケティング戦略の立て方とは?フレームワーク別解説とテンプレート紹介
マーケティング戦略は、企業の目標達成や成長に欠かせない重要な要素です。本記事では、戦略の基本的な考え方や立て方、具体的なフレームワークや活用例、実践的なテンプレートを詳しく解説しています。
マーケティング戦略の立て方とは?フレームワーク別解説とテンプレート紹介
マーケティング戦略は、企業の目標達成や成長に欠かせない重要な要素です。本記事では、戦略の基本的な考え方や立て方、具体的なフレームワークや活用例、実践的なテンプレートを詳しく解説しています。
なぜ4P分析が必要なのか
4P分析をすることで、「プロモーションしたい商品の価値」をより明確にできます。例えば、自社商品が他社より安く提供できるなら「Price(プライス:価格)」が価値になりますし、SNSから人気に火が付いた商品は「Promotion(プロモーション:販売促進)」が価値になります。
要するに「商品の強み」や「売り」が分かりやすくなり、商品をセールスするときに顧客へのアピールポイントが明確になるのです。
4P分析を活用する際の注意点

商品をセールスするためには、適切な4P分析が必要になります。注意すべきポイントを見ていきましょう。
1. 顧客のニーズを把握したうえで分析する
適切な4P分析とは「顧客のニーズに即した分析」ということです。自社の売りたい商品や大事にしたいコンセプトにとらわれるのではなく、顧客の欲しい商品・顧客に求められている商品はどのようなものかをまず把握しましょう。
市場には非常に多くの商品とサービスがあふれ、顧客は多くの選択肢から商品・サービスを選べる立場にいます。顧客のニーズに添わないものはすぐに淘汰されてしまうでしょう。
2. 4Pをバラバラに分析しない
4Pの要素である「製品」「価格」「流通」「販売促進」は、バラバラの要素ではなくそれぞれが互いに連動しています。例えば、高級スキンケアのドモホルンリンクルは、高品質な商品ゆえに大量生産ができません。したがって、利益を出すためには高価格で販売する必要があります。
そのため、店頭販売を避けて通販限定にすることで価格競争を避けています。そして、スキンケアにお金をかける層に適切にアプローチをするため、TVCMと無料お試しセットのプロモーション戦略を取っています。
このように、一つの要素が他の要素にも連動していることがわかります。
3. イメージだけで考えず、根拠や証拠を明確にする
4P分析を行う際は、主観的なイメージだけで判断せず、根拠や証拠を明確にすることが重要です。例えば、「この価格なら売れる」「この販促方法が効果的」といった思い込みで施策を決定すると、期待した成果が得られない可能性があります。
市場調査データや競合分析、顧客アンケートなどの客観的な情報を活用し、各P(Product, Price, Place, Promotion)の戦略に論理的な裏付けを持たせることで、より精度の高いマーケティング施策を実施できます。
4. 一度の分析で終わらせず、継続的に観察する
商品発売後も、継続的に4P分析を行いましょう。顧客が求めるもの、人気の商品、競合が販売している商品の価格などは日々変わっていきます。パッケージデザインや価格帯、プロモーション方法などを時代の流れや市場の空気にあわせて更新し続けることで、顧客に長く愛される商品・サービスになります。
4C分析とは

4P分析と対になるフレームワークに「4C分析」があります。アメリカの経済学者ロバート・ラウターボーンが1993年に発表しました。4Pは商品・サービスを提供する企業側の視点なのに対し、4Cは商品・サービスの顧客側の目線に立って考えるのが特徴です。
4P分析に使われる4Cとは、以下の用語の頭文字です。
- Customer Value(顧客にとって価値はあるのか)
- Customer Cost(顧客が払うお金に見合っているか)
- Communication(顧客とのコミュニケーションは取れているか)
- Convenience(顧客に利便性はあるのか?)
社内で「この商品・サービスは素晴らしい」と思っていても、顧客側は「特に必要ない商品・サービス」だと感じているかもしれません。顧客側の視点から商品・サービスの特徴をとらえるために4C分析を行います。
以下より、4C分析の無料テンプレートがダウンロード可能です。ぜひご活用ください。
<無料>資料ダウンロード
【無料テンプレート】4C分析
顧客目線での分析に役立つ!無料テンプレートをダウンロード
なぜ4C分析が必要なのか
商品・サービスを提供する企業目線での分析が4P、商品・サービスの顧客視点での分析が4Cです。「売りたい側」、「買いたい側」の両方の視点で分析することで、商品の特徴や魅力が明確になり、より良いマーケティング戦略を考えられるのです。
例えば、4P分析の「Promotion(販売促進)」では、顧客に定期的にDMを送り、リマインド効果を狙うという発想になりますが、顧客目線の「Communication(顧客とのコミュニケーション)」で見た場合、「何度もDMが届いてうっとうしい」と思われる可能性に気付くことができます。
4C分析と3C分析の違い
4C分析は、顧客視点に立ち、自社の販売方法の課題を浮き彫りにして改善する手法です。一方の3C分析は、顧客・競合・自社のそれぞれの立場から、自社商品がどういうポジションにあるのかを分析する手法です。
4C分析:顧客・自社が対象で顧客視点
3C分析:顧客・競合・自社が対象で自社視点
4C分析と3C分析の違いを端的に表すと、上記のようになります。
4C分析を活用する際の注意点

マーケティングで4C分析を行う際に注意したいことは何でしょうか。ポイントを4つまとめました。
1. 顧客視点での分析を意識する
4C分析の要素はすべて顧客視点です。しかし、自社商品のマーケティングを行ううちに、気付かないうちに企業側の視点や想いが入ってしまい、4C分析を始めたのに4P分析になってしまうことがあります。
4C分析は常に顧客視点から離れないようにしましょう。対になる4P分析行い、両方を見比べることで、商品・サービスの弱点に気付くこともあります。
サービスの強みをどのようにアピールすべきかお悩みの方は、下記の記事も参考にしてみてください。
参考:マーケティングにおけるUSPとは|効果的なアピールで売上アップへ|株式会社TSUTA‐MARKE
2. イメージだけで考えず、根拠や証拠を明確にする
顧客視点を想定するときにやってしまいがちなのが、「イメージ」で顧客を想定することです。実際にアンケートを取ったりインタビューやリサーチを行ったりして、確かなデータを手に入れましょう。企業側のイメージによらず、実際の顧客の声を参考に商品・サービスを開発することで、顧客に商品の価値を感じてもらいやすくなります。
3. 顧客は誰かをはっきりさせてから分析する
4C分析をする際には、想定する「顧客」の像をはっきり決めておきましょう。例えば、同じ30代の女性でも、未婚か既婚か、子供の有無、共働きの有無などで商品に対するニーズが大きく異なります。顧客像をはっきりさせておかなければ、的確な分析はできません。商品・サービスの開発途中であっても顧客像がぶれないように気を付けましょう。
4. 4Cをバラバラに分析しない
4C分析においても、4つの要素には互いに連動した繋がりがあります。顧客の利便性を高める素晴らしい商品であっても、ターゲット層の「この商品ならここまで払える」という価格帯から大幅にずれていれば、購入には至らないでしょう。各要素をバラバラに分析せず、総合的に考えることが大切です。
 市場分析のためのフレームワークを紹介!やり方やツールもチェック
市場分析のために用いられるフレームワークについて、使い方や目的ごとでおすすめするフレームワークを紹介しています。 自社のビジネスをより成長させるためにも、正しいフレームワークの活用方法を覚えておきましょう 。
市場分析のためのフレームワークを紹介!やり方やツールもチェック
市場分析のために用いられるフレームワークについて、使い方や目的ごとでおすすめするフレームワークを紹介しています。 自社のビジネスをより成長させるためにも、正しいフレームワークの活用方法を覚えておきましょう 。
4P分析の事例

次に、4P分析の事例を紹介します。
スターバックスの事例
スターバックスは、「Product」を強みとして日本で大成功を収めました。スターバックスの商品はその国の文化を取り入れており、例えば、日本では抹茶関連の商品を作りました。
また、サイズも国によって異なります。日本では以下の4種類です。
- Short(ショート)240ml
- Tall(トール)350ml
- Grande(グランデ)470ml
- Venti(ベンティ)590ml
一番小さいショートは、日本人の体型にあわせて作られたサイズで他の国にはありません。
| Product | ショートサイズ・抹茶関連の商品開発 |
| Price | ある程度高価格帯 |
| Promotion | CMは打たずSNSでの口コミ訴求 |
| Place | 港区に多いなど高級な立地に出店 |
ユニクロの事例
なんといっても価格の安さがイメージにあるユニクロ。「Price」を強みとして大きく成長してきました。一方で、有名ブランドやデザイナーとコラボするなど良質な商品というイメージづくりも行ってきました。
- ジル・サンダー
- イネス・ドラフレサンジュ
- JWアンダーソン
- クリストフ・ルメール
- Theory
- マリメッコ など
その後、低価格ブランドである「GU」を立ち上げ、ユニクロは低価格路線から脱却。現在は「Product」「Promotion」を強みに展開しています。
| Product | 洗練された良質な商品 |
| Price | 「GU」を立ち上げ低価格から脱却 |
| Promotion | 季節に合わせたCMで訴求 |
| Place | 海外を含め店舗やECで展開 |
4C分析の事例

次は4C分析の事例を紹介します。
サッポロビールの事例
| Customer Value | 苦味を抑えたベルギービールを提供 |
| Cost | 低価格 |
| Convenience | コンビニや量販店のほか、ECでも購入可能 |
| Communication | Facebook、Twitterでのマーケティング |
日本ではなかなか飲む機会の少ないベルギービール。それを手頃な価格で誰にでも購入できるようにしたのが、サッポロビールが販売する「ホワイトベルグ」です。クラフトビール人気とあいまって、確かな顧客層をつかんでいます。
企業視点、顧客視点の両方で商品を分析するのが重要

4P分析による企業側の視点と、4C分析による顧客側の視点の両方を組みあわせることで、バランスの良い商品・サービス開発が行えます。いくら画期的な商品・サービスを開発しても、消費者に受け入れられなければヒットしません。
例えば、リモートワークに関連する商品・サービスは何年も前から存在していましたが、急激に世の中に浸透したのは、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの企業がリモートワークを必要としたからです。需要と供給のバランスがマッチして初めて、大きなヒットに繋がるのです。
サイトの成果改善でお困りではないですか?
「サイトからの問い合わせを増やしたいが、どこを改善すべきか分からない…」そんなお悩みをお抱えの方、ニュートラルワークスにご相談ください。
弊社のサイト改善コンサルティングでは、サイトのどこに課題があるかを実績豊富なプロが診断し、ビジネスに直結する改善策をご提案します。
4P分析と4C分析のよくあるご質問
- 4P分析とは?
-
4P分析に使われる4Pとは、「Product(プロダクト:製品)」「Price(プライス:価格)」「Place(プレイス:流通)」「Promotion(プロモーション:販売促進)」の頭文字です
4Pは、「どのような製品を・どれくらいの価格で・どの販売チャネルで売っていくのか」「どのようなターゲット層にどうアプローチするのか」などのマーケティング戦略を考えるときに使われる要素です。 - 4C分析とは?
-
4P分析に使われる4Cとは、「Customer Value(顧客にとって価値はあるのか)」「Customer Cost(顧客が払うお金に見合っているか)」「Communication(顧客とのコミュニケーションは取れているか)」「Convenience(顧客に利便性はあるのか?)」の頭文字です。
顧客側の視点から商品・サービスの特徴をとらえるために4C分析を行います。 - 4C分析と3C分析の違いは?
-
4C分析は、顧客視点に立ち、自社の販売方法の課題を浮き彫りにして改善する手法です。一方の3C分析は、顧客・競合・自社のそれぞれの立場から、自社商品がどういうポジションにあるのかを分析する手法です。