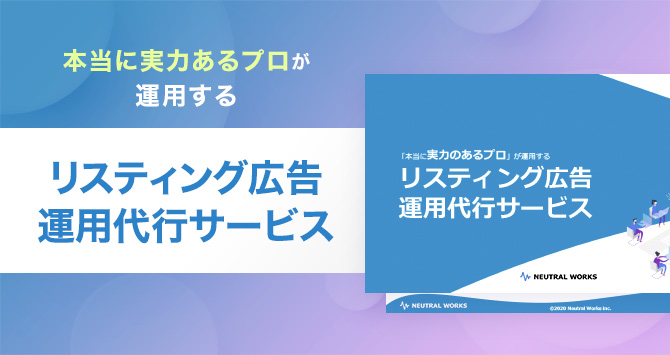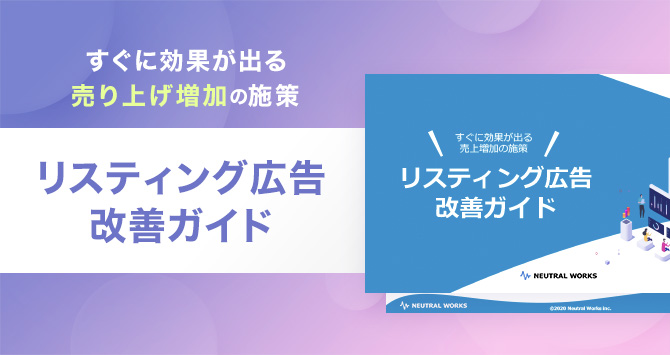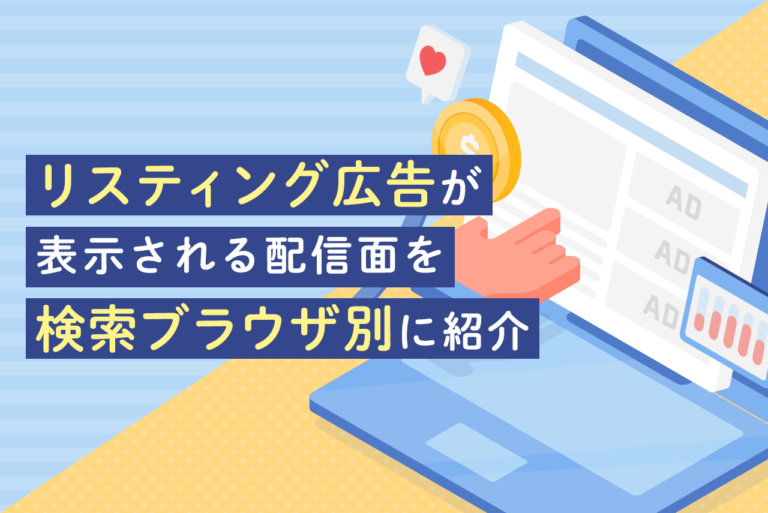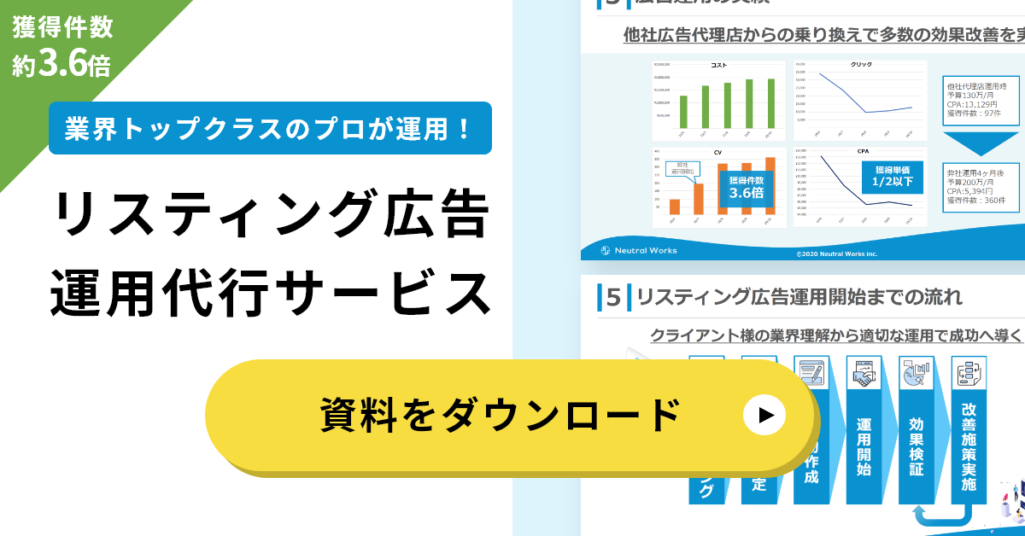この記事のポイント
この記事でおさえておきたいポイントは以下です。
-
スマート自動入札とは
-
スマート自動入札とは、Google広告で利用できる機能で、目標に応じて自動で入札単価が設定され、配信を調節する自動入札の一部であり、コンバージョンに特化した入札戦略のことです。
-
スマート自動入札のメリット
-
運用者が細かく調整しなくても自動で運用を遂行することが可能なため、最小限のコストでリスティング広告の運用を行うことができます。また、自動入札であっても、ユーザーに合わせて適切な広告を配信することが可能です。個人・会社ごとのビジネス目標に合わせて設定を自由に行うことができるところもメリットです。
-
スマート自動入札の注意点
-
キーワードなどを設定した後にAIが学習を開始するため、設定後はキーワードや予算を変更しないことが重要です。アカウントのコンバージョン数が少ない場合、GoogleのAIが判断する精度が低くなってしまう可能性があるため、データが少ない場合にはまずコンバージョンデータを貯めていきましょう。
リスティング広告を運用する中で、よく耳にするのが「スマート自動入札」。
「スマート自動入札を活用することでどんな利点があるのか分からない」
「スマート自動入札と自動入札の違いがいまいちよく分からない」
スマート自動入札に関して、上のように考えるリスティング広告運用者の方は少なくありません。
本記事では、リスティング広告におけるスマート自動入札の基礎やメリット、デメリットについてご紹介します。これからスマート自動入札を取り入れたリスティング広告運用を始めたい方や、スマート自動入札の理解度を深めたい方はぜひ本記事を参考にしてみてください。
<無料>資料ダウンロード
【本物のプロが運用】リスティング広告 運用代行
~業界トップクラスのコンサルタントがお客様のリスティング広告を運用!~
スマート自動入札とは

スマート自動入札とは、Google広告で利用できる機能であり自動入札戦略の一部。
【スマート自動入札の特徴】
- 機械学習を使用している
- コンバージョントラッキングデータに基づく
- 広告オークションごとに広告掲載の最適化を行う
- シグナルを元にした調整が可能
スマート自動入札では、高度な機械学習を使用してAIが入札戦略を立ててくれます。そのため、これまでのコンバージョンデータに基づき、最小限の手間で成果を出しやすくなると考えられています。また、スマート自動入札では、オークションごとに入札調整を行うことも可能です。
運用者が手動で調整するのは、手間と時間がかかり、対応できる施策の幅も狭まってしまいます。スマート自動入札なら、オークションごとにコンバージョン数やコンバージョン値の最適化を行うことができるため、細かな調整もスムーズに行うことが可能です。
加えて、スマート自動入札の特徴として、ユーザーのシグナルに基づいた運用である点も挙げられます。
【スマート自動入札に使用されるシグナル(例)】
- 所在地
- 曜日や時間帯
- デバイス
- ユーザー属性(性別、年齢)
- 検索語句
ユーザーの属性や環境に合わせて広告配信を最適化するため、よりターゲットにとって必要としている広告を届けやすくなります。
以上の特徴から、スマート自動入札は、収益に繋がらないクリックを減らし、収益性の高いクリックを多く獲得できるよう調整することで、費用を抑えながら多くのコンバージョンを獲得することができると言えます。
特に、コンバージョンやダイレクトレスポンスに注力している広告主に最適な機能です。
入札戦略とは
リスティング広告を運用する上で、さまざまな要素(アカウントやキャンペーン構成、キーワード、広告文など)を変更したり追加したりする必要があります。
ただ、全ての広告の要素を細かくチェックするのは、どれだけ時間があってもなかなか成し遂げられるものではありません。また、リスティング広告で成果を高めるためには、競合他社よりも優れた広告掲載面を獲得することも大切です。
リスティング広告で効果を上げるために活用したいのが「入札戦略」。入札戦略(ポートフォリオ戦略)とは、より集中して獲得を目指す要素(クリック、インプレッション、コンバージョンまたは視聴)に応じて戦略を指定することができる機能のこと。
キャンペーンの種類や広告掲載の目標に応じて、最適な入札戦略を利用することができます。
【入札戦略の種類】
- 手動入札
- 自動入札(スマート自動入札)
自動入札との違い
自動入札とは、目標に応じて自動で入札単価が設定され、配信を調節してくれる機能のこと。
【自動入札の種類】
- クリック数の最大化:サイト訪問者を増やす
- 目標インプレッションシェア:広告の可視性を高める
今回ご紹介するスマート自動入札は、自動入札の一部。スマート自動入札と自動入札の違いとして、入札戦略における目的が挙げられます。
自動入札は、自動で入札戦略を行う全ての機能を指します。一方、スマート自動入札は、自動入札の中でも特にコンバージョン獲得に特化した入札戦略を指します。
そのため、スマート自動入札はリスティング広告の運用に手間や時間をかけたくない方だけでなく、リスティング広告を通じてコンバージョンの獲得に注力したい方にぴったりな入札戦略と言えます。
スマート自動入札の種類

ここからはスマート自動入札の種類についてご紹介します。
スマート自動入札とは、自動入札の一部でありコンバージョンに特化した入札戦略のこと。自動入札戦略やスマート自動入札にはさまざまな種類が存在します。そのため、目標に応じて、自動入札戦略を設定することができます。
現在、スマート自動入札の種類は、以下の2つに分類されます。
①コンバージョン数の最大化
②コンバージョン値の最大化
本項では、スマート自動入札の種類別に可能なことや注意点についてご紹介します。また、2021年現在、これまでのスマート自動入札の種類分けとは異なっている部分もあるため、その点も合わせて解説していきます。
コンバージョン数の最大化
コンバージョン数の最大化とは、キャンペーンで設定した1日の予算を消化しながらコンバージョン数が最大化されるように入札調整を行う戦略のこと。
コンバージョン数の最大化では、広告が表示されるたびに、適切な入札単価が自動的に算出されます。予算に合わせて、最も低いコンバージョン単価が設定されるよう最適化される仕組みです。
コンバージョン数の最大化では、1日の平均予算をすべて使い切ることを目指して消化を進めていきます。そのため、現時点での費用が予算を大幅に下回っている場合、従来よりも費用が上回る可能性がある点に注意しましょう。
また、キーワードごとのクリック単価を設定することができません。そのため、クリックが少ないキャンペーンでは、クリック単価が上昇する可能性もあるためチェックが必要です。コンバージョン数の最大化は、費用削減よりもコンバージョン数を増やしたい場合におすすめです。
目標コンバージョン単価
コンバージョン数の最大化では、任意の目標コンバージョン単価を設定することができます。ここで設定した目標コンバージョン単価で、より多くのコンバージョン数の獲得を目指します。
ちなみに、個別のコンバージョン単価は目標額を上回るまたは下回る場合もあります。平均としては目標額に近づくよう設定されているため、さほど気にする必要はありません。
加えて、設定金額が低すぎると、コンバージョン数が減少してしまう恐れもあるため十分な予算を設定しておくことが大切です。目標コンバージョン単価は、これまでの運用結果などからすでに目標とする1件あたりのコンバージョン単価が決まっている場合におすすめです。
コンバージョン値の最大化
コンバージョン値の最大化とは、コンバージョンで発生する値(売上価格、収益、利益率など)が最も大きくなるように入札調整を行う戦略のこと。
コンバージョン値の最大化では、過去のキャンペーンデータとオークション時のコンテキストシグナルに基づいて、広告が掲載対象となるたびにクリック単価が自動で算出されます。
つまり、予算を消化しながらより価値の高いコンバージョンを獲得するように努める戦略です。広告に対して価値の高いユーザーへ配信を行っていきたい場合におすすめです。
目標広告費用対効果
コンバージョン値の最大化では、任意の目標広告費用対効果を設定することができます。目標広告費用対効果(ROAS)とは、広告費用で獲得したいコンバージョンの価値の平均のこと。費用に対してどれだけ成果を発生したかを重視したい場合におすすめです。
スマート自動入札戦略の構成変更
2021年4月より、検索キャンペーン向けの入札戦略の構成が変更されています。今回のスマート自動入札戦略の構成変更は、リスティング広告運用者がビジネスに最適な入札戦略を選びやすくする目的で行われたものです。
【(変更前)入札戦略の分類】
- コンバージョン数の最大化
- 目標コンバージョン単価
- コンバージョン値の最大化
- 目標広告費用対効果
【(変更後)入札戦略の分類】
- コンバージョン数の最大化
→目標コンバージョン単価(省略可)
- コンバージョン値の最大化
→目標広告費用対効果(省略可)
この変更をもって「目標コンバージョン単価」が「コンバージョン数の最大化」内へ、「目標広告費用対効果」が「コンバージョン値の最大化」内へ含まれるようになっています(それぞれ省略可能)。
以上の分類を見比べるとわかる通り、構成変更とされているものの、実際は入札戦略の分類がシンプルになっただけであり、入札戦略の内容に変動はありません。
スマート自動入札のメリット・デメリット
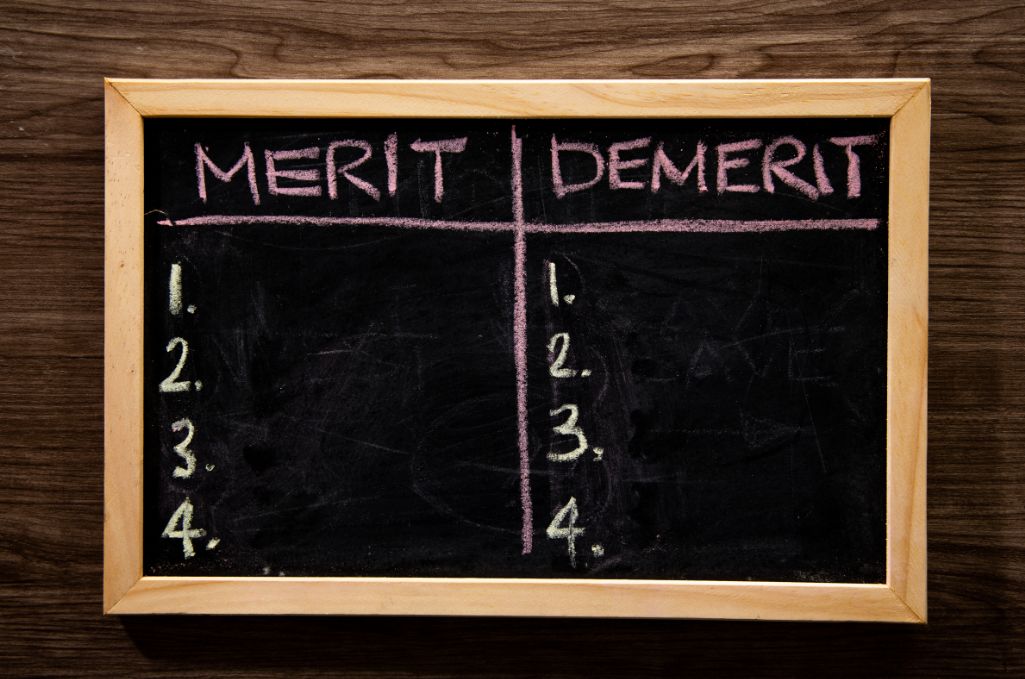
さまざまな入札戦略を実行することができるスマート自動入札。スマート自動入札では、AIによって自動で入札内容の調整や管理することができる点が魅力です。一方、コンバージョン数をはじめとしたデータがなければ正確な運用を実行しにくい点はデメリットとも言えます。
それぞれの目的や注意点だけでなく、以上のようなメリットやデメリットも知っておくことで、より効率的にリスティング広告の運用を行うことが可能です。
続いて、スマート自動入札のメリットとデメリットについてご紹介します。
スマート自動入札のメリット
- 高度な機械学習を活用している
- さまざまなシグナルが考慮される
- 掲載結果を管理できる
- 掲載結果レポートを活用できる
高度な機械学習を活用している
1つ目のメリットは、高度な機械学習を活用していること。
スマート自動入札は、機械学習アルゴリズムが広範囲のデータを学習し単価設定を行う仕組み。過去のデータに基づいて入札単価の調整を行うため、運用者が細かく調整しなくても自動で運用を遂行することが可能です。
そのため、これまでの運用にかかっていた時間や手間を省くことができ、最小限のコストでリスティング広告の運用を行うことができます。
さまざまなシグナルが考慮される
2つ目のメリットは、さまざまなシグナルが考慮されること。
スマート自動入札では、入札単価の最適化が行われるときにさまざまなシグナルが考慮されます。シグナルとは、ユーザーやオークション時のコンテキストを特定できる属性のこと。
【シグナルの例】
- デバイス
- 所在地
- 曜日と時間帯
- ブラウザ
- OS
- 実際の検索語句など
以上のようなシグナルをもとに、オークションごとに入札を調整することができます。つまり、自動入札であっても、ユーザーに合わせて適切な広告を配信することが可能だと言えます。
掲載結果を管理できる
3つ目のメリットは、掲載結果を管理できること。スマート自動入札では、個人・会社ごとのビジネス目標に合わせて設定を自由に行うことができます。
【例】
- アトリビューションモデルに合わせて入札単価を調整
- デバイス別に成果目標を設定
実現したい目標を細分化し、達成したい目標に沿って運用を行うことが可能です。
掲載結果レポートを活用できる
4つ目のメリットは、掲載結果レポートを活用できること。スマート自動入札では、入札管理を自動で行うだけではなく運用結果をまとめたレポートツールも利用することが可能です。
【掲載結果レポートの例】
- 入札戦略レポート
- キャンペーンの下書きとテスト
- シュミレーションなど
以上のようなレポートツールを活用することで、効率よくリスティング広告を運用することができます。
スマート自動入札のデメリット
- コンバージョン数に運用が左右される
- データの貯蓄が必須
- 期間限定キャンペーンでは手動運用が必要
コンバージョン数に運用が左右される
1つ目のデメリットは、コンバージョン数に運用が左右されること。
スマート自動入札では、過去のコンバージョンデータに基づいて入札調整が行われます。つまり、アカウントで十分なコンバージョン数を獲得できていないと、明確な分析を行うことが難しいのです。
もしコンバージョン数が少ない場合は、コンバージョンデータが蓄積されるまで様子を見る必要もあるでしょう。また、インプレッションを増やしたい場合などコンバージョンにこだわらない運用をしたい時もスマート自動入札以外の手段を考えた方が良いでしょう。
データの貯蓄が必須
2つ目のデメリットは、データの貯蓄が必須であること。
自動入札には、より正確に分析を行い運用を実施するために、最大2~3週間AIに学習させる必要があります。そのため、ある程度アカウントでデータを貯蓄しておくことが必須です。
期間限定キャンペーンでは手動運用が必要
3つ目のデメリットは、期間限定キャンペーンでは手動運用が必要であること。
セールやシーズン別(クリスマス、バレンタイン)などの期間限定キャンペーンでは、通常の分析・運用とは異なった調整が必要となる場合があります。そのため、イレギュラーな運用を行う際には、運用者が手動で調整する必要があります。
スマート自動入札の注意点

スマート自動入札では、機械学習に基づいて運用が行われるという特徴があります。特徴を押さえた上で、運用時に注意すべきポイントもいくつか存在します。
最後に、スマート自動入札の注意点についてご紹介します。
設定後はキーワードや予算を変更しない
1つ目の注意点は、設定後はキーワードや予算を変更しないこと。
スマート自動入札では、キーワードなどを設定した後にAIが学習を開始します。なぜなら、より精度高く自動入札を実行するためです。
しかし、設定後にキーワードの追加や予算変更を行うことで、機械学習結果が異なってしまう恐れがあります。その結果、スマート自動入札での入札精度が低くなってしまう可能性も考えられます。
通常2週間前後で機械学習は完了するため、一度設定を行ったらその期間はキーワードの追加や予算変更を行わないことをおすすめします。
入札単価はコンバージョン数に左右される
2つ目の注意点は、入札単価はコンバージョン数に左右されること。
スマート自動入札での入札単価は、コンバージョン数によって左右されます。そのため、アカウントのコンバージョン数が少ない場合、GoogleのAIが判断する精度が低くなってしまう可能性があります。
コンバージョンデータが蓄積されることで、安定して精度の高い入札を行うことができるようになるので、データが少ない場合にはまずコンバージョンデータを貯めていきましょう。
運用前に「下書きとテスト」でシュミレーションを行う
3つ目の注意点は、運用前に「下書きとテスト」でシュミレーションを行うこと。
これまで実施してきた手動での運用から、スマート自動入札へ変更することで効果が出なくなるのではないかと不安に感じる運用者の方は少なくありません。
そこでおすすめなのが「下書きとテスト」機能。実際に広告配信が行われるものの、現在のキャンペーンと同じ設定で入札戦略のみ変更したキャンペーンの作成が可能です。
スマート自動入札を設定し運用する前に「下書きとテスト」機能を活用して、キャンペーンの配信テストを行うと安心です。
まとめ

今回は、スマート自動入札の仕組みや種類、メリット・デメリット、注意点についてご紹介しました。
現在、リスティング広告を手動で運用しており、より手間や時間を省きたいとお悩みの運用者の方には、スマート自動入札の導入をおすすめします。ぜひこの機会に本記事を参考にして、スマート自動入札の導入を検討してみてください。
また、スマート自動入札を設定後、より細かく自社の運用を見直したい場合はプロに依頼するのもおすすめです。ニュートラルワークスでは、リスティング広告の運用手法に関する無料資料をご提供しています。合わせて無料相談も受け付けているので、お悩みの方はぜひ一度ご活用ください。