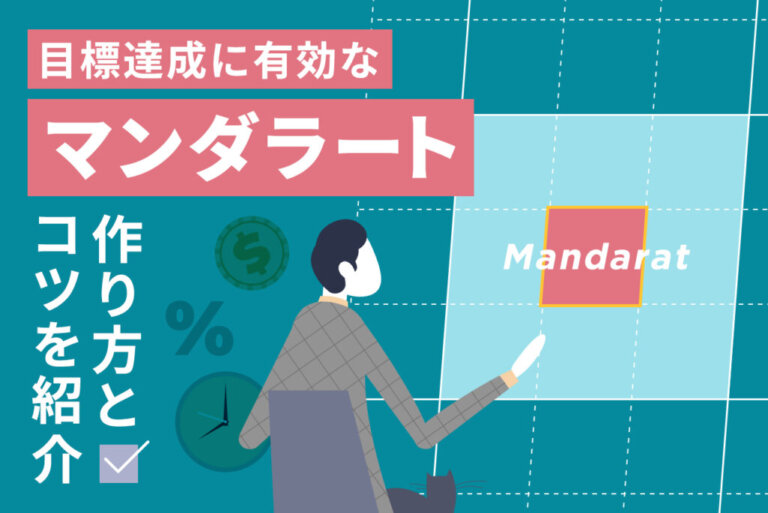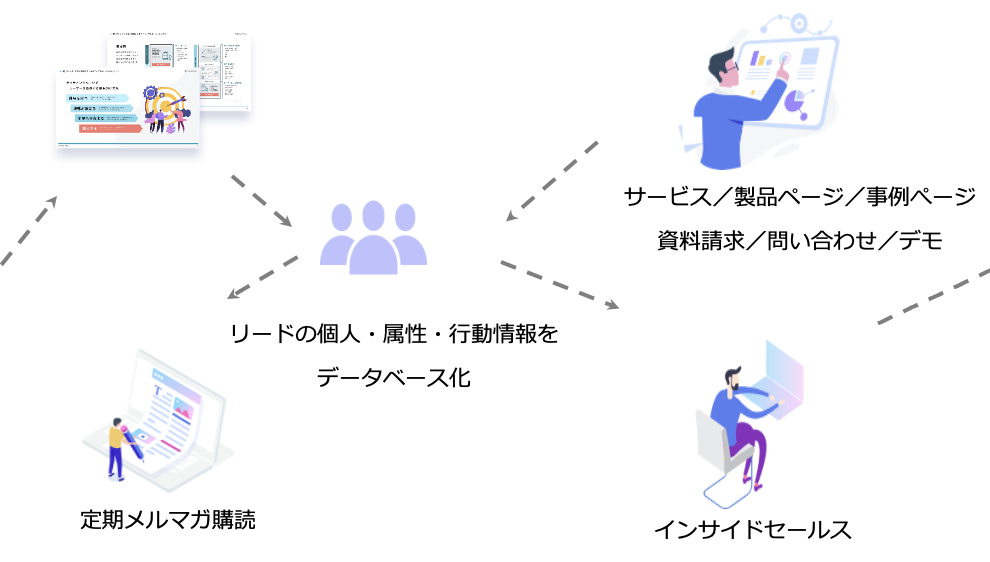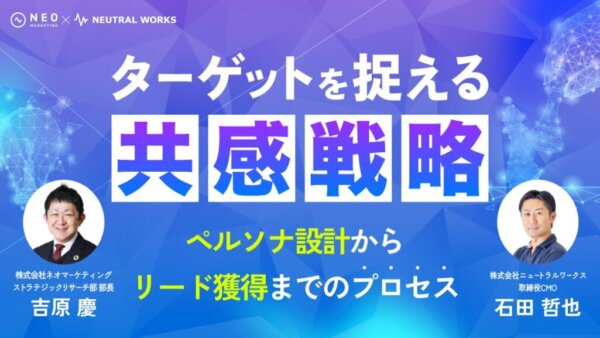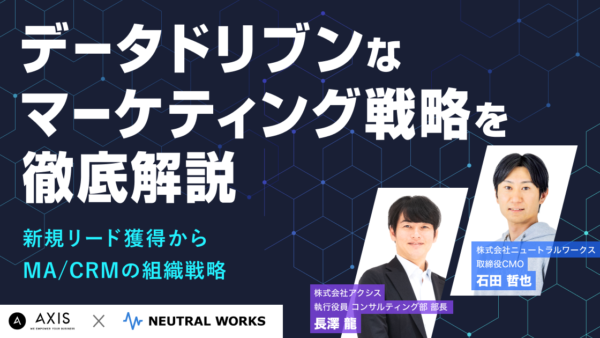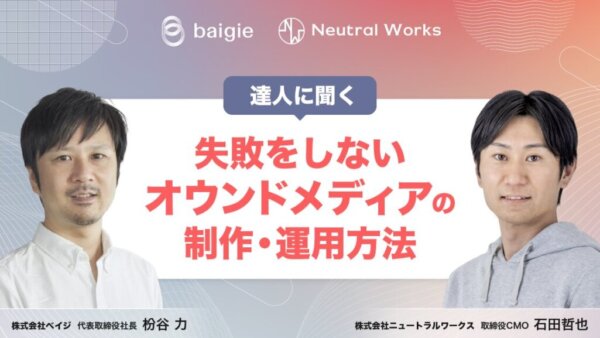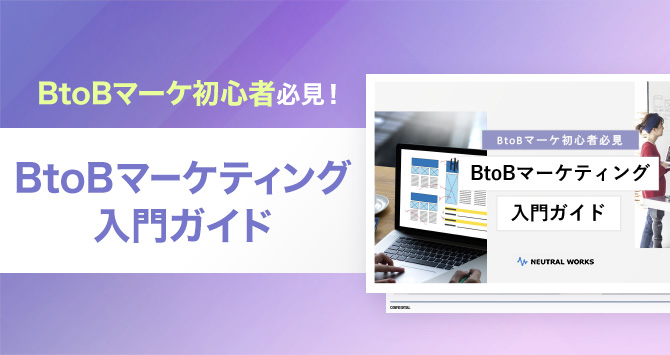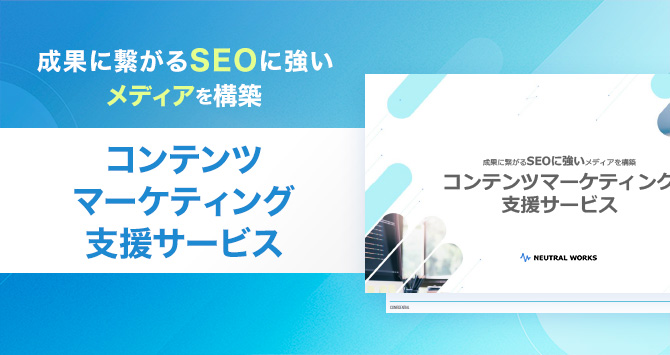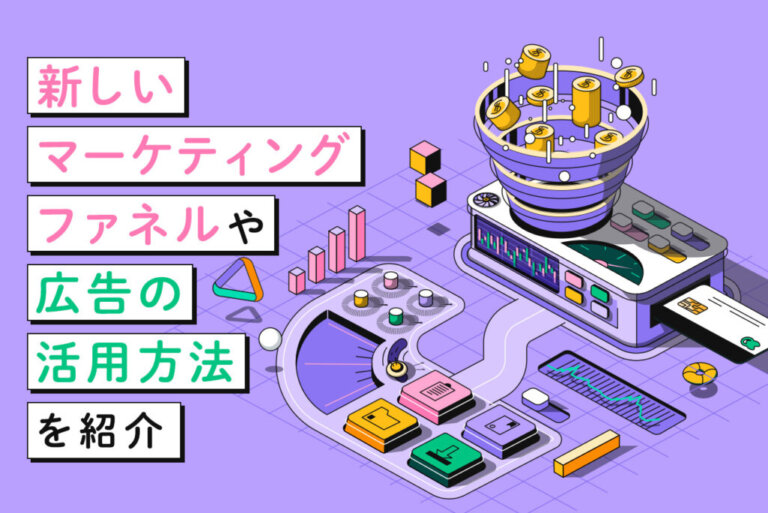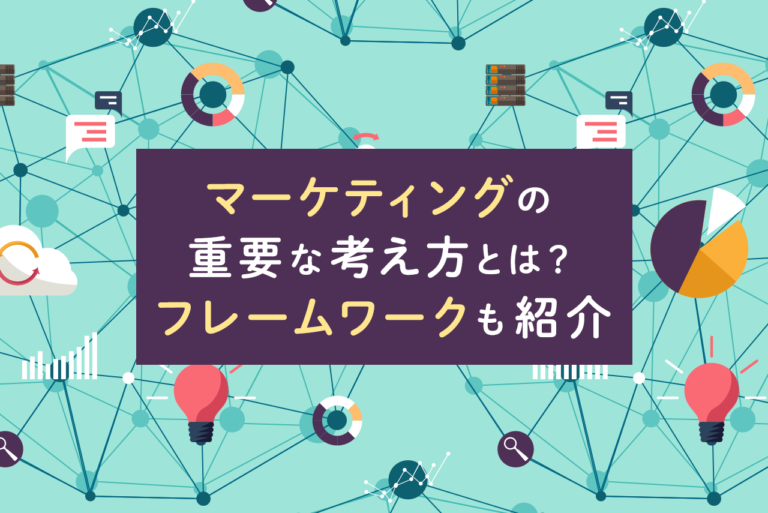KPTは、現状を整理して今後の行動指針を決めるためのフレームワークです。定期的にKPTを実施すれば、課題の早期発見やチーム力の向上につながり、効果的な業務が期待できるようになります。そこでこの記事では、KPTの概要やメリット、活用方法と有効なツールについて紹介します。
社内にKPTを取り入れて、業務の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方や経営者、個人で日々の仕事の振り返りを行いたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
<無料>資料ダウンロード
【サイト運営者必見】お客様成功事例集
集客と売上がアップした成功実績が見られる!
KPTとは振り返りのフレームワークのこと

KPTは「ケプト」と呼ばれるフレームワークで、以下の頭文字を取ったものです。
- Keep:良かった点を継続させる
- Problem:問題点・課題点を発見する
- Try:改善点・問題点に挑戦する
KPTは日本でも有名なフレームワークですが、これはアメリカの情報工学者であるAlistair Cockburn(アリスター・コーバーン)氏が「Reflection Workshop」で提唱した「The Keep/Try Reflection」という手法が元になっています。
このフレームワークでは、以下3つの要素に分けて振り返りを行うように推奨されていました。
- What we should keep.…続けるべきこと
- Where we are having ongoing problems. …今抱えている問題
- What we want to try in the next time period. …次にトライしたいこと
この手法が日本で独自の形で変化し、アジャイル開発における振り返りに適したフレームワークとして、広まっていきました。実際にKPTを行う場合は、ホワイトボードを「Keep」「Problem」「Try」の3つのグループに分けて、それぞれの内容をポストイットに書いて貼り付けていきます。
KPTは仕事やプロジェクトの改善を加速化させるフレームワークです。KPTを行うと振り返るべき項目を見える化し、整理させることができます。そのため個人だけでなく、チームでも「何をすれば良いのか」が明確になります。
KPTの目的
KPTを行う目的は、課題を共有して改善が必要なものを見える化することです。シンプルな方法ではありますが、大人数でも活用できるため、振り返りには最適な手法だとされています。例えば、大きなプロジェクトを進めていると、営業担当者やディレクター、エンジニア、デザイナーなどさまざまな職種の人々がチームになって動くことがあります。
このような場合、他の職種の人がどんな業務を行っているのか、どんな課題があるのか、何をゴールに設定しているのか、といったことを把握することは難しいです。そこでKPTを用いることで、チームでの振り返りができます。職種に限らず、プロジェクト単位で行えるので、大変便利です。
YWTとの違い
KPTと同じように振り返るためのフレームワークに、YWTというものがあります。YWTとは「日本能率協会コンサルティング」から提唱されているもので、以下の頭文字を取って名付けられています。
- Y…Yattakoto(やったこと)
- W…Wakattakoto(分かったこと)
- T…Tuginiyarukoto(次にやること)
これらの3段階に分けてフレームワークを行うことで、業務に対する振り返りが簡単になります。KPTとYWTの違いは、個人単位で行うかチーム単位で行うかという点です。KPTはホワイトボードとポストイットを使ってチーム単位で行うことを目的としているのに対し、YWTは個人単位で行うことを目的としています。
KPTのメリット

KPTを行うことで得られるメリットは、以下の4つです。
- 課題を可視化・早期発見できる
- チーム全員が課題に向きあえる
- チーム全員が次に何をすべきか明確になる
- 前向きな振り返り・反省ができる
メリット1.課題を可視化・早期発見できる
まず、KPTには課題を可視化・早期発見できるメリットがあります。プロジェクトが完了してから次のプロジェクトに移る前に、課題を共有することは大切です。しかし振り返りの機会をつくらない限り、課題を共有することは難しいでしょう。また、職種が異なる人たちでチームを構成していると、さらに課題を理解しあうことが難しいです。
そこでKPTを用いることで、プロジェクトの課題を可視化・早期発見ができます。プロジェクトや現状の組織に対して課題を感じていても、共有する機会がないとなかなか課題を認識して改善することができません。
メリット2.チーム全員が課題に向きあえる
KPTを使うと、チーム全員が課題に向きあえるのもメリットの一つです。プロジェクトが完了してしまうと、振り返りを行わないまま次のプロジェクトに進んでしまうこともあります。すると、抱えている課題が分からないまま次のプロジェクトに進んでしまい、同じ問題を繰り返してしまう可能性もあるでしょう。
KPTを取り入れれば、チーム全員で課題に向きあえます。仮に別の職種の人が抱えている課題であったとしても、チームとして課題に取り組むことで、カバーできる可能性があります。
メリット3.チーム全員が次に何をすべきか明確になる
また、KPTを行えばチーム全員が次に何をすべきか明確になります。チームで課題を共有することで、その課題に対して何をすべきかが見えてきます。また、上司として部下がいる場合、部下の問題や課題を把握することが可能です。
メリット4.前向きな振り返り・反省ができる
最後のメリットとして、前向きな振り返りや反省ができることが挙げられます。チームで単に振り返りだけをしても、反省で終わってしまうこともあるでしょう。しかし「Try」で改善点・問題点に挑戦することを共有すれば、前向きに課題を共有することが可能です。
また、KPTを行う機会を導入することで、振り返りや反省をすることが習慣になります。やっていくうちに短い時間で精度を高めていくことも可能でしょう。部下の教育にも役立つので、ぜひ取り入れるべきフレームワークです。
KPTの進め方
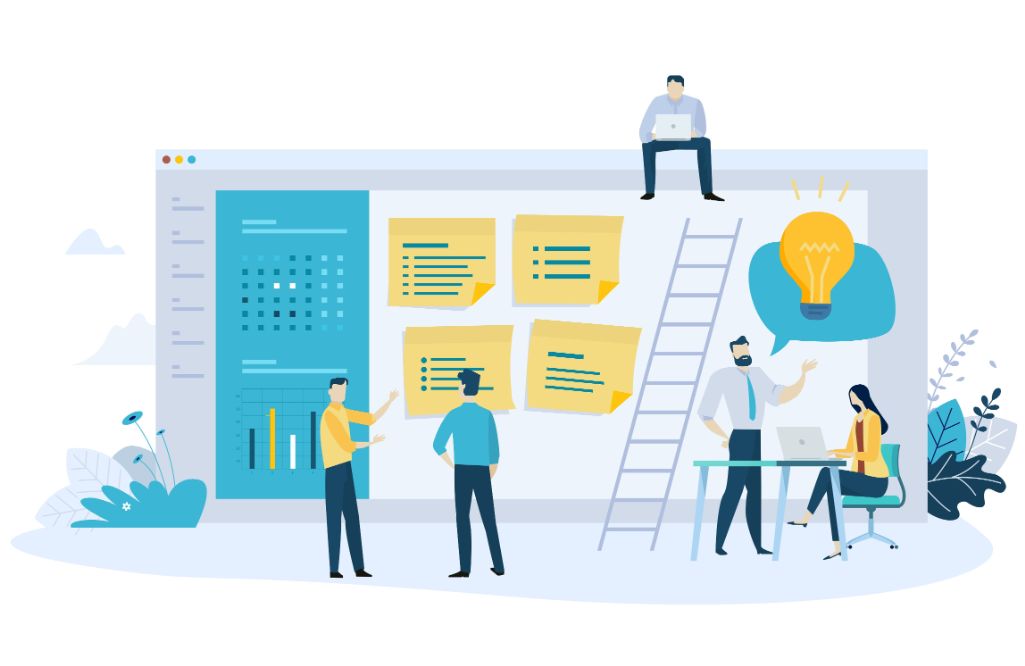
では、KPTではどのように取り入れればいいのでしょうか。KPTは以下4つのステップで進めていきます。
- KPTをするための準備をする
- 「Keep」と「Problem」を書いてみる
- 具体的な行動につながる「Try」を決める
- KPT実行後に再度KPTを振り返る
ここからは、KPTの具体的な活用方法をステップごとに解説します。
1.KPTをするための準備をする
| アナログ | デジタル |
|---|---|
| ・ホワイトボード ・ボールペン ・ポストイット |
・KPTを実施できるツール |
まず、KPTを行うための準備をしましょう。KPTにはアナログで行う方法とデジタルで行う方法の2種類があります。それぞれ準備するものは上記のとおりです。アナログの場合は、ホワイトボード、ボールペン、ポストイットの3つ、デジタルで行う場合は、KPTを実施できるツールを用意しましょう。
ツールについては「KPTに役立つツール4選」で詳しく紹介しますので、以降はアナログで進める場合の方法を中心に解説します。アナログの方法では、ホワイトボードを使って以下のように区切り、それぞれに「Keep」「Problem」「Try」と書き込みます。「Keep」「Problem」「Try」は以下のような意味あいとなっています。
成功したこと
このまま継続すべきことTry
問題や課題に対する解決策
新しく挑戦すること問題点や課題点
| Keep |
|---|
| Problem |
チームで行う場合は、プロジェクトやそれぞれの仕事内容を共有しておきましょう。何も情報がないまま始めてしまうと、お互いに理解ができないこともあります。また、ポストイットは使いやすいように個人の手元に配っておくといいでしょう。
2.「Keep」と「Problem」を書いてみる
KPTの準備が整ったら、実際に手を動かして進めてみましょう。まずは、プロジェクトや活動内容の結果をポストイットに書き出していきます。書き出しが完了したら、それぞれの内容を「Keep」また「Problem」に貼り付けていきます。成功したことやこのまま継続すべきことは「Keep」へ、問題点や課題点となるものは「Problem」へ分類して貼り付けます。
ここでポイントは、「Problem」を貼り付ける際に、どうして課題や問題となっているのかを同時に考えることです。思いついたらポストイットにメモしておきましょう。
3.具体的な行動につながる「Try」を決める
「Keep」と「Problem」の書き出しが完了したら、続いて具体的な行動につながる「Try」を決めていきます。Tryでは問題や課題に対する解決策、新しく挑戦することを書き出しましょう。ここでTryは、具体的なアクションを提示することが大切です。
例えば課題点に「顧客からの指示書を捉え間違えた」という項目があった場合、ここで「指示書を読み間違えない」とするのはよくありません。それは、「間違えない」ための具体的な行動が分からないからです。
この場合は例として、「オリジナルの指示書と社内の指示書を付き合わせてミスを事前に防ぐ」など、具体的な行動を示す必要があります。なお、チームで行っている場合も、まずは各自で解決策や挑戦することを考えて思いつくだけ書き出していくといいでしょう。書き上がったらTryのエリアに貼り出します。
4.KPT実行後に再度KPTを振り返る
3つの枠が完了したら、再度KPTを振り返りましょう。特にチームで行っている場合は、課題や具体的な行動への認識を共有する必要があります。チーム内で上がった「Keep」「Problem」「Try」についてそれぞれ必要な問題か、解決策は正しいかなどを話し合いましょう。
KPTを円滑に進めるために注意すべきポイント

KPTを円滑に進めるためのコツとポイントは4つあります。
- チームの仕組みに問題・原因がないか確認する
- 意見しやすい環境をつくる
- ファシリテーターを設置する
- 継続してKPTを行う
それぞれ見ていきましょう。
チームの仕組みに問題・原因がないか確認する
まず、再度KPTで振り返る際に、チームの仕組みに問題・原因がないか確認しておきましょう。チームでKPTを行う場合、まずは個人で書き出すようにお伝えしました。個人で書き出すと、個人の成果や問題に目が行きがちで、チームの仕組みや働きを忘れることが多いです。
そのため、一度「Keep」「Problem」「Try」が出揃ったら、チームの仕組みや動きという別の視点から見つめ直すと効果的です。
意見しやすい環境をつくる
大事なことは個人が意見を言いやすい環境をつくることです。そこで重要なのが意見を否定しないことです。インサイトを引き出したり、アイデア出しをしたりするケースでは、大事なことが一つあります。それは意見を否定しないこと。重要ではないと個人が思っていることが、実はチームとしては重要なことが往々にしてあります。
しかし、意見が否定される環境では、そういった意見が発言されなくなってしまいます。誰からでも細大漏らさず意見が述べられる環境をつくりましょう。
ファシリテーターを設置する
進行役を決めると円滑にKPTを行うことができるでしょう。客観的に問題を見つめることで、新しく見えてくるものがあります。なお、会議の進行や段取りが整うので、限られた時間を有効活用できます。
継続してKPTを行う
KPTが機能するには継続して行うことが必須です。そこで大事なのが、前回の「Try」について、どうだったのかを振り返ることです。そして、「keep」と「Problem」を出していく。こうすることで自然と継続性が生まれます。
継続していく中で、KPT がうまく行き、成果につながることが出てきます。そうなると、KPT を継続して行うことのモチベーションが維持されていくでしょう。チームの進化を体感し、さらに継続して行うようになります。
KPTの失敗例
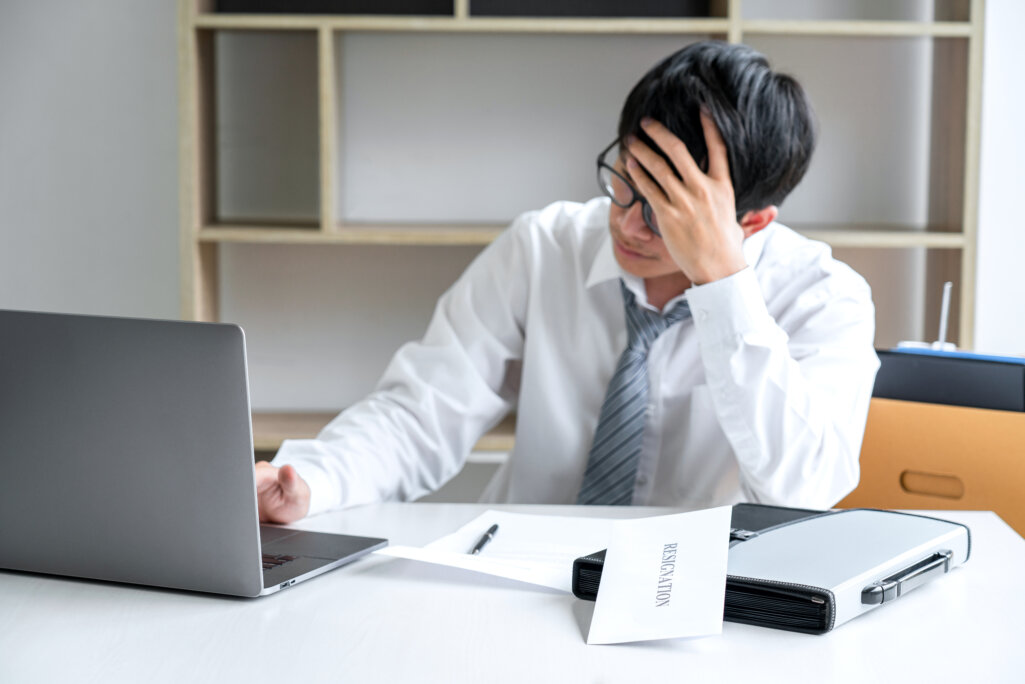
KPTを行っていると、よく陥りがちな失敗例があります。それは「Keep」「Problem」「Try」を出していく中で、「Keep」よりも「Problem」に注力してしまうことです。課題や問題点が出てくると、どうしてもそれを解決しようとしてしまうのが人の性と言えます。
しかし、継続すべきことを続けていくのと、課題を解決するのとでは労力が異なります。後者に注力するとどうしても労力がかかり、いつしか継続すべきことが疎かになってしまうのです。
また、「Problem」に対する「Try」について検証するには、同じ「Problem」が発生する必要があります。繰り返し作業であれば同じ問題がすぐに発生するでしょうが、通常はそういうケースは少ないでしょう。検証ができないことで成果・進化を実感できずにモチベーションが維持されなくなってしまいます。その結果、KPTを行わなくなってしまうのがよくある失敗事例です。
KPTに役立つツール4選

KPTというフレームワークはやり方に決まりはないですが、実はツールを用いて行うことも可能です。ここからは、KPTを行う際に役立つツールを紹介します。
1.無料のタスク管理ツール「Trello」

出典:Trello
| ツールの特徴 | ・課題ごとに「カード」単位で登録できる ・分類やコメント、ファイルの添付が可能 |
|---|---|
| ツールのメリット | ・濃密に仕事の振り返りができる |
| 料金 | 無料〜 |
デジタルでKPTを行う方法の一つが、「Trello」という無料のタスク管理ツールを活用する方法です。Trelloの特徴は、課題ごとにタスクを登録できる点にあります。Trelloには「カード」と呼ばれるタスク管理システムがあり、カードを活用すれば課題ごとに管理が可能です。また、カードを分類したり、コメント、ファイルの添付ができるので、濃密に仕事の振り返りができます。
なお、Trelloは無料プランから有料プランまで用意されています。有料プランは、スタンダードプランの5ドルから利用が可能です。
2.KPTの進捗管理ができる「Wistant」

出典:Wistant
| ツールの特徴 | ・個人のタスクの進捗を「%」で確認できる ・外部ツールとの連携が可能 |
|---|---|
| ツールのメリット | ・メンバーごとの進捗状況を確認できる |
| 料金 | 2カ月目から一人あたり980円(税抜き) |
WistantはKPTの進捗管理ができるツールで、個人にフォーカスすることが可能です。例えば、Wistantでは個人のタスクの進捗を「%」で確認できます。個人のタスクを管理する上司にとっては、数字で確認できるのでとても分かりやすいでしょう。
また、「Slack」や「Chatwork」のような外部ツールとの連携も可能です。ただし、Wistantは初月のみ無料で、2カ月目から1カ月月に一人あたり980円(税抜き)の料金が発生します。
3.自動でログ収集ができる「ラジログ」

出典:ラジログ
| ツールの特徴 | ・外部ツールとの連携が可能 ・振り返り項目をカスタムできる |
|---|---|
| ツールのメリット | ・個人の振り返りから1on1まで活用できる ・外部ツールと連携してコミュニケーションが取れる |
| 料金 | 一人あたり500円(税込み) |
ラジログは、自動でログ収集ができる便利なツールです。ラジログでは外部ツールとの連携が可能なので、コミュニケーションを取りやすいというメリットがあります。また、振り返り項目をカスタムできるので、チーム内で課題を共有しやすいです。
なお、個人の振り返りにも対応しているので、幅広い用途で使用が可能です。ただし、ラジログは一人あたり1カ月500円(税込み)が発生します。
KPTの実践例

最後に、KPTを実施している企業の実践例を紹介します。KPTを実施している企業には、エウレカやサイボウズがあります。株式会社エウレカは、マッチングアプリ「Pairs(ペアーズ)」を運営している企業です。エウレカでは日々発生する課題に対して素早い対応ができるように、KPTを用いて振り返りを行っています。
KPTの実施方法はいたってシンプルで、ホワイトボードとポストイットを用いてアナログ方式で行っています。エウレカのエンジニアチームは、以下の2つのポイントを意識しています。
- 課題を放置せず可視化することでチームで共有する
- 誰かを責めるのではなくどう改善できるかにフォーカスする
日々の業務があると、問題や課題が発生しても業務を優先しがちです。しかしそうならないように振り返りの機会を設けることで、課題をチームで共有できます。また全員が発言をしやすいような環境をつくることも、工夫の一つです。そして、「サイボウズ Office」シリーズなどを手掛けるサイボウズでは、開発メンバー全体で2週間に1度KPTによって振り返りを行っています。
そんなサイボウズでは、普段からの気付きをkintoneというツールにメモをしておく文化があります。これにより、振り返りがスムーズになるそうです。
KPとは?のまとめ

KPTは効果的な振り返りができるフレームワークです。チームで課題を共有し、次にすべきことを把握できます。KPT活用法のポイントは、進行役を設けることや、チームの仕組みにも目を向けることでした。KPTには役立つツールもあるので、取り入れると効果的です。
とはいえど、フレームワークを行ってもなかなかプロジェクトが改善されないこともあるでしょう。こうした場合、コンサルティングなどのご要望がありましたら、ニュートラルワークスにぜひご相談ください。
KPT法のよくあるご質問
- KPTとは?
-
KPTは「ケプト」と呼ばれるフレームワークで、「Keep」「Problem」「Try」の頭文字を取ったものです。KPTを行うと振り返るべき項目を見える化し、整理させることができます。
- KPTの目的は?
-
KPTを行う目的は、課題を共有して改善が必要なものを見える化することです。シンプルな方法ではありますが、大人数でも活用できるため、振り返りには最適な手法だとされています。
- KPTとYWTとの違いは?
-
KPTとYWTの違いは、個人単位で行うかチーム単位で行うかという点です。KPTはホワイトボードとポストイットを使ってチーム単位で行うことを目的としているのに対し、YWTは個人単位で行うことを目的としています。