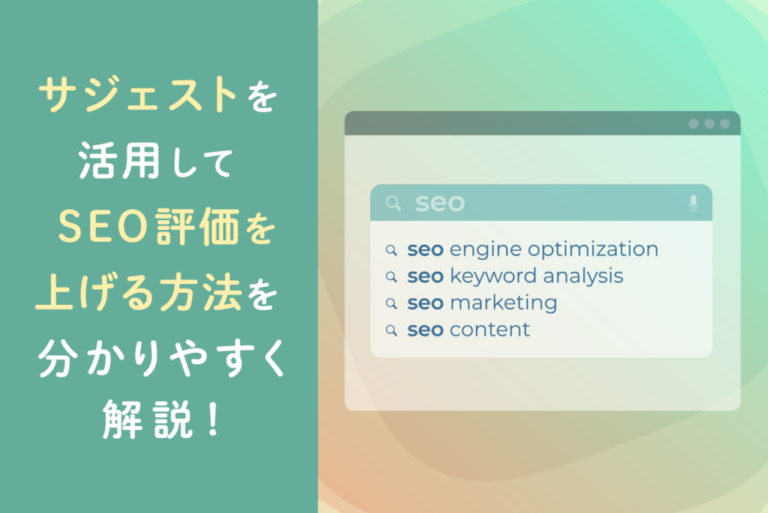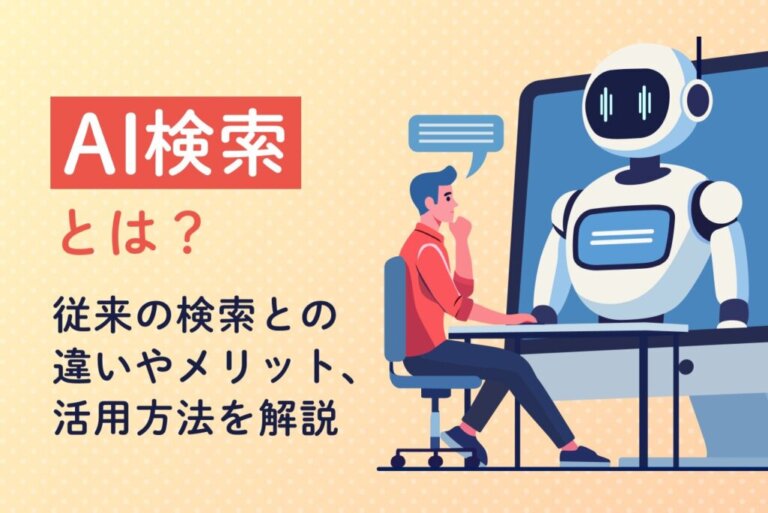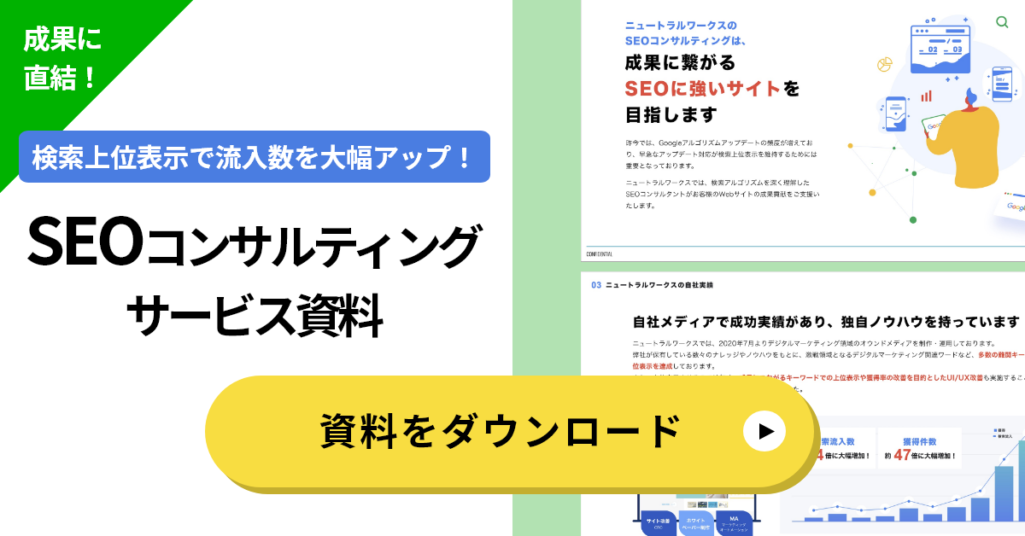この記事のポイント
-
Googleアルゴリズムとは
-
Googleアルゴリズムとは、Googleの検索エンジンがインターネット上の情報をどのように処理し、検索結果として表示するかを決定する一連の規則や計算式のことです。キーワードとの関連性、コンテンツの品質、Webサイトやリンクの権威性、ユーザー体験などさまざまな要因が考慮されます。
-
Googleアルゴリズムのアップデートとは
-
Googleアルゴリズムのアップデートとは、Googleが検索結果の品質を向上させるために行うアルゴリズムの改善や修正のことです。
-
Googleアルゴリズムの変更に適応したSEO戦略
-
E-E-A-Tは、サイトやコンテンツの専門性、権威性、信頼性を評価する基準であり、高品質なサイトが検索結果で優遇されるように作用するため強化していくことが重要です。お金や健康に大きな影響を与える可能性のあるYMYL(Your Money Your Life)に関わるコンテンツは特に厳格に評価されるため特に注意しましょう。
Googleアルゴリズムは、インターネット上の情報をどのように処理し、検索結果として表示するかを決定するGoogleの検索エンジンの心臓部です。
この記事では、Googleアルゴリズムに関係する要素、そして主要なアップデートについて解説します。
また、SEO対策の戦略としてアルゴリズムに適応する方法についても掘り下げていますので、ぜひ最後までお読みください。
<無料>資料ダウンロード
【サイト運営者必見】SEO対策成功事例集
実例から学ぶ、急成長を遂げたストーリーが見られる!
目次
Googleアルゴリズムとは

Googleアルゴリズムとは、Googleの検索エンジンがインターネット上の情報をどのように処理し、検索結果として表示するかを決定する一連の規則や計算式のことです。
アルゴリズムは、ユーザーの検索クエリに最も関連性の高いものかつ、信頼できるWebページを識別し、ランク付けするために用いられます。
また、Googleアルゴリズムはキーワードとの関連性、コンテンツの品質、Webサイトやリンクの権威性、ユーザー体験などさまざまな要因を考慮します。
検索結果の精度を高めるために定期的に更新され、新しいWeb標準やユーザー行動の変化にも適応しています。
Googleアルゴリズムに関係する主な要素

Googleは、結果を自動的に生成する仕組みを公開しています。これらが実際の検索結果にどのくらい影響しているかは不明ですが、Googleアルゴリズムを理解するうえで、以下の5つが重要な要素といえます。
- 検索キーワードとWebページとの関連性
- 検索ニーズの把握
- コンテンツの品質
- ユーザビリティ
- 文脈の考慮
検索キーワードとWebページとの関連性
Googleアルゴリズムは、検索キーワードとWebページとの関連性を重視します。
キーワードがページの内容とどれだけ密接に関連しているかを評価し、ユーザーの検索意図に合致するページを上位に表示します。
したがって、キーワードの適切な使用とそのキーワードに関連する価値ある情報の提供が重要です。キーワードの自然な組み込みと、トピックの深堀りが成功の鍵といえます。
検索ニーズの把握
Googleアルゴリズムは、検索ニーズを理解し最適な結果を提供することを目指しています。
「ユーザーが何を求めているのか」「どのような情報が役立つのか」を把握することが、SEOの中心となるため、ターゲットのニーズを研究し、そのニーズに応える高品質なコンテンツを作成することが重要です。
コンテンツの品質
Googleアルゴリズムは、コンテンツの品質も評価します。
高品質なコンテンツと評価されるためには、オリジナル性・専門性・信頼性そしてユーザーへの価値提供が求められます。
詳細な調査や正確な情報など、ユーザーにとって有益なコンテンツを作成することが、検索順位を高めるためには不可欠です。
ユーザビリティ
ユーザビリティも、Googleアルゴリズムにおける重要な要素です。
誰もが使いやすいWebサイトは、ユーザーの滞在時間を延ばし、エンゲージメントを高めます。
応答速度、ナビゲーションの容易さ、モバイルフレンドリーなデザインなどが、ユーザビリティを高める重要な要因です。良いユーザー体験は、検索順位向上にもつながります。
文脈の考慮
Googleアルゴリズムは、検索クエリの文脈を考慮しています。これは、クエリの背景やユーザーの検索意図に合致する結果を提供できるよう重視しているからです。
このため、作成するコンテンツはキーワードだけでなく、トピック全体を包括的に扱う必要があります。
ユーザーの検索意図を理解し、それに対応する詳細かつ関連性の高いコンテンツを作成することが効果的なSEO戦略の鍵となります。
 Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説
検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。
Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説
検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。
Googleアルゴリズムの進化を指すのが「アップデート」

アップデートとは、Googleが検索結果の品質を向上させるために行うアルゴリズムの改善や修正のことです。
Googleアルゴリズムの歴史は、インターネットの進化と密接に関連しており、初期の単純なキーワードベースの検索から、現在では機械学習による複雑な理解と分析が可能になっています。
また、アップデートには小規模なものから、検索結果に大きな影響を与えるものまであります。
Googleアルゴリズムの主なアップデート
| 種類 | 概要 | |
| 2011年 | パンダアップデート | コンテンツの品質に関するアップデートです |
| 2015年 | モバイルフレンドリーアップデート | スマートフォン対応に関するアップデート |
| 2016年 | ペンギンアップデート | リンクに関するアップーデート |
| 2017年 | ヘルスケアアップデート | 医療や健康に関する情報を精査するためのアップデート |
| 2018年 | スピードアップデート | Webサイトの表示速度に関するアップデート |
Googleアルゴリズムの主なアップデートとして、コンテンツの品質を重視する「パンダアップデート」や、不自然なリンクを対象にした「ペンギンアップデート」、モバイルフレンドリーを促進する「モバイルフレンドリーアップデート」、お金や病気に関する「ヘルスケアアップデート」などがあります。
これらはWebサイトの検索順位に影響を及ぼし、SEO戦略においても重要なポイントとなります。
なぜなら、アップデートは高品質なコンテンツを作成し、ユーザーに最適な体験を提供するWebサイトを優遇する傾向にあるからです。
検索アルゴリズムの大規模な更新を「コアアルゴリズムアップデート」と呼ぶ
コアアップデート(コアアルゴリズムアップデートの略称)は、一般的に年に数回行われ、Webサイトのランキングに大きな影響を及ぼす場合があります。
コアアップデートでは、検索アルゴリズム全体の機能やパフォーマンスが総合的に変更され、これにより特定のWebサイトやページランキングが大きく変動することがあります。
Googleアルゴリズムに順応するためのSEO戦略

Googleアルゴリズムの変更に適応するためには、常に最新トレンドに敏感である必要があります。
キーワードの最適化やユーザー体験の改善、モバイル対応と高品質なコンテンツの提供などがあり、いずれも非常に重要です。
また、Googleのガイドラインに準拠し、検索エンジンに対して正直なアプローチを取ることも基本といえます。
GoogleアルゴリズムとE-A-Tの重要性
E-E-A-Tは、サイトやコンテンツの専門性、権威性、信頼性を評価する基準であり、高品質なサイトが検索結果で優遇されるように作用します。
E-E-A-Tを高めるための方法には、専門機関や専門家に監修や執筆を依頼するなどがあります。その分野の専門家や機関に関わってもらうことで、より正確な情報を届けることが可能となるでしょう。
また、信頼性の高いデータベースやサイトからの被リンクも鍵となります。専門機関や専門家から被リンクをもらうことで、E-A-Tを強化していくのも方法の一つといえます。
 E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOで重要なGoogleの評価基準を解説
E-E-A-Tは、Googleがウェブサイトの品質評価に用いる基準で、SEOにおいて重要な要素です。この記事では、各要素の意味やSEO対策への影響、具体的な改善方法について詳しく解説しています。
E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOで重要なGoogleの評価基準を解説
E-E-A-Tは、Googleがウェブサイトの品質評価に用いる基準で、SEOにおいて重要な要素です。この記事では、各要素の意味やSEO対策への影響、具体的な改善方法について詳しく解説しています。
GoogleアルゴリズムとYMYL(Your Money Your Life)の重要性
YMYL(Your Money Your Life)は、お金や健康に大きな影響を与える可能性のあるコンテンツに関するGoogleの基準です。
この種のコンテンツに対しては、特に高い品質と正確性が求められ、Googleアルゴリズムによって厳格に評価されます。
トラフィックが減ったときは必ず原因を調べる
大規模なアルゴリズムアップデートが行われると、Webページの検索順位が下落することがあります。
しかし、トラフィックが減ったことを「悪い影響」と決めつけるのではなく、アクセス解析などによって、まずは正確な情報を把握しましょう。
検索順位の低下は必ずしも「Webサイトに問題があったから」というわけではないからです。それまで評価されていなかったWebサイトが、アルゴリズムの変動によって正当な評価を受け、順位を上げてきたというケースも多々あります。
アップデートの全貌がみえないうちに対策を講じるのは危険なため、Googleサーチコンソールを活用するなどして、アップデートの情報を冷静にリサーチしてください。
まずはGoogleアルゴリズムを理解することが大切

Googleアルゴリズムは、Webページをランク付けするための基本ルールです。
Googleアルゴリズムに順応するには、キーワードとの関連性が高く、信頼できる情報を提供することが重要であり、そのためには検索ニーズの把握、コンテンツの品質、ユーザビリティ、文脈の考慮が不可欠となります。
アルゴリズムのアップデートがいつ行われても問題ないよう、常にユーザー目線に立ち、価値あるコンテンツの提供を心がけていきましょう。
また、トラフィックの変動があった場合も常に、適切な分析とSEO戦略の見直しを行うことが重要です。
<無料>資料ダウンロード
【プロにお任せ】SEOコンサルティング
見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決